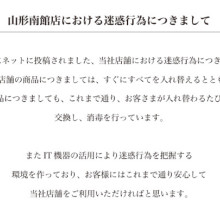空はどんよりしている。けど、残暑の空気は暖かい。
おばあちゃんの家から駅までは、健太君といっしょに歩いて、小一時間くらいの距離だ。
二人で並んで歩き始めたのに、健太君は途中で走りだした。少し進んだ先で立ち止まった。
振り返り、私を待っている。
追いつくと、片手を唇に当てながら聞いてきた。
「ねえ、お姉ちゃんは、なんで、お姉ちゃんなの」
健太君は首をかしげて、不思議そうな顔をしている。口もとが膨らんでいて、かわいい。
触ったら、やわらかそう。
健太君は、よく食事のときに、脇から伯父さんのあぐらの中に座り込んでしまうことがあった。
それから、ボールとグローブを持って外へ遊びに行くと、伯父さんの背中に飛びついたり、伯父さんのお腹に頭を押しつけて、さらさらの髪の毛をぼさぼさにしていたりした。
そんなときの伯父さんは、いつも「やめろ、やめろ」と言うけど、うれしそうだ。
健太君は、もの心がついてからは、私に抱きついたりはしなくなった。でも、赤ちゃんのころは、私の胸で、泣いたり、笑ったり、暴れ回ったりしていた。
私は健太君のお姉ちゃんで、健太君は私のかわいい弟だ。
「お姉ちゃんはね、健太君のことが大好きだから、お姉ちゃんなのよ」
そう告げたら、健太君は、口もとをほころばせて、それからまた駆けていった。
デパートは、三階建ての大きなビルだった。屋上が遊園地になっていた。
けど、健太君よりももっと小さな子どもたちが、馬の乗り物にまたがったり、汽車に乗ったりしていた。
健太君は、ここへはよく来るようで、一目散に、アスレティックコースへ走っていった。
網をつたって台によじ登り、木橋の途中で、丸太の透き間へ体をすべり込ませた。そのまま近道をして、ゴールへたどり着いてしまった。
一周して戻ってきた健太君は、おでこに汗をかいているけど、息は整っている。
健太君が体を寄せてきた。それから、珍しく、私の服を引っぱった。
(つづく/文・竹内みちまろ/イラスト・ezu.&夜野青)