新日本
-
スポーツ 2017年08月03日 17時30分

猪木以来の快挙なるか? 中邑真輔、シナとの日米決戦を制しWWE最高峰王座に挑戦!
世界一のプロレス団体、WWEのTVショー『スマックダウン』が米国現地時間8月1日オハイオ州クリーブランドで行われ、元新日本プロレスの中邑真輔がWWE王座挑戦権を賭けてジョン・シナとの日米夢の初対決に挑んだ。 試合は、中邑は挨拶がわりに得意の延髄斬りやけいれん式ストンピングを繰り出し、さらにシナがファイブ・ナックル・シャッフルを決めようと「You can't see me」のポーズをすると、中邑は下から腕十字、さらには三角締めと巧みな関節技を繰り出した。勢いに乗る中邑はキンシャサを狙うも、これをかわされると今度はシナがSTFで中邑を締め上げる。目まぐるしい技の攻防に会場からはどよめきが起こった。 中邑は打撃からのキンシャサをシナに叩き込み、さらに2発目を狙うも、今度はシナが渾身のアティテュード・アジャストメントを決める。これで試合は決まったかに思えたが、なんと中邑はこれをカウント2で返し、さらに追い打ちをかけるシナを今度は中邑が持ち上げてリバースパワースラム、さらに全身をたぎらせたキンシャサを決めて勝負あり。中邑は完璧な3カウントをシナから奪い日米ドリームマッチを制した。シナとの初対決で勝利をもぎ取った中邑は、真夏の祭典『サマースラム』でのWWE王座挑戦権を獲得。 WWE王座戦が行われるPPV『サマースラム』は現地時間8月21日、ニューヨーク州ブルックリン、バークレーセンターで行われる。 日本人ではアントニオ猪木以来38年振りとなるWWE王座獲得へ。猪木は第9代王者と認定されながら、新日本所属だったこともあり、団体間の政治的な理由から取り消された経緯がある。WWEに移籍した中邑はキング・オブ・ストロングスタイルとして真の世界一へ王手をかけた。 ■中邑真輔の試合後コメント 「ついに実現した夢の対決、中邑真輔対ジョン・シナ。ジョン・シナを越えた今、次の夢の対決は『サマースラム』WWEチャンピオンシップ、ジンダー・マハル対中邑真輔。 イヤァオ!」文・構成 / どら増田写真 / c 2017 WWE, Inc. All Rights Reserved
-
スポーツ 2017年07月31日 16時00分
プロレス解体新書 ROUND60 〈小橋vs蝶野“魂の名勝負”〉 満天下に示したプロレスの矜恃
2003年5月2日、新日本プロレスの東京ドーム大会は『アルティメットクラッシュ』と名付けられ、総合格闘技色を全面に打ち出して開催された。 そんな中で行われた純プロレスのビッグマッチ、小橋建太vs蝶野正洋は、ガチンコを超えるプロレスの魅力を存分に見せつける名勝負となった。 新日本プロレスの1・4東京ドーム大会において、初めて観客数の発表が5万人を切ったのは2005年のことだった。4万6000人の発表ながら客席には空きが目立ち、当時を知る関係者からは有料入場者の実数が8500人だったとの声もある。新日が“冬の時代”といわれ始めたのも、やはりこの頃だった。 そうした凋落は'01年の総合格闘技戦で、永田裕志がミルコ・クロコップに惨敗したことでもたらされたとする声も多いが、加えてもう一つ大きな低迷の要因があった。いわゆる“土下座外交”である。 90年代の半ば辺りから、従来の地方巡業よりもドーム級の大会場を重視する興行スタイルへとシフトした新日は、その勢いに陰りが見え始めた21世紀に入っても、なおそうした形態に依存していた。 アントニオ猪木が引退し、長州力や藤波辰爾も衰え、'00年には橋本真也が独立。'02年の春には同じ闘魂三銃士の武藤敬司が、全日本プロレスへと移籍した。看板となる選手が次々にいなくなる中で、それでもビッグマッチを開催するためには、どうしても外部に頼らなければならない。 「新日側の都合でビッグネームを招聘するとなれば、試合においては相手の要求を全面的に飲まされることになる。ただでさえスター不足の新日が、さらに外敵に花を持たせるという、負のスパイラルに完全にハマってしまいました」(プロレスライター) この時期の新日で主役を張ったのは、藤田和之や髙山善廣、鈴木みのるなどの外敵軍や、ブロック・レスナー、ボブ・サップといった外国人であり、永田や中西学、棚橋弘至らの生え抜きたちは、その引き立て役に回された。 「これでは新日ファンはまったく面白くない。唯一、スター候補として育てられたのは中邑真輔でしたが、これも総帥たる猪木の意向ひとつでK-1やら総合格闘技やらと使い回され、肝心のプロレスに専念できないという状況。これでは誰を応援していいのかも分からない」(同) そんな中にあって三銃士で唯一、新日に残っていた蝶野正洋も、やはり苦しい立場に置かれていた。 '01年に猪木から現場監督に指名されると、外敵軍との抗争のためにそれまで率いたヒールユニットTEAM2000を解散し、正規軍に合流。'94年G1優勝後のヒールターンから、nWoを経て積み上げてきた歴史を封印することになる。元WWEの女子レスラー、ジョーニー・ローラーとの男女対戦というイロモノ的な試合もこなした。 さらに'02年、東京ドーム大会への三沢光晴参戦から始まった交流を発展させるため、翌年には自らノアへの参戦を果たした。 そうして迎えた'03年5月、東京ドームでの小橋建太戦は、いわば蝶野のプロレス人生を投げ打って実現したといっても過言ではない。ドーム興行成功のため、つまりは会社の儲けのために己を犠牲にして…。 ノアの“絶対王者”といわれた小橋なら、相手にとって不足のないビッグネームではあるが、それは同時に、この試合において“蝶野に勝ち目がない”ことを意味していた。この当時のノアは興行面で安定しており、他団体に頼る必要がなかった。そのトップである小橋が、わざわざ不利になるようなカードに応じるわけがないのである。 しかし、蝶野はそんな中にあって最高の試合を見せた。事前に膝を故障したというのも、負けたときの言い訳的な意味合いがあったかもしれないが、リング上ではそんな様子を感じさせない。 序盤はチョップ主体で攻め立てる小橋に対し、喧嘩キックやSTF、さらには大一番でしか披露しないルー・テーズ直伝の低空高速バックドロップを、危険な角度で繰り出した。 一方、小橋の反撃も容赦なく、ハーフネルソン・スープレックスを4連発。首に古傷を抱える蝶野にとって、文字通り命取りとなる大技だ。セコンドの天山広吉が思わずタオル投入の構えを見せるが、蝶野は必死の形相でこれを制する。 小橋はさらにハーフネルソン2連発から、ショートレンジの剛腕ラリアットを叩き込み、ついに激闘に幕が下ろされた。最初こそは小橋への声援が支配的だったが、蝶野の予想を超えた闘いぶりに、試合後は両者互角のコールが送られることになった。 この大会、他の試合はアルティメットクラッシュと題された格闘技戦で占められており、これが実は“なんちゃって格闘技”ではないガチンコだったのだが、蝶野と小橋はそれにまったく引けを取らない、プロレスの凄味を見せつけた。 しかし、そんな蝶野の孤軍奮闘がありながらも、猪木やフロントの専横は続けられ、新日が冬の時代へと向かう歯車が止まることはなかった…。
-
スポーツ 2017年07月21日 16時00分
プロレス解体新書 ROUND59 〈尻も出すが実力もある〉 “マードックvs藤波”匠同士の闘い
選手の大量離脱によって低迷した新日本プロレスで、確固たる外国人エースがいない中、苦しい興行を支えたのがディック・マードックだった。 タッグ戦でのアドリアン・アドニスやマスクド・スーパースターとの名コンビぶりや、藤波辰巳(現・辰爾)との試合における“尻出し”パフォーマンスなど、記憶に残る名場面をいくつも残してきた。 ディック・マードックについて、かつてテキサス・アウトローズとしてタッグを組んだ盟友のダスティ・ローデスは、「あいつはNWA王者になるべきだった」と評した。 確かにマードックは、プロレスラーとしてのタフネスと技量を高いレベルで備え、観客へのアピール力にも長けている。それはローデス以外にも多くのレスラー仲間や関係者の認めるところであり、長きにわたり“次期王者候補”と目されていた。 しかし、肝心のマードック本人は王者となることにこだわらない…というよりも、むしろ避けていた節まである。 王者となれば、それにふさわしい振る舞いが求められ、移動の際にはスーツ着用が必須。ほとんど休みなく、全米はおろか全世界を飛び回るハードスケジュールが待っている。 試合内容においても、各地のローカルヒーローに見せ場をつくり、観客を満足させながらも必ず王座を守って帰ってこなければならない。非常に神経を使わざるを得なくなる。 マードックはそんな堅苦しい毎日よりも、自由気ままな生き方を望んだ。王者としての名誉や高額のギャラよりも、好きなように暴れた試合の後で、人目をはばからずにかっくらう1杯のビールの方を選んだというわけだ。 そんなマードックの奔放さについて、ジャイアント馬場は能力の高さを認めつつも「ギャラの分しか仕事をしない」と、批判的なコメントを残している。 また、アントニオ猪木も不満に感じる部分があったようで、新日で外国人との折衝役を務めていたレフェリーのミスター高橋は、『猪木から“マードックを怒らせろ”と指示があった』とのエピソードを自著に記している。 「当時、ファンの間でも“酒場でのストリートファイトなら最強”などと噂されていたように、猪木としても怒って本気になったマードックの凄味を見てみたかったのでしょう」(プロレスライター) 結局、高橋は『藤波がお前のパンチはたいしたことないと言っていたぞ』とマードックを焚きつけ、試合で本気のパンチを顔面に叩き込まれた藤波は、哀れにも顔面アザだらけになったという。しかし、それも一時的な発奮に終わり、猪木の策略は失敗に終わったと言えようか。 マードックと藤波の対戦で、多くのファンがまず思い出すのが“尻出し”だろう。場外戦からリングに戻ろうとするとき、マードックのタイツを藤波が引っ張ると、タイツがまくれて真っ白い尻がさらされた。 最初は単なるアクシデントだったが、それが観客にウケたことで両者の間での定番ムーブとなり、のちには藤波の方が尻を出すこともあった。 「ほかにマードックの定番としては、木村健吾との闘いで“マードックがコーナーポスト最上段に上ったときに木村がロープを揺さぶり、股間をロープに打ちつける”というムーブもありましたが、やはり記憶に残っているのは尻出しパフォーマンス。マードックは藤波のプロレスの巧さや受けのスタイルを高く評価しており、まっとうな好勝負も多かった。そのため尻出しも強く記憶に残っているのでしょう。猪木はそんなマードックのふざけたようにも見える姿勢を改めさせ、猪木流のシビアな闘いに引っ張り込みたかったのでしょうが、結局、最後までマードックの自由人ぶりを変えることはできませんでした」(同) とはいえ新日ファンからのマードックへの信望は厚く、いくら尻を出しても、いくら鼻柱へのパンチが寸止めに見えたとしても、それで軽んじられるようなことはなかった。 「ブルーザー・ブロディのような巨漢パワーファイターが相手でも、前田日明のようなUWFスタイルが相手でも、マードックは自分流の試合を貫いた。さすがに尻出しなどのおふざけは少ないものの、自分なりのアメリカン・プロレスでキッチリと対応してみせた。ファンはそれが、実力に裏打ちされたものであることを敏感に感じ取ったのでしょう。これらの試合ではマードックへの大声援が起こったものでした」(同) 前田の試合スタイルに対して「喧嘩がしたいのか、プロレスがしたいのか」と詰め寄ったとの逸話もあるが、しかし、いったんリングに上がればそんな様子はおくびにも出さない。 「マードックは父親もプロレスラーで、若き日にはファンク道場でも修行したという筋金入り。フィニッシュ技がキラー・カール・コックス直伝の正統ブレーンバスターというところを見ても、内心ではプロレスラーとしての強いプライドを持っていたのではないでしょうか」(同) 陽気でいいかげんそうに見えて、いざとなれば誰も恐れることなく向かっていく。古きよき時代のアメリカン・プロレスを象徴するレスラーであった。
-
-
スポーツ 2017年07月17日 16時00分
プロレス解体新書 ROUND58 〈プロレスと格闘技の狭間〉 混迷を象徴する“藤田vs永田”
総合格闘技で華々しい結果を残して、新日本プロレスのマットに凱旋を果たした藤田和之。IWGPヘビー級王座にも君臨し、2001年6月6日の日本武道館大会では、永田裕志を挑戦者に迎えた 表向きにはプロレス大賞の年間最高試合賞(ベストバウト)を獲得したが、実際は新日“冬の時代”の幕開けとなる一戦であった。 2000年1月にPRIDEへの参戦を果たした藤田和之は、当時の格闘技界で“霊長類最強”の呼び名をほしいままにしていたマーク・ケアーに、大番狂わせの判定勝ち。 さらに、ケン・シャムロック(キング・オブ・パンクラシスト、UFCスーパーファイト王者)、ギルバート・アイブル(リングス無差別級王者)と、日本でなじみの深い強豪にも連勝し、一躍、総合格闘技界のトップランナーとなった。 古巣の新日本プロレスとしても、そんなニュースターを放っておくわけにはいかない。'00年の退団から1年4カ月ぶりに新日マットに登場した藤田は、スコット・ノートンを破ってIWGP王座を戴冠した。 「ここで業界やファンが足並みをそろえ、プロレス界の代表として藤田をバックアップしていたならば、もしかしたら後に、『プロレスラーは弱い』との誹りを受けることはなかったかもしれません」(プロレスライター) しかし、王者の藤田はすんなりと受け入れられなかった。 「例えば、AKB48グループのメンバーが多数出演したドラマ『豆腐プロレス』で、主役以上に好評を博したのが、本来は脇役だったはずの島田晴香(役名・ユンボ島田)でした。ドラマとはいえプロレスに対する島田の真剣さが、視聴者に伝わったんですね。しかし、藤田の場合はその真逆でした」(同) 抜群の身体能力に恵まれながらプロレスになじもうとせず、格闘技の世界に転身したという来歴への不満。プロレスよりも格闘技に目が向いているのではないかとの疑念。 ビッグマッチのみに出場する藤田に比べ、普段の巡業で団体を支え続ける選手たちへの同情。新日退団後に藤田が属した猪木事務所(アントニオ猪木)によるゴリ押しへの反発。 ファンの多くが藤田の背後に、リング上の闘い以外のさまざまを見ていた。 また、他のレスラーたちも藤田に対して複雑な思いを抱いていた。 「新日の先輩レスラーたちからすれば、もともとの藤田はプロレスに適応できなかった落ちこぼれです。いくら格闘技で結果を出したからといって、会社の方針一つでいきなり上に立たれたのでは、面白いわけがない」(スポーツ紙記者) 藤田が王者になるというだけならば、まだ甘んじて受け入れられても、それに挑戦して負けたとなれば、選手としての格付けにも関わる大問題だ。そのため藤田絡みのカードは、どうしても不自然なことになってしまう。 まず、新日に復帰した当初の藤田が挑戦を表明したのは、そのときのIWGP王者・佐々木健介だったが、藤田戦を前にあっさりノートンに王座を明け渡してしまった。 「コアなファンは“藤田に負けたくないから王座から降りた”と見透かしているのに、その試合後のマイクで健介が言い放った『藤田、正直すまんかった』の白々しさといったらもう…。それからしばらくの間、健介は何をやってもしょっぱい“塩介”と嘲られることになりました」(同) もしも藤田が三銃士らと直接対決して、これを倒していたならば…。トップどころの技量からすれば、不器用といわれる藤田をうまくリードして、王者として認められる存在にまで育てられたかもしれない。しかし、そうしたカードが組まれることはなかった。 ファンの不服は、藤田の試合内容にまで及んだ。王座を奪取したノートン戦では、勝利を告げられた藤田がなおもスリーパーホールドで締め続けていると、落ちて失神したはずのノートンが藤田の膝に手を当てて、「早く技を解いてくれ」とばかりに合図を送ったのだ。 その様子がテレビカメラにしっかりと映されたことで、一部ファンからは“ノートンもみもみ事件”と揶揄されることになった。 そうして迎えた初防衛戦。挑戦者として名乗りを上げたのは、永田裕志だった。 「永田ならば技術面でも対応できるし、同じレスリング出身の藤田を先輩として思いやる気持ちもあったでしょう。のちに格闘技戦に駆り出されたように、上からの頼みを断りきれない人のよさもあります」(同) そんな永田のリードと対応力もあって、この試合はプロレス大賞にも選ばれる好勝負となったのだが、その最後の最後で藤田がやらかしてしまう。 グラウンド状態の永田に対して、膝を連発で落としてのレフェリーストップ勝ちとなったのだが、その膝がまったく永田に当たっていないのだ。ただただマットに膝をぶつける様子が、またもやテレビにしっかりと映し出されていた。 「これが、例えばスタン・ハンセンなら、当たっていないラリアットでもファンは不満を口にしないが、残念ながら藤田には、まだそこまでの信用がありませんでした」(同) ファンからの共感を得られないまま“格闘技風プロレス”は続けられ、新日は長い冬の時代を迎えることになった。
-
スポーツ 2017年07月08日 15時00分
プロレス解体新書 ROUND57 〈第2回 IWGP暴動事件〉 猪木vsホーガンに長州が乱入
新日本プロレス史上初の本格的暴動を引き起こし、警察まで出動する騒ぎとなった第2回IWGP決勝戦(1984年6月14日/東京・蔵前国技館)。 長州力の謎の乱入によるアントニオ猪木の勝利は、いったい誰が描いた筋書きだったのか。 いよいよ平成から新たな元号に改まろうという中、それでもなお昭和プロレスについてさまざまに語られるのは、良くも悪くもアントニオ猪木の影響によるところが大きい。 「とにかく“普通”とか“当たり前”を嫌った人でした。例えば、藤波辰爾(当時は辰巳)と長州力の、いわゆる名勝負数え歌が盛り上がっていた頃、唐突に『いっつも同じような試合でつまんねえなぁ』と言い出す。それで札幌の“藤原喜明テロリスト事件”が起きたりするわけです」(新日関係者) しかも、猪木は思い付きを口にするだけで、実際のストーリー作りは他にお任せ。そのため周囲は猪木におうかがいを立てながら、あれやこれやと頭をひねることになる。 「花道で長州を襲うというのはどうでしょう?」 「いいんじゃないか」 「誰にやらせましょうか」 「誰でもいいよ」 「乱入の理由付けはどうしますか?」 「お前らで何か考えろ」 「当人たちには?」 「教えたら面白くならねえだろ」 だが、いつもの名勝負を期待しているファンからすれば、そもそも余計なことをする意味が分からない。 猪木の並外れて無責任な体質のせいで、伏線の回収をされないまま終わるアングルもしばしばで、その残された謎についての議論に花が咲くことになる。 「ただの思い付きもうまくハマれば、しっかり練った企画以上に緊張感あふれるものとなりますが、逆に周囲の人間が忖度しまくった結果、アルティメット・ロワイヤルのような選手もファンも、誰一人喜ばない、どうしようもないものになったりもする。だからといって猪木さんを無視すると、周りに知らせず、さらに勝手なことをやり始めるから始末に悪い」(同) その最たる例が第1回IWGP決勝戦における、自作自演の失神KO敗戦だ。 社運を賭けた一大イベントで、当然、最後に勝つのは猪木だと誰もが思っていた。ところが、猪木はそれが面白くない。 「おそらく“ここで一発アクシデントが起きれば、大騒ぎになるぞ”という発想なんでしょう。しかし、あの当時の新日ファンにしてみれば、IWGPがNWAを超える権威となり、その頂点に猪木が立つことを期待しているわけで…」(プロレス記者) “俺のやることに文句はなかろう”という根っからのスター気質ゆえなのか、ファンの託す思いをくみ取ろうとしないのは、猪木の弱点の一つと言えるかもしれない。 そんな猪木の“悪癖”は、翌年の第2回IWGP決勝戦でも表出する。前年の敗戦以降、アントンハイセル事業の失敗に社長解任クーデター、タイガーマスクの退団、UWF旗揚げに伴う選手の大量離脱と、ろくなことがなかった猪木が雪辱を期して迎えた大一番。 相手は前年覇者のハルク・ホーガン。むろんファンが望むのは、リング外のネガティブな話題を吹き飛ばし、なおかつホーガンへの雪辱を果たす猪木の快勝であった。 「ただ、このときすでにホーガンはWWF王者であり、その商品価値からして猪木がクリーンな勝利を収めることは、政治的な意味で難しい。それは薄々ファンも分かっており、決着さえつけば普通にリングアウト勝ちで構わないのだが、猪木という人はそれを良しとしなかった」(同) そこで、まず採用されたのは“延長戦”だった。新日の大一番としては'80年の異種格闘技戦、猪木vsウイリー・ウィリアムスでこれが実施され、翌年のスタン・ハンセンvsアンドレ・ザ・ジャイアント以降は、ファンからの“延長コール”も定着しつつあった。 延長1回だとありきたりだから2回にしようというところまでは、ファンもそれだけの熱闘と受け取るかもしれないが、しかし、そこから先のところで猪木のいいかげんさが顔を出す。 「長州を乱入させてヒール的な要素を付加しようというのは、おそらく猪木さんの発想です。あの頃の長州を自在に操れるのは、猪木さんぐらいですからね。だけど、最後に猪木さんを勝たせるにもかかわらず、猪木さんだけを攻撃するのは変だし、ホーガンだけに仕掛けたのでは猪木さんの反則負けと受け取られかねない」(前出・新日関係者) だったら両方に攻撃しようということで、まず猪木にリキ・ラリアットをかました長州は、返す刀でホーガンに向かい、アックス・ボンバーの相打ちに…。そうしてホーガンが倒れている間に、猪木がリングインして勝利となったものの、あまりの意味不明さに収まらないのはファンたちだ。 暴徒化したファンが蔵前国技館内の設備を破壊し、ついには警察官まで駆けつける騒ぎとなったが、新日初の暴動事件を生み出した張本人は、紛れもなく猪木自身であった。
-
-
スポーツ 2017年07月03日 15時00分

年商600億!“プロレス界のメジャーリーグ”WWE日本公演に欠かせぬクリス・ジェリコ
世界最大のプロレス団体、アメリカのWWEが6月30日、7月1日の2日間、毎年恒例となる日本公演『WWE Live Tokyo』を両国国技館で開催した。 スモーアリーナ(国技館)にはWWEユニバースと呼ばれるファンが多数詰めかけ、6月30日は6069人、7月1日は8318人を動員。試合前のグッズ売場にはスモーアリーナの1階を1周するほど長蛇の列が見られる盛況ぶりで、会場内は和風とアメリカンな空気が良い感じに混雑していた。ディズニーランドや、USJに来たような感覚と言ったらわかりやすいかもしれない。あの自由な空気感は日本の団体には作り出せないだろう。キャラや英語、ストーリーが全く分からなくても、その場の空気感で理解できてしまうのがWWEの魅力であり、魔力である。ファンの「HAPPY!な気分になりに来ました」感がスゴイ。とにかく楽しんだモン勝ちみたいなムードが充満しているのだ。 「WWE(当時はWWF)も観たことないのにプロレスを語れるのか?」 昔、プロレスマスコミの先輩にこんな嫌味を言われたことがある。まだWWEがこのようなツアーを日本で開催していない時代。WWEを観るにはそれこそニューヨークに行くしかなかった。それが今ではハウスショーながら、年に一度は渋谷から30分の距離でニューヨークが体感できる。本当に良い時代になった。 報道陣に渡された資料には、「スポーツエンターテイメント」を「ビジネス」として成立しているのがWWEだと記載されているが、上場企業であるWWEの年商は600億円を超えると言われており、プロレス界では断トツで世界一の団体。2位は日本の新日本プロレスだが、新日本の年商は約37億円とその差は歴然としている。 WWEと新日本をはじめとする日本マット界の関係は、野球に例えるならMLB(メジャーリーグ)と、NPB(プロ野球)の関係に似ているが、決定的に違う点がひとつだけある。それはWWEに日本の団体に所属する選手が移籍しても日本の団体には移籍料が一銭も発生しないということだ。MLBとNPBは協定を結んでいるので、海外FA(フリーエージェント)権を行使しない限りは“希望球団に”移籍できないようなシステムになっている。しかし、日本のプロレス団体は単年契約が基本となっており、選手が契約を更新しなければWWEに移籍することが可能なのだ。 WWEは『RAW』と『SMACK DOWN』という2大ブランドを軸に、『NXT』というMLBではマイナーリーグにあたる育成ブランドと、軽量級の選手に特化した新ブランド『205 Live』の4つのブランドをテレビ番組として制作。莫大な放映権料を収入源にしている。WWEのTVショーは2014年に開局した有料ストリーミングサイト『WWE NETWORK』により、全世界でライブ視聴が可能となった。日本では今年の4月から『DAZN』での配信をスタートさせた。 『WWE NETWORK』の開設は、新時代に向けた投資であるとともに、世界制覇に動き出した証でもある。これまでも日本人選手や日本で活躍していた選手がWWEに移籍することはあったが、2014年7月にプロレスリング・ノアの主力選手だったKENTA(ヒデオ・イタミ)がWWEの大阪公演のリング上で、“超人”ハルク・ホーガンが立ち会いのもと契約書にサイン。2015年には新日本で育ち、IWGPジュニアヘビー級王者として新日ジュニアを牽引。2014年からは外国人ヒールユニット、バレットクラブのリーダーとして活躍していたプリンス・デヴィット(フィン・ベイラー)、そして昨年は新日本のトップ選手だった中邑真輔、AJスタイルズ、カール・アンダーソン、ドグ・ギャローズ(ルーク・ギャローズ)、ドラゴンゲートの主力選手だった戸澤陽がWWEに引き抜かれるような形で移籍している。WWEの日本侵攻は男子選手だけに留まらない。2015年に日本ではフリーだったが、各団体のエースを相手に活躍していた華名(ASUKA)が移籍すると、NXTでデビュー以来、連勝街道を突っ走りNXT女子王者に。デビュー以来174連勝というこれまでビル・ゴールドバーグが保持していた団体記録を更新する快挙を達成した。このニュースは世界中で報じられ、現在も連勝記録を更新中だ。そして、先日スターダムを退団したばかりの宝城カイリが、今回の日本公演開演前に会場のスクリーンに登場し、本人の口からWWEと契約し、カイリ・レインというリングネームでNXTでデビューすることが発表された。 これまでは、英語圏とスペイン語圏に比べると明らかに劣る日本のマーケットはあまり重視されていなかった。しかし、WWEは次世代の主要コンテンツである『WWE NETWORK』の加入者を増やすためには、プロレスを見る文化が根付いている日本を外すことはできない。またバレットクラブのブレイクにより、バレットクラブTシャツを着たファンがWWEのTVショーに映し出されることもあることから、アメリカ進出を果たした新日本の存在も刺激したのは言うまでもない。 日本公演ではこのような経緯でWWEに移籍した選手による凱旋マッチが毎年ラインナップされているが、初日のオープニングマッチに出場したヒデオ・イタミがブーイングが浴びせられる場面があった。これは対戦相手のクリス・ジェリコが、日本マットで名と実績を上げてWWEのトップにまで登り詰め、現体制になってから初となる日本公演(2002年3月1日 横浜アリーナ)ではメインイベントでザ・ロック(のちにハリウッド俳優としても活躍しているドウェイン・ジョンソン)を破ったスーパーレジェンドということも影響している。ジェリコは、WAR(かつて天龍源一郎が代表を務めていた団体)でライオン・ハートのリングネームで定期参戦していたとき、現在は新日本のCHAOSで活動している邪道、外道、そして故・冬木弘道さんとともに冬木軍のライオン道として行動をともにしていたことがある。WARが国技館を定期的に利用していたので、初来日のWWEスーパースターたちに“テッポウ”の意味を教えたり、日本公演に自分の名前がないと「行かなくていいの?」と自ら志願するほどの親日家。ヒデオとの試合では日本の“第1試合”のようなオーソドックスなジャパニーズスタイルを見せてくれた。ヒデオにとってはほろ苦い凱旋マッチになってしまったが、2日目にジェリコと対戦したフィン・ベイラーは勝利を収めた後、ジェリコに最大限の敬意を払っていたように、ジェリコはヒデオやベイラーと同じ日本のジュニアヘビーからアメリカンドリームならぬ、ワールドドリームを掴み取った選手である。 今回はRAWの選手を中心に構成された来日メンバーだが、ジェリコはSMACK DOWN所属。次回の日本公演は9.16エディオンアリーナ大阪公演が決定。中邑真輔、AJスタイルズらSMACK DOWNのメンバーが中心と発表されている。渋谷から30分のニューヨークに続いて、ミナミから5分のニューヨークである。そこにはきっとまたジェリコの姿が当たり前のようにあるはずだ。取材・文/どら増田※写真・(C)広瀬ゼンイチ
-
スポーツ 2017年07月02日 14時00分
プロレス解体新書 ROUND56 〈伝説のスーパーJカップ〉 ハヤブサを飛翔させたライガー
「ジュニアの世界であればメジャーとインディーによる団体間の交流も可能」という獣神サンダー・ライガーの提唱により、1994年に開催された第1回スーパーJカップ。決勝戦のワイルド・ペガサスvsザ・グレート・サスケ以上に強烈なインパクトを残したのは、1回戦でのライガーとハヤブサの一戦だった。 新日本プロレス恒例のジュニアヘビー級最強決定戦『ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア』を、今年限りで卒業すると宣言した獣神サンダー・ライガー。その結果は1勝6敗の予選リーグ敗退に終わった。 マスクマンとしての初登場から28年、素顔の時代も含めれば現役生活30年以上になる“生きる伝説”が、一つの時代を終えようとしている。アニメのタイアップとして登場したライガーだが、永井豪による原作の内容まで記憶する人は、どれほどいるだろうか。 肉体型パワードスーツをまとった主人公という元来の設定よりも、プロレスラーの姿の方が世間に浸透しているのが実際のところだろう。印象的な「♪燃やせ燃やせ〜」のフレーズで始まるアニメの主題歌『怒りの獣神』も、今ではすっかりライガーの登場テーマ曲として定着している。 「ジュニアならではの華麗な空中殺法はもちろん、打撃や寝技、ラフ&パワーファイトと、すべてをハイレベルでこなすオールラウンダー。それだから、誰が相手でも好勝負ができる。唯一とも言えるビッグマッチでの凡戦は、2002年にパンクラスで行われた鈴木みのるとの総合格闘技戦ぐらい。2分弱でチョークスリーパーに敗れましたが、ただこれは、新日を離脱してWJに移籍した佐々木健介の代役出場で、事前の準備が十分にできなかったのだからやむを得ない」(プロレス記者) 主役としても脇役としても輝くことができるライガーは、日本プロレス史を見ても希少な存在だ。 「人気もポテンシャルも最上級なのに、ライガー本人は決して主役の座にこだわらず、対戦相手にも華を持たせる。そんな姿勢はプロレス界全体の底上げにもつながりました」(同) また、その影響は日本のみにとどまらない。 「クリス・ベノア(ワイルド・ペガサス)やエディ・ゲレロ(2代目ブラック・タイガー)、クリス・ジェリコ(ライオン道)ら、WWEスーパースターたちも、ライガーをはじめとする日本での闘いを糧にして、自らのファイトスタイルを築きました」(同) FMWのハヤブサもまた、ライガーの存在を抜きにして語れない1人だ。1994年4月16日、両国国技館で開催されたスーパーJカップ。ライガーの提唱によるワンナイトトーナメントには、団体の垣根を越えて国内4団体、海外2団体から全14選手が集まった。 その1回戦でライガーと対戦したハヤブサは、このときまったく無名の若手に過ぎなかった。メキシコからの武者修行帰りとは言いながら、現地での試合は手違いのためほとんど組まれていなかったという。 そのためハヤブサ本人は、参戦オファーを受けた際に「そのメンバーとやれる自信がない」と、断りを入れたことを後日告白している。それでも団体の後押しもあり、出場を決めた。 ハヤブサは目の周りが広く開いた変形マスクで、素顔の部分に歌舞伎風の隈取りを施した新奇なルックス。さらに、これもまた珍しい着流し風ガウンで、さっそうとリングに登場した。 大観衆の興味と期待が、そのたたずまいに注がれたところでゴングが鳴ると、同時にハヤブサはドロップキック一閃、場外に転落したライガーに向かって、ガウンの裾を翻しながらトペ・コン・ヒーロを放った。 「獲物を狙うかのような鋭い眼光で相手を見据え、リングのライトを浴びてキラキラ光を放ちながら宙を舞った姿は、プロレス史上屈指の美しさでした」(スポーツ紙記者) そのインパクト抜群の一撃でファンのハートをつかんだハヤブサだったが、しかし、試合に入るとどうしても経験不足から拙さが出てしまう。早い段階でスタミナを切らし、立っているのがやっとの状態で、技を仕掛けるにも距離感はバラバラ。 「今になって映像を見るとそうした粗も目立つのですが、実際の会場ではそれを感じなかった」(同) もちろん、それはライガーのリードのたまものだ。猛攻を続けて観客にハヤブサのスタミナ切れを察知させず、力感を欠いた技にも丁寧に対応していく。 ライガーのオリジナル技であるシューティング・スター・プレスをハヤブサが放ったときですら、やはりきちんと受けに回った。 「いくらハヤブサがゲストとはいえ、新人が下手な真似をしたらキレてもおかしくない。それを不問にしたのは、主催者として大会の成功を第一に考えていただけでなく、ハヤブサの将来性を見込んでのことだったのでしょう」(同) 敗れてもなおハヤブサの出世試合として語られる名勝負だが、その実態はライガーが懐の深さを示した一戦でもあったのだ。
-
スポーツ 2017年06月25日 15時00分
プロレス解体新書 ROUND55 〈大巨人が初のギブアップ〉 快挙の裏に隠された猪木の思惑
さすがのアントニオ猪木も1986年頃になると、ファンから“前田日明との対戦から逃げている”などの声が上がり、その衰えを指摘され始めた。そんな中で成し遂げたアンドレ・ザ・ジャイアントからのギブアップ勝利は、世界初にして唯一の快挙となった。 「故郷の田舎町に新日本プロレスの巡業が来た翌日、通っていた中学校での話題はアンドレ・ザ・ジャイアント一色でした。皆が口々に『パンフレットには身長223センチとなってるけど3メートルはあった』『近くで見たら校舎の2階ぐらいの高さだった』と、生で見る大巨人はそれほどインパクト絶大でした。このときはMSGシリーズで、ほかにも豪華外国人がそろっていたはずなんですけどね」(プロレスライター) テレビ放送では日本人選手をクローズアップしなければならず、その存在感を伝え切れない部分もあっただろう。しかし、生身のアンドレはやはり格別の存在であり、'74年のギネスブックに“年俸世界一のプロレスラー”と記載されたのはダテではない。 なお、このときの年俸は40万ドル(当時は1ドル=300円換算で約1億2000万円)とされ、同時期、メジャーリーガーの平均年俸が4万ドル程度だから、その10倍も稼いでいたことになる。 世界中のどこに行ってもアンドレ見たさに人が集まるのだから、ファイトマネーの高騰も当然のこと。基本的にベビーフェース(善玉)側のゲストとして各地をサーキットしており、新日参戦時のヒール(悪玉)役はむしろ例外だった。 しかし、「ベビー、ヒールに関係なく、ただただ大巨人の勇姿を見たい」というのが、ファンの本音であったろう。 そんなアンドレとの対戦にあたって、格闘技的意味での勝負を求めたのが、誰あろうアントニオ猪木だった。 今にしてみればこれを無粋と感じるファンもいるだろうが、当時“キング・オブ・スポーツ”を掲げてストロングスタイルを標榜した新日においては、いくら世界的人気者のアンドレが相手でもそこは譲れない一線であった。 「これはファンに対して、エンターテインメントではない“勝負”を見せたかったということであって、単なる勝敗とは別の話。星取りでいえば両者はまったくの五分で、最初の対戦では猪木がフォール負け(マネージャーが場外から足を引っ張ったところにジャイアント・プレス)を喫しています」(プロレス記者) そんな中で、猪木が勝ちにこだわった試合もあった。一つは'76年に行われた格闘技世界一決定戦である。 「その3カ月前、モハメド・アリとの闘いを世間から凡戦と酷評されたことで、猪木としては負けられない一戦となりました。この試合で猪木は、アンドレを一本背負いやリバース・スープレックスで投げ飛ばした上に、大流血に追い込んでTKO勝ちしています」 “格闘技世界一を名乗るなら俺を倒してみろ”というアンドレの挑発に応えて、プロレス界のナンバーワンを決めるという意味付けの試合でもあった。 そしてもう一つが'86年6月17日、愛知県立体育館で行われたIWGPチャンピオンシリーズの公式戦だ。 「この大会の直前、猪木は写真誌に不倫現場を撮られて懺悔の丸坊主にしていました。そのため、このアンドレ戦における勝利を“スキャンダルの汚名返上のため”と見る向きもあるようですが、事実は少し異なります」(新日関係者) 新日は前年10月にWWF(現WWE)との業務提携解消を発表しており、WWF主要キャストであるアンドレの新日参戦も、これがラストとされていた。 「そのため猪木としては、最後のアンドレ戦で完全勝利を果たしたかったわけです」(同) とはいえ相手は、'73年に前名のモンスター・ロシモフからアンドレにリングネームを変更し、それから10年以上にわたって一度たりともフォール、ギブアップでの負けを喫していない世界的スーパースター。 勝敗はプライドの問題であり、ファイトマネーを積めば何とかなるという話ではない。 「そもそもアンドレ側がクリーンな負けに納得するだけの金額は、低迷期にあった当時の新日には用意できなかったでしょう」(同) それでも交渉の結果、アンドレの合意を得て猪木は腕固めでギブアップ勝ちを収める。その後、WWFでヒールに転じてからは、ハルク・ホーガンやアルティメット・ウォリアーにフォール負けを喫したものの、ギブアップを奪ったのは猪木が世界初にして唯一となった。 では、なぜアンドレは猪木の要求を飲んだのだろうか。 「アンドレは猪木がアリと闘った同日、異種格闘技戦でボクサーのチャック・ウェップナーと対戦(ヘッドバットから場外に投げ落としてリングアウト勝ち)しています。それで、同じくボクサー相手に闘った猪木に、何かしら尊敬の念のようなものがあったのでは? もうアンドレは亡くなっているので、あくまでも想像に過ぎませんが…」(同)
-
スポーツ 2017年06月25日 12時00分
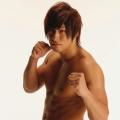
飯伏幸太電撃参戦!新日本プロレス今年の『G1』は、日本全国 闘いサマー!!
「自分の感情がコントロールできるのか 大爆発してしまうんじゃないか」 新日本プロレス6.20後楽園ホール大会で、『G1 CLIMAX 27』エントリー選手が場内のスクリーンで次々と発表される中、最後の選手が発表される前に、その選手の背中とともにこんなメッセージが流された。その選手とは、“ゴールデン★スター”飯伏幸太である。 飯伏は2013年10月に日本プロレス界初の2団体所属(もう1団体はDDTプロレス)として、新日本に入団したが、頸椎椎間板ヘルニアの影響で、2015年11月より長期欠場。昨年2月に両団体を退団後、復帰を果たし飯伏プロレス研究所の所属として国内外の団体に参戦。新日本マットには約1年8か月ぶりの復帰となる。 飯伏は過去にジュニアヘビー級時代の2013年と、ヘビー級に転向を果たした2015年の2度『G1』に出場しているが、いずれも4勝5敗と決勝進出はおろかリーグ戦で勝ち越せてもいない。注目のブロック分けは6.26後楽園大会で、各大会の公式戦は翌6.27後楽園大会で発表されるが、飯伏の参戦が発表されるとブロック分けやカード発表を待たずして、各大会の前売り券の売り上げが伸びており、完売の席種も目立ってきた。優勝決定戦が行われる8.13両国国技館大会をはじめ、チケットが残りわずかという大会も少なくない。飯伏の『G1』参戦、新日本マット復帰のインパクトは、悲鳴にも似た大歓声があがった後楽園ホールだけではなく、新日本プロレスワールドなどで生中継を見ていたファンもSNSで一斉に発信したため、プロレスファンのSNSのタイムラインがしばらくの間、飯伏一色となるといったパニック状態だった。 「悪くなってしまったので、闘いたいですね」 今年の3月12日に放送された『現役・OBレスラー200人&ファン1万人がガチで投票!プロレス総選挙』(テレビ朝日系)の中で、15位にランクインしたかつての盟友ケニー・オメガを前に、ゲスト出演した飯伏はこんなコメントを残している。オンエア後、このコメントに対してケニーが反応したことで、ファンも「いつかはまた2人の試合が見たい」という声が高まっていた。また、飯伏の口からは節々に同級生である内藤哲也を意識する発言も飛び出しており、飯伏退団後にヒールとして大ブレイクを果たした両選手との対戦が、今年の『G1』で実現するのか、非常に注目される。 他にも激闘を繰り広げたオカダ・カズチカや、飯伏が神と仰ぐ棚橋弘至、そして3年ぶりに出場する鈴木みのるには勝ったことがない。また飯伏退団以降に新日本マットに登場したSANADAや、凱旋帰国したEVIL、ザック・セイバーJr.との対戦も実現すれば新鮮だ。 今年の『G1』のキャッチコピーは“日本全国 闘いサマー!!”とつけられた。猛暑が予想されている今年の夏。“鬼軍曹”故・山本小鉄さんの言葉を借りるなら、リング上が40℃を超えるのは間違いない。 ゴールデン★スターが電撃復帰を果たす今年の『G1』は、9月から来年1.4東京ドーム大会までの新日本マットを占う上で、大きな意味を持つ大会になる。新日本マットの中心に飯伏は再び割り込んでくるのか?全試合を見逃すな!■『G1 CLIMAX 27』出場メンバー棚橋弘至【16年連続16回目の出場(※2007年&2015年優勝)】真壁刀義【14年連続14回目の出場(※2009年優勝)】マイケル・エルガン【3年連続3回目の出場】オカダ・カズチカ【6年連続6回目の出場(※2012年&2014年優勝)】後藤洋央紀【10年連続10回目の出場(※2008年優勝)】石井智宏【5年連続5回目の出場】矢野通【11年連続12回目の出場】YOSHI-HASHI【2年連続2回目の出場】ケニー・オメガ【2年連続2回目の出場(※2016年優勝)】バッドラック・ファレ【4年連続4回目の出場】タマ・トンガ【2年連続2回目の出場】内藤哲也【8年連続8回目の出場(※2013年優勝)】SANADA【2年連続2回目の出場】EVIL【2年連続2回目の出場】小島聡【2年ぶり15回目の出場(※2010年優勝)】永田裕志【19年連続19回目の出場(※2001年優勝)】ジュース・ロビンソン【初出場】鈴木みのる【3年ぶり7回目の出場】ザック・セイバーJr.【初出場】飯伏幸太【2年ぶり3回目の出場】 全20選手が、AブロックとBブロックに10選手ずつ分かれて、7.17北海きたえーる大会から8.12両国大会までの18大会で総当りリーグ戦を開催。両ブロックの1位選手が、8.13両国大会で優勝決定戦を行う。(どら増田)【新日Times vol.71】※写真:飯伏幸太選手 (C)新日本プロレス
-
-
スポーツ 2017年06月18日 12時00分

棚橋が渾身のテキサスクローバーで内藤を撃破しIC王座奪取! 今度こそ棚橋色に染め上げるか?
新日本プロレス『DOMINION』大阪城ホール大会が11日に開催され、11,756人(札止め)の大観衆を動員し、会場は終始熱気に包まれていた。 セミファイナルでは内藤哲也が持つIWGPインターコンチネンタル王座に、エース復権を掲げる棚橋弘至が1.4東京ドーム大会に続いて再挑戦。右腕の負傷により前シリーズを全休した棚橋や、7月のロサンゼルス大会から新設されるIWGP USヘビー級王座に対して怒りの内藤は、ベルトを破壊するなどの暴挙にでていただけじゃなく、勝てばインターコンチ王座の封印もしくは返上を宣言。一方の棚橋は破壊されたベルトについて「ビンテージ感がある」とファッション的な観点から評価。「内藤の土俵でケリをつける」と強い口調で言い切った。 試合は、1.4ドームを超えるハイレベルな攻防の末、終盤スリングブレイド2連発で勝機を掴んだ棚橋は一気にコーナーに登り、終生のライバル中邑真輔が乗り移ったかのように“滾る”と大阪城ホールからは大きなどよめきが…。そして必殺のハイフライフローを決めるも、内藤はギリギリでキックアウト。すると、普段であればもう1発ハイフライフローを決めにかかるところだが、テキサスクローバーホールドで内藤を締め上げた。1度はロープ際まで逃げようとした内藤だが、棚橋は再びリング中央まで引き戻し、渾身のテキサスクローバーホールドを高角度でガッチリ決めると、内藤も堪らずギブアップ。 内藤は調印式で、「棚橋選手には、結果で俺を黙らせてほしいなと思います。そして、かつてのライバルであり、IWGPインターコンチネンタル王座のかつての主である中邑真輔の気持ちも背負って、棚橋選手には大阪城ホール大会のリングに立ってほしいなと思います」と話していたが、棚橋からすればお望み通りの形で葬ったことになる。 棚橋がタイトル戦においてテキサスクローバーホールドをフィニッシュに選んだのは、2007年11月に、海外遠征から凱旋帰国し、波に乗っていた後藤洋央紀が初挑戦したIWGPヘビー級選手権が思い出される。あの時の後藤も棚橋を執拗に挑発しており、相手を黙らせるためには「ギブアップさせるしかない」という考えがあるのかもしれない。現に試合後の内藤は、今後インターコンチ王座に関わらないだろうというコメントを残しただけで、試合についての言いわけや、棚橋に対する憎まれ口を叩くことなく、会場を後にしている。内藤を黙らせるほどの説得力が、この日のテキサスクローバーホールドにはあった。 「まだ死んでなかったでしょ。棚橋は生きてるから、“Tanahashi still alive”。休場明けの横綱が強いように、故障明けのホームランバッターがいつでもホームランを打つように、少し休んでもエースはエースだから。そんなに年数経ってないのに、この貫禄。これにダメージデニムも合わせて、カッコよく着こなすから。ベルトは、腰に巻かれることによって、本来の意味をなす。今日、久しぶりにこのベルトは、“腰に巻かれる”という役目を与えられて、初めてこの世に存在します」 久々にシングル王座のベルトを腰に巻いた棚橋は、このように感情を一気にまくし立てると、少し落ち着いたのか、本音を語りはじめた。 「ホント言うとね、怪我のタイミングが最悪で、『なんでこのタイミングで、怪我なんだろ』って思ったけど、その試練を越えた。これから、どんなことがあっても、立ち向かっていけます」 と不安があったことを吐露すると、続けて中邑を意識した滾るパフォーマンスをだしたことについても語った。 「もうとっくに消化してるって言ったし、内藤に言われて、どうこう思ったところもないし。ただ、インターコンチを巻くにあたって、去年の長岡(ケニーとの王座決定戦)からずっとモヤモヤしてたものがあったから。かつて、あれほど鬱陶しいほど絡んでいったのに、急に何もなしですかっていうのは、あまりに素っ気ないし。ちょっとだけです」 昨年2月に中邑真輔の気持ちを引き継いだ形で、ケニー・オメガとの王座決定戦に臨むも敗れ、大阪城で訪れた挑戦のチャンスも怪我で失い、そして、今年の1.4ドームではマイケル・エルガンから同王座を奪取した内藤に挑戦するも、惨敗。世代交代まで言い渡されてしまった。インターコンチの神様から見放されているようにも見えるが、棚橋の頭の中には2014年1月に中邑を破り、3か月間保持していたインターコンチ王座に対して、“棚橋色”に染め上げられなかったという悔いがずっと残っている。 「前は何もしてあげられなかったから、今度あのベルトを獲ったら“棚橋色”に染めあげますよ!」 これは王座決定戦が決定した直後に棚橋がだしたコメントである。昨年の1.4ドーム大会でオカダ・カズチカのIWGPヘビー級王座に挑戦し敗れて以来、インターコンチ王座に固執し続けたのは、中邑との思い以上にこんな理由があったのだ。実に2年4か月ぶりのシングル王座戴冠となった棚橋が、ビンテージ感を増した白いベルトを今度こそエースのベルトにできるのか? その初陣は来月2日のロサンゼルス大会。元WWEスーパースターのレジェンド、ビリー・ガンを挑戦者に迎えて幕を開ける。(どら増田) 【新日Times vol.70】※写真・(C)新日本プロレス
-

スポーツ
新日本プチシルマ争奪戦勃発
2007年03月07日 15時00分
-

スポーツ
棚橋時代到来
2007年02月19日 15時00分
-

スポーツ
アングル 永田 新日制圧へ IWGPヘビー級タッグ王者中西、大森組への挑戦急浮上
2007年02月19日 15時00分
-

スポーツ
猪木 緊急提言 想定外プロレスをやれ!
2006年12月05日 15時00分
-

スポーツ
1・4東京D「レッスルキングダム」 新日本 全日本“乗っ取り”へ秘策 長州3冠戦出撃
2006年11月16日 15時00分
-

スポーツ
復活1・4東京D大会へ秘策 新日本最終兵器サイモン猪木 IWGP挑戦!?
2006年11月07日 15時00分
特集
-

あかつ、アメリカ・アポロシアターでの「動きで笑わせるネタ」は世界にも テレビに年数回でも出られる自分は「持ってる」
芸能
2025年10月03日 12時00分
-

TKO・木下、篠宮との一件を明かす 目標は「タイと日本のハブ」 挑戦に対する厳しい声には「どうでもいい」
芸能
2025年09月26日 18時00分
-
-

元ボーイフレンド・宮川英二、最大の挫折は「M-1グランプリ」 セカンドキャリアは、芸人やお笑いサークルの学生の就職支援 芸人の給料も赤裸々に語る
芸能
2025年09月18日 17時00分
-

岡平健治「19」解散は「お金の問題じゃない」 岩瀬敬吾、地元に戻るのを「止められてよかった」 今後はバラエティーで「ポンコツっぷりを見て笑ってほしい」
芸能
2025年08月05日 23時00分
-

misono、家族について「マジで気持ち悪い家族」 「⼦ども⾃然にできると思っていたけど……」と不妊治療の再開、明かす
芸能
2025年09月16日 11時00分
