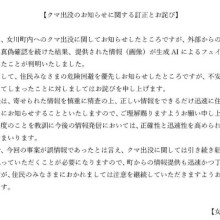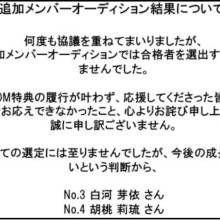明治43(1910)年4月15日、1年間のお礼奉公が終わった。以後、仕事はすべて能率に応じた出来高払いになる。坂田の店から仕事を受け取り、仕上げて納める“下請け”だ。もっとも、相変わらず芳松夫妻と一緒に親子のように暮らしていた。
器用で仕事が手早い上、仕上がりがきれいだった。ほかの職人仲間が月12円くらい稼ぐところ、徳次は月15円を下らなかった。その中から食費として5円をおかみさんに納めていた。
自前でそろえることになっている仕事道具や材料のほかに、自分の工夫や考案に使う大小のプレスの購入に稼ぎの残りを充てた。機械の導入は徳次が丁稚のころから思っていたことだった。芳松は、仕事は腕で勝負するという昔かたぎの職人だったから、新時代の機械には目もくれなかった。しかし徳次は“これからは、いい機械を他人よりも先に使わないと成功しない”と考えていた。
そこで少しでも金がたまると次々に機械を買い入れた。周囲はまだ腕を競い合う明治の終わりごろのことで、機械に目をつけている職人などほとんどいなかった。職人仲間が陰で自分のことを「機械狂い」と言っていることも徳次は知っていたが、陰口をいちいち気にしていたのでは何もできない、と考えていた。そして、この機械導入という先行投資が後の徳次の事業に大きく寄与するのだ。
ほかの職人より1カ月の納品収入は多かった。しかし主な仕事だった洋傘の付属品作製は主として10月から4月までの冬場の仕事だったので、平均すると収入はそれほど多くはなかった。その上、義母は相変わらずやって来る。
月に2度、3度と無心に来ることもあり、黙って聞いてばかりはいられなかった。すると人相のよくない男を差し向けて、店の前の通りから徳次に向って怒鳴ったり嫌がらせを言わせたりすることさえあった。