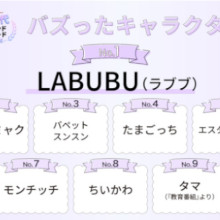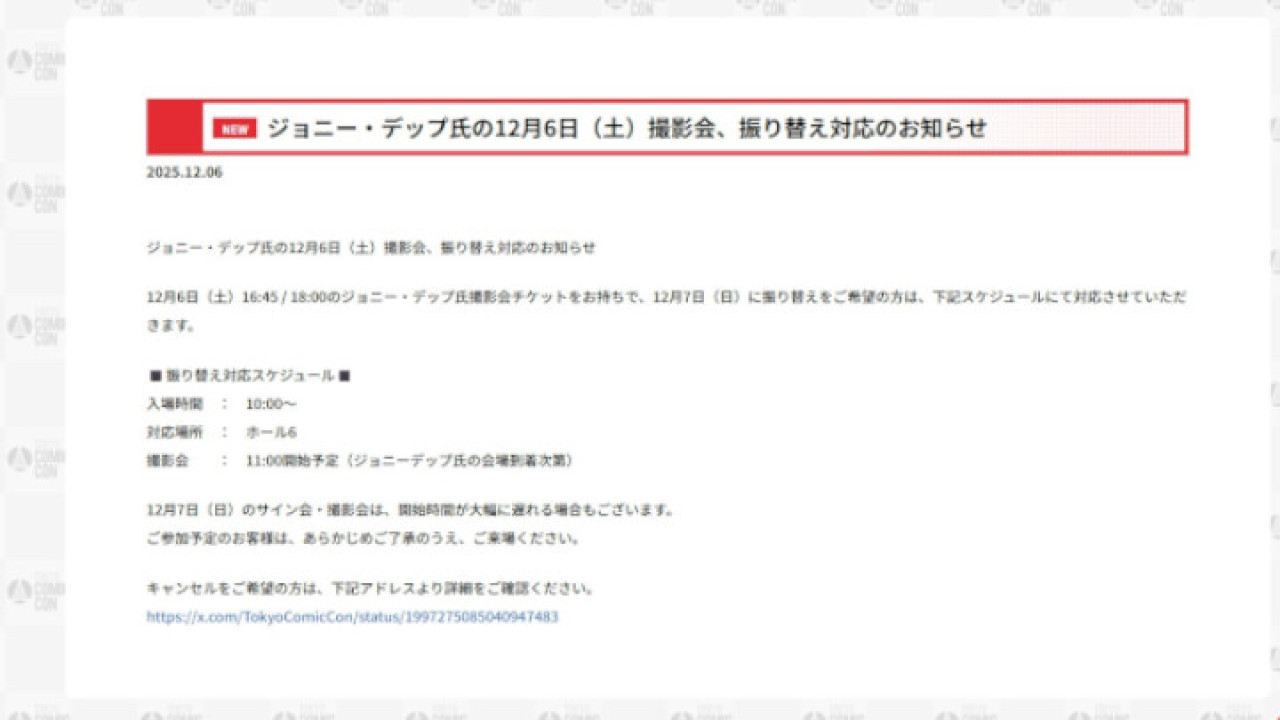1人あたりの平均年間労働時間は、日本1617時間に対してドイツは1331時間。ドイツの労働生産性は日本の1.5倍以上と言われており、労働者が1時間あたりに生み出す付加価値が高い。これが短時間でも高い賃金を支払える基盤となっている。第一生命経済研究所の熊野英生氏は「働き方のメリハリが違っていて、為替要因だけではなく、効率でも日本の働き方が劣っているのではないか」と語る。
あるドイツ人ユーチューバーは「ドイツ人は2~3週間の休みを取る。長く休みたいから効率よく仕事しましょうみたいな考え方がある」と語った。日本で長く活動しているドイツ人翻訳家、マライ・メントライン氏は「日本の会議は長い。完璧な形で企画書を出そうとするとか仕事のやり方が丁寧すぎるところもある」と話す。
レギュラーコメンテーターの玉川徹氏は「為替のせいにしてはダメ。円が安いというのは日本の国力が落ちているということ。為替調整するために金利を上げたら日本は大不況になる」と分析する。
アメリカは少子高齢化には無縁といわれ、中国は高齢化が進んでいるものの10億人以上の人口がいるのでGDPが大きくて当然だ。日本とドイツは少子高齢化という抱えている社会問題が同じだが、これだけ差がつくのは社会のシステムにも大きな違いがある。
日本は新卒一括採用で年功序列だが、ドイツはジョブ型雇用。この違いは決定的だ。ジョブ型雇用とは、職務内容(ジョブ)を明確に定義し、その職務に求められるスキルや専門性を持つ人材を、特定の役割と責任に基づいて採用・評価する雇用形態だ。日本の雇用制度では生産性向上のインセンティブが働きにくい。
番組コメンテーターの結城東輝弁護士は日本の社会システムが変わるにはまだ20~30年かかると指摘する。
「日本も今の20代はジョブ型雇用に変わっている。その人たちが管理職に就いて会社の仕組みを変えるにはまだまだ時間がかかる。相当大きな文化的変換をしなければならない」
熊野氏はこれに応じ、次のように付け加えた。
「ドイツで『シュレーダー改革』が行われたのが20年前。その構造改革により労働者は成果に応じて稼げるようになった。だから日本が今から改革を始めても成果が出るのは2050年くらい」
会社の利益などのうち人件費に回る割合を「労働分配率」と呼ぶが、日本の労働分配率は90年代からずっと下がり続けて今は57.2%だ。ドイツは2000年代後半から持ち直し、今は58.3%になった。そして、日本企業の内部留保は今も右肩上がりで増えており、日本企業が労働者にしっかり利益還元しようとしない姿勢が鮮明になっている。