この戦国現代ドラマでは才人・石田三成(萩原聖人)も江の前では形無しである。三成は人を見る目の確かさを称賛するために、自分の出世話を披露する。茶を所望した秀吉に対し、飲みやすいように最初は温めの茶を出したというエピソードである。これは三成の才覚を示す話であるが、本人の口から語らせると効果半減である。江に「全部そなたの自慢話ではないか」と一喝される。
このように有名な歴史的エピソードを登場させつつも、定説とは異なる文脈で利用する点が『江』の特色である。過去にも市が小豆を織田信長に送るエピソードや、信長が敵将の頭蓋骨を盃にするエピソードで新鮮な解釈が提示された。
その中でも今後の展開に影響する見どころは竹千代(嘉数一星)が聡明であるという設定である。竹千代は徳川家康の三男で、後の徳川秀忠である。一般に秀忠は凡庸で、武将としての才覚は兄の信康や結城秀康、弟の松平忠輝にも劣るというイメージがある。関ヶ原の合戦への遅参が好例である。ところが、『江』では徳川家康(北大路欣也)や本多正信(草刈正雄)に「類稀なる何かがある」と言わせている。
これに対して竹千代の兄の羽柴秀康(前田健)は冴えない。前回登場時は竹千代と剣術の稽古をしていたが、竹千代の一本を取られて、内心立腹していた。大人が演じる秀康が子役の竹千代に腹を立てることは、秀康の小人ぶりを示すことになる。今回も事実上の人質でありながら、秀吉になついてしまうという軽さを見せた。これは秀吉の「人たらし」ぶりを示す演出であるが、具体的な「人たらし」ぶりが描かれないため、安易に敵方の秀吉になびく秀康が小物に見えてしまう。
歴史上の秀康(後の結城秀康)は才能を持ちながらも、父親である家康に疎まれた悲劇の武将として語られる。ところが、『江』では秀忠を持ち上げて、秀康を下げている。これは直接的には秀忠が主人公・江の将来の夫であることによる逆ヒロイン補正になるが、「戦は嫌にござります」という江の価値観とも合致している。戦上手な秀康は貶められ、戦下手の秀忠は評価される。
『江』は江らが戦国武将に対して「戦は嫌にござります」と明言する点で突き抜けているが、「戦は嫌」という価値観自体は過去の女性視点の大河ドラマでも見られた。しかし、現代人にとっては自然な感覚でも、戦争で勝ち上がってきた武将が名を残しているという戦国時代の現実がある。従って、戦国時代劇では「戦は嫌」という価値観は現実の前に脆くも崩れ去る。主人公サイドは「やむを得ず戦争になった」と言い訳しつつも、戦で勝利し、勝利の恩恵を味わうことになる。
姉妹で敵味方に分かれる大阪の陣を描く以上、これは『江』も免れない。それでも戦下手の秀忠に類稀なる価値を見出そうとすることで、『江』では「戦は嫌」という価値観に無力な願望以上の意味を付与することができる。戦が嫌いな戦国時代劇の今後に注目である。
(林田力)







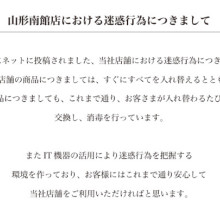




















 社会
社会








