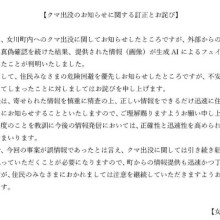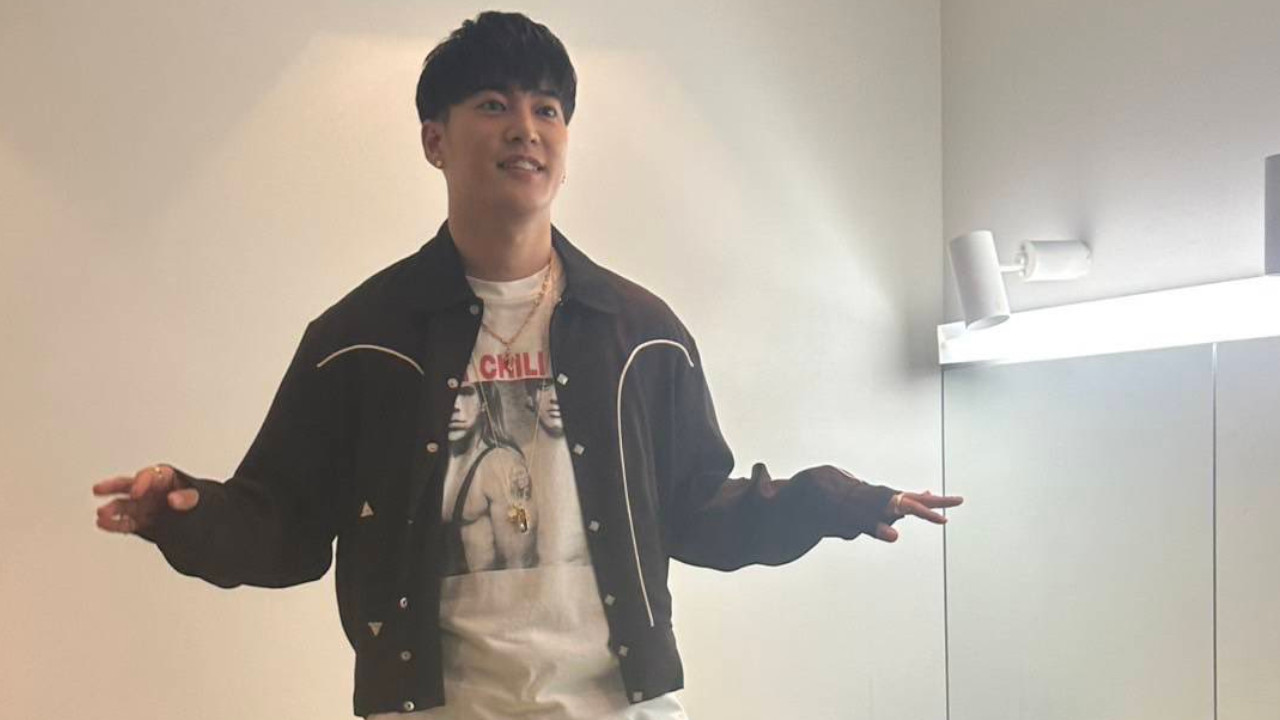また、入りたいな。
でも、今日は体の調子が悪いし、生理の血で汚しちゃったら、嫌だ。
「体をふくだけにしとく。来そうなんで」
伯母さんが急に心配そうな顔になった。伯母さんは、体を近づけてきて、私の顔をのぞき込んでくれた。
「大丈夫かい」
伯母さんは、私の生理痛がひどいことを知っている。いつか、伯母さんが私の家に来たときに、わざわざ部屋で寝ている私の様子を見舞ってくれた。
あれは中学二年のときだ。朝からお腹が締めつけられるようで、けど、無理をして学校に行った。
朝礼が始まるまで、机に伏していた。仲のいいお友だちがみんな気がついて、周りに来て心配してくれた。
お友だちに言葉を返し、顔を上げて教室の様子を眺めると、何人かの男の子が、私を見ていた。
先生が教室に入ってきた。お友だちが私のことを先生に伝えてくれた。お友だちはそのまま保健室まで付き添ってくれた。
教室から出るとき、男の子たちがみんな、私を見ていた。なんだか恥ずかしいような、くやしいような気持ちになって、涙が出ていた。
生理で泣いたのは、あの時だけだ。
「うん。大丈夫」
伯母さんに答えてから、朝、駅舎から見上げたどんよりした空を思いだした。特に山の方が暗くて、灰色の雲が渦巻いていた。
私の体の中でも、黒い血が渦巻いているのだろうか。
伯母さんが、少し、ほっとした顔をした。
「そうか。悪いね、そんなときに」
伯母さんには、心配をかけてばかりだ。
「いえ。ぜんぜん、へいきです」
「何かあったら、お風呂場の前の戸棚に入ってるから。一番上の開き戸」
この家は、生理用品は、あそこにあるんだ。
「はい」
でも、持ってきているから、借りることはないと思う。
台所から土間をつたってお風呂場をのぞいた。湯船も、スノコも、記憶のままだった。入り口ののれんまで同じ模様で、テレビの宣伝でよく見る電気ジャーのダンボール箱があったけど、家は昔のままだ。
柱が太くて黒光りしている。風が吹くとガラス戸がかたかた鳴る。天井が高くて、昔ながらの丈夫な家。
ちょうど、今の健太君くらいの年までは、毎年、夏休みとお正月に、泊まっていた。
(つづく/文・竹内みちまろ/イラスト・ezu.&夜野青)













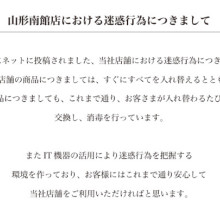
















 芸能
芸能