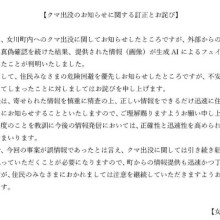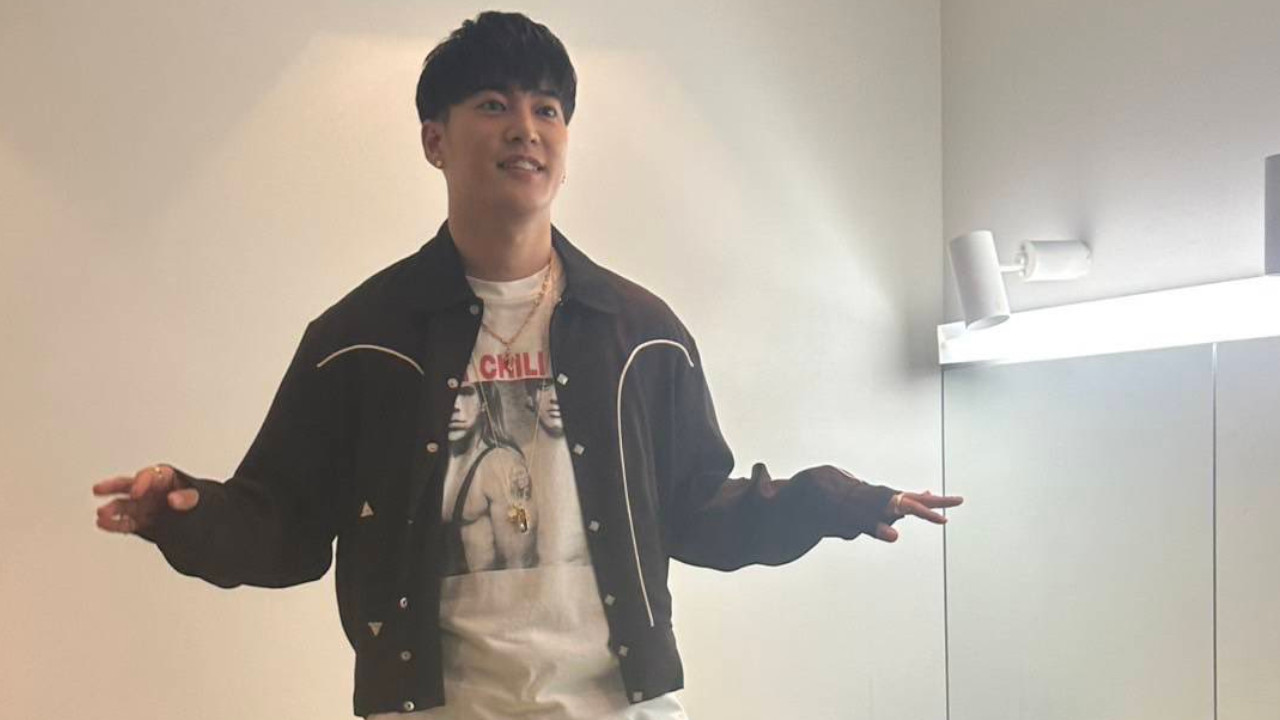驚きながら一周していると、アイスキャンディーのコーナーがあった。赤いものや、青いもの、黄色いものまで、大量のアイスキャンディーが並んでいた。頭のなめるところがみんな、丸く円を描いて、なめらかになっていた。
健太君といっしょに食べよう。
「健ちゃん、何色がほしい」
アイスクリームの色を健太君に聞くと、健太君は、しばらく眺めたあとに「赤」と答えた。
「そう、じゃあ、お姉ちゃんも赤にする」
赤いアイスキャンディーは、一番、奥にあった。
よく見ると、赤いアイスキャンディーの表面には、所々に、赤紫の筋が入っていた。ぶどうの果肉か何かが交ざっているのかな。青いアイスキャンディーや、黄色いアイスキャンディーは、表面がみんな同じ色で、模様はなかった。
手を伸ばしたら、ひじの内側がどこかに触れた。何かが服に触った感じがして、一瞬あと、肌の内側に氷をつけられたような冷たさを感じた。
反射的に、腕を引っ込めた。手もとが、青いアイスキャンディーに触れたみたい。
アイスキャンディーを取るだけでこんな思いをするなんて、デパートは、すごいんだ。辺りを見渡すと、人はたくさんいるけど、なんだかテレビの中の風景を見ている気になった。
急に、健太君が、私とアイスキャンディーが入っているコーナーとの間に、小さな体をすべり込ませてきた。健太君の後頭部が、私の胸に触れた。
健太君は、それから、前かがみになった。健太君のお尻が、腰に触れた。
健太君は、すっと手を伸ばして、赤いアイスキャンディーを二本、つまんだ。
突然のことで、しかも見とれている間に、終わってしまった。ようやく、一歩、後ろに下がると、健太君は、振り向いた。アイスキャンディーを差し出してきた。
健太君、私の代わりにアイスキャンディーを取ってくれたんだ。
健太君が、ほっぺたを膨らませて笑った。かわいい。
「健ちゃん、ありがと」
受け取ると、健太君が目を細めた。ほんと、かわいい。
レジの人が、アイスキャンディーを入れたビニール袋に、ドライアイスを入れてくれた。
(つづく/文・竹内みちまろ/イラスト・ezu.&夜野青)













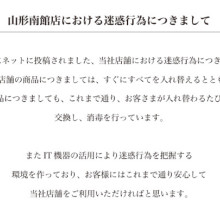















 芸能
芸能