おばあちゃんの家のお風呂は、気持ちよくて、ゆっくりできる。洗い場のスノコも、湯船のふたも、みんなヒノキだ。
小さいころ、おばあちゃんの家に泊まりに来ると、夕方にお風呂に入れてもらった。
裸になってお風呂場に入ると、ふたの透き間から湯気があがっていて、洗い場までくもっていた。
ふたに手のひらを当てると、最初は熱くて、だんだんと慣れていった。
私はいつも、湯船のふたを、すぐにはどけなかった。
ふたをそのままにしておいて、指で触った。
湯船のふたを指で触ったあと、今度は重心を落として、洗い場のスノコに、お尻から座り込んだ。目を閉じて、体じゅうの力を抜いて、ヒノキのふたの上に上半身を投げ出した。
熱に抱かれているような感触。
そのままじっとしていると、窓の外から、巣に帰る小鳥たちの羽音が聞こえてきた。
からからに乾燥したヒノキは、いい香りがする。
目を閉じたままほっぺたをこすりつけていると、木目のくぼみが、水滴か何かで濡れている場所があった。
ほっぺたに水気を感じたら、顔で木目をなぞりながら、鼻をくぼみに当てた。濡れている場所は、養分か何かが溶け込んだにおいがする。
ひととおり、においをかいだあと、最後に、唇を当てた。
熱を帯びた湿り気を口に含んで、それだけで、体が熱くなった。
それから、ようやく、私は湯船のふたを外した。
ふたを外す順番は決まっていて、最初に真ん中の一枚、次に右隣の一枚、左隣、右端、左端。そうやって外したふたを洗い場に立てかけていくと、側面の模様がそろって、削られる前の木目が浮かびあがってきた。
かき回し棒でお湯を整えてから、湯船に体を沈め、ヒノキの模様を眺めるのが好きだった。
山の夕暮れは早い。窓の外は、もう、たそがれどきだった。鳥たちは巣に帰り着いていて、山が夜を迎える気配が始まっていた。
木目が、ぼんやりとしてくる。山に、夜の闇が、広がり始める。
あのお風呂か。
また、入りたいな。
(つづく/文・竹内みちまろ/イラスト・ezu.&夜野青)









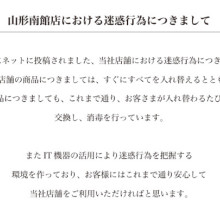



















 社会
社会








