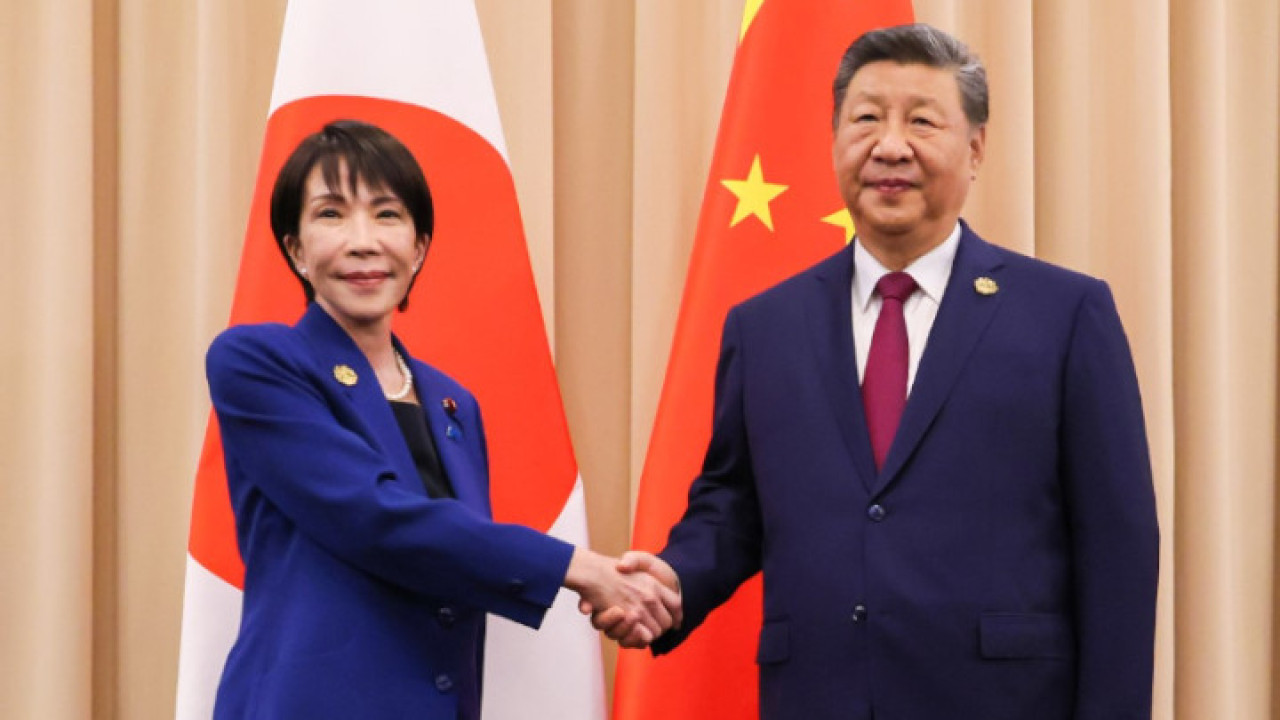居間にいる健太君へ腕を伸ばせば、体を抱き寄せられる。健太君を、ぎゅっと抱きしめてみたい。昔はよく、健太君を胸に抱いた。でも、今の健太君をこそ抱きしめたい。顔を埋めて目をつぶり、健太君のすべすべの肌を確かめてみたい。
やだ、健太君、ほっぺが紅くなっている。ほんとに、照れているんだ。
もう、がまんできない。
「健ちゃん、いらっしゃい」
健太君は、下を向いたまま返事をしない。
「お姉ちゃんが、洗ってあげる」
もう一回、言うと、健太君がようやく、ぼそぼそと口を開いた。
「ひとりで入る」
「お姉ちゃんが洗ってあげるから、服、脱ぎなさい」
健太君、うつむいて体をよじっている。ほんとうに恥ずかしいみたい。ようやく、健太君が告げてきた。
「いいよ」
健太君が「お姉ちゃんは、あっち行ってて」と言ってきかないので、健太君が行水する間、蚊帳を吊りに行くことにした。健太君は、私が居間を出るまで、立ったままじっと見張っていた。
健太君を残して、掛け軸の部屋へ向かった。
昔ながらの造りのこの家は、天井が高い。柱も太くて、夜になると、柱の上の方が薄闇に包まれてしまう。おばあちゃんがよく、天井には神様がいて私たちを見ていると話してくれた。おばあちゃんの家に泊まりに来たときは、布団に入って電気が消されると、部屋の中が急に別世界になったように感じた。
掛け軸の部屋に行くには、外の渡り廊下を使う。
掛け軸の部屋は、私が泊まりに来たときに寝る場所だ。布団に入ると、月が出ている晩は、障子に木の影が映った。あれは確か風が強かった日、月明かりが強くて、障子の青色がいつもよりもにじみ出ていた夜だ。急に、障子に大きな影が現れた。いつも見ている木の影なんかよりもぜんぜん大きかった。大人の男の人の形をしていた。それも、のしかかってくるみたいに両手を上げていた。肩幅が広かった。
そのとき、私は、幼稚園で見た赤ずきんの影絵劇を思い出した。小さな赤ずきんが森を歩いていると、いきなり、オオカミの影が布いっぱいに登場した。両手を広げて、赤ずきんに、のしかかった。
(つづく/文・竹内みちまろ/イラスト・ezu.&夜野青)









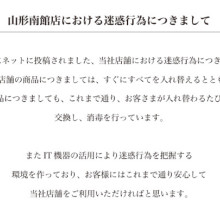





















 芸能
芸能