新旧の映画を紹介するコラム。今回は、「二十四の瞳」(木下恵介監督/1954年/日本/出演:高峰秀子、天本英世、夏川静江、笠智衆ほか)。
1973年生まれの記者は、二つ上の兄、両親、祖母との5人家族だった。近所の家でも、祖父がいる家庭は少なかったように記憶している。子ども心に、「自分がいて、兄弟か姉妹がいて、両親がいて、祖母がいて、祖父は戦争で死んだ」、それが「家庭」というものだと思っていた。
小学生のころは、高度成長が始まる前の田舎町を走り回っていた。あちらこちらで転び、ひざ小僧をすりむいていた。
思い出がある。
近所で転んだとき、前の家のお母さんが垣根から顔を出してくれた。縁側で、赤チンと呼ばれた薬を塗ってくれた。赤チンを塗り終わると「○○君、失敗の巻き」と言って、励ましてくれた。
当時、大人の女の人は、なにかあると、この「失敗の巻き」を口にしていた記憶がある。この「失敗の巻き」はなんだのだろうと、長く疑問だった。
その疑問は、映画「二十四の瞳」で解けた。毎年、夏にテレビで放映されていた記憶がある。
映画「二十四の瞳」は、瀬戸内海の村が舞台。新任のモダンガール教師・大石先生を高峰秀子さんが演じた。大石先生が自転車で島を走る姿を、村人たちが呆然と見つめる。
映画「二十四の瞳」は年代を追ってストーリーが進む。終盤では、高峰秀子さんは、おばあさんになった大石先生を演じていた。高峰秀子さんとともに、スクリーンの中の小学生たちも成長していく。高峰秀子さんの自伝「わたしの渡世日記」(文春文庫)には、映画「二十四の瞳」の企画がはじまって最初にやったことは、全国から小学校一年生と六年生のよく似た兄弟・姉妹の募集だったことが書かれていた。
その映画「二十四の瞳」の中で、高峰秀子さんが、子どもたちといっしょに、台風が去ったあとの浜辺を歩く場面があった。大石先生と子どもたちは、陽気に笑う。流木を集めて家屋の修理をしていたある小学生の母親が、人の不幸がおもしろいのかい、と嫌味を口にする。高峰秀子さんは、子どもたちを見て、小声で「小石先生、失敗の巻き」と告げる。
赤チンを塗ってくれた近所のお母さんたちは、みな高峰秀子さんのまねをしていたのだ。
近所のお母さんたちだけでなく、記者の母親も、そして、日本じゅうの女たちが、高峰秀子さんのまねをしながら、子どもたちを励まし、周りの人たちを励まし、そして、自分自身を、どれだけ励まし続けたことだろう。(竹内みちまろ)映画日和 「二十四の瞳」
新旧の映画を紹介するコラム。今回は、「二十四の瞳」(木下恵介監督/1954年/日本/出演:高峰秀子、天本英世、夏川静江、笠智衆ほか)。
1973年生まれの記者は、二つ上の兄、両親、祖母との5人家族だった。近所の家でも、祖父がいる家庭は少なかったように記憶している。子ども心に、「自分がいて、兄弟か姉妹がいて、両親がいて、祖母がいて、祖父は戦争で死んだ」、それが「家庭」というものだと思っていた。
小学生のころは、高度成長が始まる前の田舎町を走り回っていた。あちらこちらで転び、ひざ小僧をすりむいていた。
思い出がある。
近所で転んだとき、前の家のお母さんが垣根から顔を出してくれた。縁側で、赤チンと呼ばれた薬を塗ってくれた。赤チンを塗り終わると「○○君、失敗の巻き」と言って、励ましてくれた。
当時、大人の女の人は、なにかあると、この「失敗の巻き」を口にしていた記憶がある。この「失敗の巻き」はなんだのだろうと、長く疑問だった。
その疑問は、映画「二十四の瞳」で解けた。毎年、夏にテレビで放映されていた記憶がある。
映画「二十四の瞳」は、瀬戸内海の村が舞台。新任のモダンガール教師・大石先生を高峰秀子さんが演じた。大石先生が自転車で島を走る姿を、村人たちが呆然と見つめる。
映画「二十四の瞳」は年代を追ってストーリーが進む。終盤では、高峰秀子さんは、おばあさんになった大石先生を演じていた。高峰秀子さんとともに、スクリーンの中の小学生たちも成長していく。高峰秀子さんの自伝「わたしの渡世日記」(文春文庫)には、映画「二十四の瞳」の企画がはじまって最初にやったことは、全国から小学校一年生と六年生のよく似た兄弟・姉妹の募集だったことが書かれていた。
その映画「二十四の瞳」の中で、高峰秀子さんが、子どもたちといっしょに、台風が去ったあとの浜辺を歩く場面があった。大石先生と子どもたちは、陽気に笑う。流木を集めて家屋の修理をしていたある小学生の母親が、人の不幸がおもしろいのかい、と嫌味を口にする。高峰秀子さんは、子どもたちを見て、小声で「小石先生、失敗の巻き」と告げる。
赤チンを塗ってくれた近所のお母さんたちは、みな高峰秀子さんのまねをしていたのだ。
近所のお母さんたちだけでなく、記者の母親も、そして、日本じゅうの女たちが、高峰秀子さんのまねをしながら、子どもたちを励まし、周りの人たちを励まし、そして、自分自身を、どれだけ励まし続けたことだろう。(竹内みちまろ)













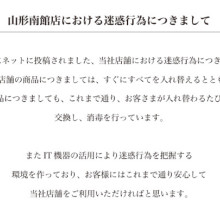














 芸能
芸能








