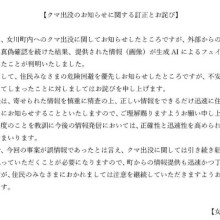数日前から熱があり全身がだるかったが、徳次は風邪を引いたのだろうと思っていた。そんなことよりも京都市から受けた注文の製作に集中していた。菊の御紋を彫り込む14金の特製シャープペンシルで、皇后への献上品なのだ。徳次は必ず入浴して身を清めてから献上シャープペンシルの製作にかかり、この仕事の最中は他の者を寄せ付けなかった。ようやく仕上げた途端、徳次は床に倒れ込んだ。熱は40度にもなっていた。
文子からの電話で近くの医者が往診に駆け付け、診察してくれた。けれども翌日も、その次の日も熱が引かず、食事も受け付けなかった。3日目になっても熱は下がらず、徳次の衰弱がひどかったので、文子は徳次の姉や兄に電話をした。欣々が医学博士の碓居竜太を伴って黒塗りの馬車で駆けつけた。
碓居博士の診断は、悪性の腸出血ということだった。徳次が大量に吐血すると、碓居博士は、腸出血に詳しい東大の真鍋博士を連れて来るために欣々の馬車を借りて大急ぎで出かけた。真鍋博士は新薬の血清を携えて来た。そして到着するとすぐ、その血清を立て続けに注射した。この新薬はまだ一般には使用されていない貴重な物だった。
欣々の他に登鯉子、政治、熊八、ひさ、芳松夫妻が集まった。巻島夫妻はお百度参りをしていた。2人の医学博士から、一度は「もう時間の問題です」と宣言され、「あと10分でご臨終」とまで言われた徳次は、奇跡的に死の淵から生還した。
その後、2が月間は病床にあったが、桜の咲くころには半身起き上がれるようになり、八月末には初めて外出の許可がでた。こうした経過の中で、徳次は自分に人間的な愛情を持ってくれている人々がいることに深い喜びを覚えた。そして今まで無理をして体を酷使していたことも同時に反省した。