テーブルのところに伯母さんがいて、健太君のお茶碗やおはしを、お盆の上に乗せていた。伯母さんは、忙しそうだ。
伯母さんに声をかけた。
「私、やります」
伯母さんが笑顔で、手を止めた。
「そう、じゃあ、さっそくお願いしちゃおうかね」
土間の向こうにしつらえられた台所へ、お盆を運んだ。伯母さんも台所に来て、カレーのお鍋の火を消した。
伯母さんがふたを開けると、湯気が一気に広がって、高い天井へ登っていった。カレーは、よく煮えている。あくがていねいに取られていて、いい香り。
伯母さんも、カレーの出来映えに満足そうな顔をしている。
「晩ごはんは、これで済ませちゃって。食べ終わって冷めたら、鍋ごと、冷蔵庫に入れておいてくれると助かるよ」
伯母さんが台所の奥を見た。
大きな冷蔵庫だ。新しく買ったんだ。
「健太は、いつも寝てる部屋でいいから。美雪は、掛け軸の部屋で寝て。蚊帳と布団は、出しといたから」
伯母さんは、そう言いながら、カレーの鍋にふたを戻した。
この家は、昔ながらの農家の造りで、天井が高い。土間の壁と壁の間には、地面の方に曲がり気味の柱が通してある。間取りもゆったりとしている。
掛け軸の部屋は、奥の離れた場所にあった。母屋とはつながっているけど、縁側から外廊下を伝って行く。客間として使われることが多い、広い部屋だ。
掛け軸の部屋の前を通り過ぎると、今度は、ちゃんとした渡り廊下がある。渡り廊下は、歩きながら、庭や、がけを眺めることができる。
渡り廊下の先は、お便所になっていた。
中に入って扉を閉めると、急に閉じ込められた気持ちになる狭い場所だ。お便所の窓の外からは、葉っぱが揺れる音が聞こえてくるし、昼間でも薄暗くて、小さいころは、怖かった。
渡り廊下には、ぼんやりした電球が一つ、ぶら下がっていた。けど、月のない夜は、足もとをわずかに照らすだけで、渡り廊下の先の方も、暗闇に包まれていた。
小さかった私は、夜中にお便所に行くときは、いつも、あやかしたちが軒下から私のことを見ているのだと思っていた。
今でも、お便所に行くと、壁に、やもりがへばりついていたりするのだろうか。
(つづく/文・竹内みちまろ/イラスト・ezu.&夜野青)















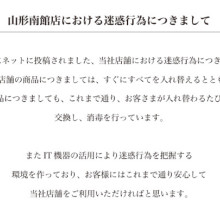














 芸能
芸能








