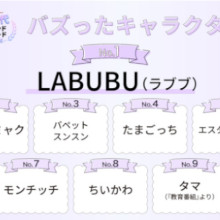しかし、ここに来て、やはり「ポスト佐藤」をうかがう福田赳夫が、佐藤に接近していると取り沙汰されるようになった。佐藤派ベテラン議員の一人は、当時の佐藤の胸中を筆者にこう語ってくれたものだった。
「佐藤は六分四分で福田を先に、そのあとに田中政権をとの思いがあった。佐藤と福田は、ともに官僚出身で気心を通じており、福田は田中より年齢的にも上だったからだ。しかし、佐藤政権は実質上、田中と福田の両雄に支えられていたことから、佐藤はこのバランスを崩すことを極力避け、得意のチェック・アンド・バランスの人事で、どちらを後継者に考えているかは、最後まで誰にもシッポをつかませなかった。ために、田中も福田も、必死で佐藤政権を支え続けたのだ」
現首相の安倍晋三に抜かれるまで、7年8カ月という戦後最長の首相在任記録を持っていた佐藤だが、長期政権を維持する秘訣の一つに、人事の巧みさということがあった。
その手法は、先のコメントにも出ていたようにチェック・アンド・バランスの「均衡人事」であった。佐藤政権を支える有力議員の“突出”を抑え、時に干しては引き上げ、引き上げてはまた干すという手法である。突出しようとすれば干されることから、結局、誰もが佐藤に逆らえずで、ひたすら長期にわたって佐藤政権を支え続けたということだった。
この佐藤の手法はビジネス社会でも見られ、人事に巧みなトップリーダーが権力を温存し、その地位を長く保つケースが多いことに似ている。例えば、佐藤は田中を幹事長に就けると福田を大蔵大臣に、田中が幹事長を降りるとその後釜に福田を据え、絶妙のバランスを取ったのである。
そうしたうえで、佐藤内閣最後の人事となった昭和46(1971)年7月の第3次改造内閣で、佐藤は福田を外務大臣に、田中を通産大臣に起用し、両雄のバランスになお腐心した。福田には「沖縄返還」を確実に着地させる役目を、田中には米国が怒りの声を強め、難航している「日米繊維交渉」の妥結を担わせた格好だった。
とくに、この繊維交渉の決着がなければ、「沖縄返還」がスムーズに運ばぬ可能性もあり、田中としてはなんとしても妥結させなければならない立場にあった。佐藤の退陣は「沖縄返還」をもってというのが既成事実化されており、この交渉の成否は自らの総裁選にも影響することから、田中としてはこの期に及んでの通産大臣就任は、人生の勝負どころと言ってよかったのである。一方の佐藤は、その成否はもとより田中の腕力に懸けたということだった。
ちなみに日米繊維交渉とは、昭和44年12月、時の米国のニクソン政権が、繊維製品の対米輸出の伸びに反発、日本に対して輸出の自主規制を求めてきたことから始まった交渉である。
ところが、日米双方の主張には隔たりがあり、田中の前の通産大臣だった大平正芳、宮澤喜一が3年かけて交渉に当たったものの、いっこうにまとまる気配がなかった。
★日米繊維交渉で見せた「凄腕」
しかし、田中通産大臣は、なんとこれをわずか3カ月あまりで決着させてしまったのだった。
米国側は、「米国全体の貿易収支が悪化しているのは、突出している対日貿易赤字が原因だ」と激しい批判を浴びせてきた。対して田中は、「角栄流」交渉の特徴である常に相手の論理に合わせ、相手の土俵に上がって理路整然と切り返したものだった。
結果、米国は日本側の最終案をのむことで、足掛け3年余の難航を重ねたこの交渉は決着をみた。その決着した最終案について、田中は「われわれは負けはしなかったが、主張しているだけでは解決しない。繊維問題をこれ以上こじらせたら、日米関係がいよいよ悪化する。理不尽ではあるが、相手の要望ものまねばならん。その代わり、日本の業界を救済する」としたのである。
すなわち、当時のカネで2000億円を繊維業者損失の補償として出し、国内業者とも手を打っての交渉、妥結ということだった。ただし、「田中はイト(繊維)を売って、ナワ(沖縄)を買った」との陰口はあった。
一方で、交渉に同席していた通産官僚は、田中の交渉能力の凄みを次のように語っていたものである。
「交渉能力の高さには、さすがに度肝を抜かれた。気迫の凄さ、理解力、頭の回転の速さ、弁論の切り口、どれをとっても当代一流。田中大臣以外だったら、あの交渉は間違いなく暗礁に乗り上げていた」
かくて、佐藤首相はこの交渉の妥結に伴い、「沖縄返還」を規定通り実現させることができた。昭和47年5月15日である。
それから約1カ月半後の7月5日の自民党総裁選は、「角福総裁選」と言われたように、事実上、田中と福田の熾烈な争いとなり、田中が勝利をおさめた。
結局、佐藤が福田のために多数派工作で動いた形跡は、なかったのである。
(文中敬称略)
***********************************************
【著者】=早大卒。永田町取材49年のベテラン政治評論家。抜群の政局・選挙分析で定評がある。著書に『愛蔵版 角栄一代』(セブン&アイ出版)、『高度経済成長に挑んだ男たち』(ビジネス社)、『21世紀リーダー候補の真贋』(読売新聞社)など多数。