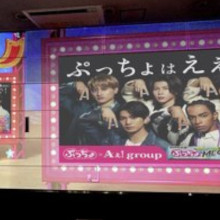レノボといえば、「Superfish」(通信傍受)疑惑という“前歴”を抱えている。こうしたこともあってか、レノボの楊元慶CEOは、「レノボはグローバル企業で、中国企業ではない」とかたくなに繰り返す。中国の指示があったと思われたくないからだが、資本関係を見る限りどうみても中国企業だ。
2004年のレノボによるIBM社のPC部門の買収により、株式の42.3%をレジェンドホールディングスという持株会社が保有しており、同持株会社の筆頭株主(65%)は、中国政府機関の中国科学院だ。また中国政府は間接的にレノボの27.56%を保有する筆頭株主で、どこから見ても紛れもない中国企業だ。
ところが「中国企業ではない」という楊CEOの発言は中国国内で罵声を浴び、国内向けには「中国の企業だ」とはっきり認めるハメに。よほど中国という祖国が非難を浴びるようなことをやっている、やってきたと語るに落ちたとはこのことだ。
米国はかねてファーウェイの通信機器を通じて中国が不正に通信を傍受しているとして、同社製品を米国市場から締め出してきた。米企業がレノボを提訴したことで、いよいよ米国による“ウミガメ掃討作戦”が本格化したのだろうか。
「ウミガメ族」とは、中国から海外に留学してから帰国し、中国の経済発展を支えてきた300万人超の人材のことだ。彼らの中には米国で最先端技術を研究してきた人材も少なくない。こうした人材を通じて、中国は先端技術を海外から吸収しているのだ。
中国のネット検索大手で、最近は自動運転技術の開発に力を入れる百度(バイドゥ)の張亜勤総裁やアリババ集団が出資する顔認証技術のスタートアップ、北京曠視科技(メグビー)の創業者、印奇氏も「ウミガメ族」だ。
グローバル経済の下で、有能な人材を介して中国に流れ込む新技術のネタの数々。中国の特許出願数も急増し、自前の開発力にも磨きをかける。半導体やAIなどでは、世界トップレベルの水準を誇る技術領域も出てきている。技術覇権に向けて着々と手を打つ中国に対して、トランプ政権が焦りを強めるのもムリはない。