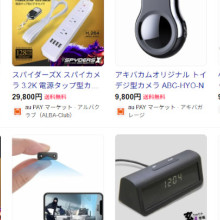日本の教員の仕事時間は国際平均に比べ、1週間当たり小学校で約12時間、中学校で約14時間長い。例えば中学で見ると、米国より9.8時間、韓国より12.0時間、フランスより16.4時間長く、日本の長時間労働が目立つ。
長時間労働の主な要因としては、授業以外の業務、すなわち事務作業と課外活動(部活動など)に費やす時間が長いことだ。特に中学校の課外活動では、国際平均の3倍以上の時間を費やしており、長時間労働の大きな要因となっている。
では、保護者から尊敬されているかといえば、そうではなさそうだ。教員を評価するという意見はOECDの小学校の平均は68.6%なのに対して日本は49.8%、OECDの中学校の平均65.4%に対して日本は45.0%といずれも過半数に満たない。
教師の勤務環境に詳しい一般社団法人ライフ&ワークの妹尾昌俊代表理事は、「保護者(母親)の高学歴化と晩婚化で教員より年上の保護者が増え、教員の専門性や優位性についての評価が相対的に低い傾向になっている」と話す。つまり、自分より年下ということもあってか、保護者が教員を下に見ているケースが増えてきたということだろう。
コメンテーターでジャーナリストの浜田敬子氏は学校現場の人手不足を指摘する。
「体調不良で休む先生がいると、他の先生たちでカバーしている。代理の先生がすぐに来るわけではない。保護者への対応にも多くの時間を使っている。事務作業については予算を取ってサポートスタッフをつけるべき」
コメンテーターの安部敏樹氏(リディラバ代表)は、残業時間をしっかりカウントして残業代を支払うべきだと主張する。
「求人倍率が下がっており、結果として先生の質が落ちてくる。先生の質が落ちれば保護者がクレームを出す。そうするとそのクレーム対応に追われる。負のサイクルに入っている」
“モンスターペアレント”という言葉が世間に広まったのは2008年のテレビドラマが大きなきっかけだった。背景には少子化で過保護親が増えたことや、親自身の孤立化とストレス増加などが指摘される。最近はSNSによって学校への不信感や誤解が増幅されていることもある。簡単には解決できない問題だ。