「ようし、次はどこで野営だ」
当時、徳島第一団はキャンプを得意とする団であり、年中あちこちでテントを張っていた様々なキャンプ大会もあった。徳島中の団が集まる大規模なキャンプ大会。徳島第一団だけで行う隊キャンプ。自分の所属する班が徳島第一団の敷地内で行う班キャンプ。
「この夏もキャンプやるぞぅ」
キャンプ好きだった筆者は喜んで、このキャンプに参加した。
ある年の夏、中学二年だった筆者は、隊キャンプとして園瀬川の河原で野営した。
「なんか、怖いな、俺らだけ離れとるなぁ」
「ほんまやな、本部からも遠いし」
河原に隊の全員がテントを張るのだが、どういうわけだが自分たちの班だけが一番端に野営することになった。隊長や大学生、高校生の先輩たちがいる本部は程遠い。
「こんなんで、泥棒の襲撃でも受けたら、やばいんとちゃうか」
「ほんまやなぁ」
竈をつくりながら後輩たちが、ふと弱気な発言をした。既に班のリーダーであった筆者は内心、不安に思ったものの、後輩たちの手前、強気に振舞った。
「なにゆうとるんじゃ、わいがおるからいけるわぁ」
と言ったものの、実は内心不気味な気配を感じていた。
「わかりました」
後輩たちは、筆者の言葉に勇気付けられ、夕食のカレーづくりも終わり、キャンプファイヤー後、無事就寝となった。だが、やはり少年たちの予感は当たった。界の住民による事件は起こったのだ。
就寝時間の後も、しばらく昼間の失敗などを冗談を交え、話し合っていた。キャンプの楽しみのひとつである。すると、後輩の一人が声をあげた
「……ん、あれ、なんか聞こえる」
「ほんまやな、足音かいな」
突如、奇妙な音が聞こえたのだ。テントの近くで音がする。
「確かに、足音が聞こえてくるわ」
後輩たちが騒ぎ始めた。いかん、このままではパニックになってしまう。
「まず、落ち着け、冷静に状況を見なあかん、それがボーイスカウトちゃうか」
筆者も、努めて冷静に、語りかけた。この時、私の耳にも確かに奇妙な足音が聞こえていた。
「先輩、どないしょう」
後輩たちはまだ震えている。
「まぁ、わいにまかしとけ」
四名の後輩を落ち着かせると、筆者は言った。
「この足音、ひょっとしたら、噂のキャンプ場荒らしかもしれん、だとしたら、いきなり出たら危ないぞ」
そう言うと、私はこの足音に注意を払ってみた。なるほど、我々五名が寝ているテントの周りを、ぐるぐる廻っている。まるで、何かを観察しているかのようであった。しかも、足音はテントの周りの雑草を踏みしめる音である。
「なるほど、泥棒はわいらの出方を見とるな、おいテントまくって泥棒の足の動きを見てみい」
そう後輩に指示を飛ばすと後輩はおそるおそるテントの裾をまくった。
「先輩、めくりました」
外部の雑草が見えた。全員で前かがみになって外を覗いた。
「えええっ」
我々はその場で全員が硬直化した。なんと、足音と同時に雑草が倒れていくのだが、足が見えないのだ。
「足が、みっ、見えん」
見えない足によって踏み潰される草。依然として、足音は聞こえ続け、テントの周りを廻っている。
「なんやろ、あれ」
筆者は思わずつぶやいた。この言葉に、全員が沈黙した。すると、大学生の先輩たちが見回りに来た。夜間の定期パトロールである。がやがやと、話ながら近づいてくる。
「助かった」
その瞬間,足音がぴたりと止まった。我々も一斉にテントの外に出ると先輩たちに駆け寄った。
「うわ〜、霊が出ました」
「出たけんど、泥棒でなくて、幽霊だったわ」
我々は口々に大学生の先輩に説明したが、笑われてしまった。
だが、あれから二十六年が経った今でも、あのシーンは目に焼き付いている。透明な足が、雑草を踏み倒していく瞬間。
あれは、真夏の夢であったのか。
それとも、少年の日の幻想だったのか。
監修:山口敏太郎事務所









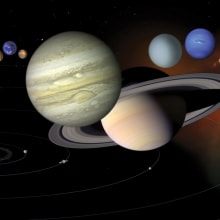





















 芸能
芸能








