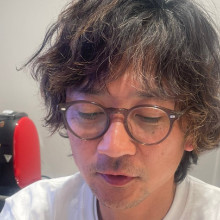経営コンサルタントが解説する。
「アサヒは今年から販売量のデータ開示を取りやめたが、各メディアが’20年上半期の販売実績や内部資料をもとにシェアを推計したところ、キリンが37・6%、アサヒは34・2%となり、逆転が判明したのです」
同コンサルタントによると、逆転の背景には以下の2つがあるという。
(1)新型コロナウイルス感染拡大の影響で外食が避けられ、巣ごもりで「家飲み」が増えた。
(2)消費者の「節約志向」が高まり、低価格ながら贅沢な味わいを追求した「新ジャンル(第三のビール)」に人気が集まった。
それは業界全体の数値でも明らかだ。ビール大手4社の上半期販売実績によると、全体の販売量シェアはビールが38%と、前年同期より8%落ちた。これに対して新ジャンルは同8%伸びて49%と、ほぼ過半数に達し、’04年に登場して以来、初めてビールを上回った。
市場の分析を続ける前に、ここで新ジャンルとは何か、あらためて簡単に説明しておこう。
主原料として麦芽を50%以上使用したものがビール、麦芽が50%未満のものは発泡酒と呼ばれる。この発泡酒に別のアルコール飲料を加えたものや、麦や麦芽以外の大豆やエンドウ豆、コーンなどを使ったものが、第三のビールと呼ばれる新ジャンルである。
’04年2月にサッポロビールから『ドラフトワン』が販売され、これが業界では初めて新ジャンルに分類される商品となった。発泡酒より税率が低いため、販売価格を抑えられるのが特徴で、例えば、350ml缶の価格で比較すると、新ジャンルは税込み127円程度とビールの218円程度より80円ほど安い。そのため「家計にやさしい第三のビール」として、一定のシェアを確保してきた。
しかも、今年上半期は新ジャンルがビールを抜き、これに力を入れたキリンがトップになったのだから、業界は大騒動だ。
さて、本論の首位逆転が起きた背景分析に戻ろう。まず、首位の座を奪われたアサヒだ。アサヒの主力はビールで、その中でも特に『スーパードライ』がメイン。ところが、そのスーパードライは上半期、前年比26%減と大きく落ち込んだ。
業界関係者が言う。
「アサヒのスーパードライは特に業務用シェアが高く、飲食店向けの販売比率が約50%に達します。新型コロナウイルスの影響で外食産業が軒並み休業したため、アサヒはストレートに大ダメージを受けたのです」
一方、キリンはどうか。キリンの販売比率はビール、新ジャンルともほぼ均等なのだが、ここ数年前から新ジャンルに力を入れ始めていたという。
「これまで新ジャンルを選択する人はコストの安さを重んじ、味の面では妥協していた。キリンはその発想を変え、低価格でもビールと同等か、それを超える新しい味を提供できれば売れると見込んだのです」(同)
そこでキリンは、本格的な苦みを持った『本麒麟』の開発に取り組んだ。本麒麟は、キリンの代表的ビール『キリンラガー』に使用しているドイツ産のホップを一部使用し、従来商品より1.5倍の長期低温熟成を行うことで、うまみのある味わいを求めた。
また、アルコール度数を6%にアップするなど、従来の新ジャンルに欠けていたとされる「力強いコクと飲みごたえ」を追求したという。
「一方でCMにも力を入れた。意外にも、これまでアルコール飲料のCMに出演したことがなかったタモリを起用し、その飲みっぷりが視聴者から支持されています」(同)
結果、本麒麟は爆発的に売れた。’19年には1510万ケース(1ケース大瓶20本)で、対前年プラス61%という驚異的な伸びを示した。その勢いは今年も続いており、’20年の販売目標を1900万ケース、前年比26%増を目指している。
さて、この本麒麟の快走に各メーカーも、新ジャンルを制することなくして他社に勝てないと意識するのは当然。今や熾烈な「第三のビール戦争」が勃発しつつある。
まず、首位奪還を目指すアサヒは3月、麦を贅沢に使用してコクと深い味わいを実現した『アサヒ ザ・リッチ』を発売。7月までに当初目標の400万ケースを突破する好調ぶりだ。
市場シェア3位のサントリーは、’07年の発売以来、’19年までに3億6200万ケースを売り上げた「金麦シリーズ」に力を入れている。上半期に20%増えた『金麦 糖質75%オフ』をさらに伸ばす考えだ。
同4位のサッポロも負けてはいない。2月に発売された『ゴールドスター』は、同社の2枚看板『サッポロ生ビール黒ラベル』の麦芽と『ヱビスビール』のホップを一部使用しており、売り上げも好調。販売目標を360万ケースから460万ケースに上積みした。
今後、各社が激しい競争を繰り広げる中で、酒税法の改正は大きなポイントだ。ビールは10月に税額が350mlで7円下がる。一方、新ジャンルは同じく約10円上がるという。
さらに’26年には、ビール、発泡酒、新ジャンルの区分けがなくなり、税額が一律同額になる。熾烈な戦いが続く中、最終勝者はまだ読めない。