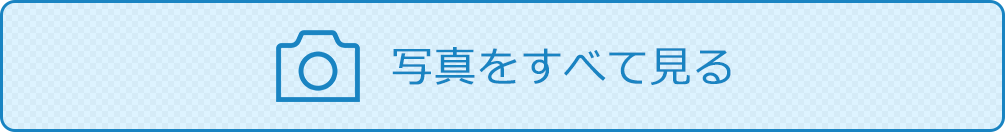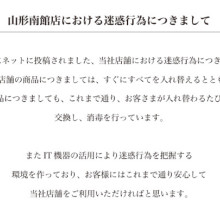坂が始まる場所に、坂名の由来を示す碑が建っている。「坂の途中にあった高田八幡(穴八幡)の御旅所で神楽を奏したから、津久戸明神が移ってきた時この坂で神楽を奏したから、若宮八幡の神楽が聞こえたから、この坂に赤城明神の神楽堂があったからなど、いずれも神楽にちなんだ諸説がある」と記されていた。
神楽坂の道幅は広くはないが、坂の両側には、白玉ぜんざいや季節のあんみつを出す甘味処、瀬戸物といっしょに雑貨を飾る店などが並んでいる。また、文房具店・相馬屋では夏目漱石が愛用した原稿用紙を買うことができる。相馬屋は創業当時は和紙をすいて江戸城に納めていたが、明治期、和半紙だった原稿用紙の資材を、尾崎紅葉の助言で洋紙に替えて売り出した店だ。
その神楽坂に、「神楽坂の毘沙門さま」として知名な善国寺がある。徳川家康の意を受けて、文禄4年(1595年)に創建された。善国寺の毘沙門天像は、室町時代の造立と推定され、戦国武将であった加藤清正の守本尊だったともいわれている。江戸期から多くの参詣者を集め、縁日は東京の山の手でも指折り数えるにぎわいを見せた。記者が訪れた日は、境内の前で、生花、ざるやかご、おせんべいなどが売られていた。
坂を上り終えてそのまま歩くと、右手に赤城神社の鳥居が見えた。この日は、赤城神社でも、手づくり品や野菜を売る市が立ち、抹茶の茶席も用意されていた。参道の階段を上り、お参りを済ませたら、(ビルや建物が多いが)街の風景を見渡すことができた。
抹茶をいただき、赤城神社をあとにした。そのまま歩いて、今度は、左の小道に入った。夏目漱石の胸像があった。「漱石山房通り」と記された柱も建っている。漱石が晩年を過ごした家の跡地につくられた漱石公園だ。漱石山房とも呼ばれた家には、毎週木曜日の「木曜会」に、多くの関係者が集まりサロンを形成していた。
漱石公園をあとにし、「夏目漱石誕生之地」と彫られた碑が建つ夏目坂を下り終えたら、穴八幡神社の鳥居が見える。鳥居の横には、「高田馬場・流鏑馬(やぶさめ)射手」という神事の像もある。徳川将軍家の厄除けや男子誕生の祝いなどに、高田と呼ばれた場所にあった幕府の馬場で流鏑馬が奉納されたそうだ。
なお、穴八幡神社の向かいにある戸山公園は、東京都心の環状線であるJR山手線内で最も標高が高い人造の箱根山がある。戸山公園がある場所には、かつて徳川将軍家の庭園があったといわれている。(竹内みちまろ)