階段を登っている時は、屋根と、門も見える。健太君は、帰り道の間じゅう、なんだかおかしそうに、私を見て笑っている。どうしたんだろう。何かうれしいことでもあったのかな。
おばあちゃんの家の門までたどり着いた。屋根のはじっこに、鬼瓦が見える。文字通り、口をひょうたんの形にゆがませた鬼が、牙をむき出しにしている。おばあちゃんのお父さん、私のひいおじいちゃんにあたる人が、わざわざ京都の鬼師のところまで頼みに行ったそうだ。鬼門にしつらえてある。
山がなびいている。風の音が聞こえる。ここも、風が強くなっている。風音に一瞬、遅れて、山を覆う枝木の海に、葉っぱの波が立った。山並みを伝って、何かが空から降ってきそう。
魔除けの面が空をにらみつけている。
鬼瓦が視線を送る先で、鳥が群れていた。同じ場所を回りながら、下界を見ている。何かを探しているみたい。何を探しているのだろう。エサかな。鳥は何を食べるのだろう。人間だ。鳥たちは、橋の下に誰かが吊されるのを待っているんだ。誰が吊されるのだろう。悪いことをした男の子。裸にされて、吊されるんだ。男の子は、恥ずかしそうにほほを紅色に染めて、待っているんだ。世が乱れる。
この空のどこかに、怪鳥がいる。
「ねえ、お姉ちゃん」
健太君が、服をひっぱってきた。健太君、笑っている。
「なに」
聞いても、健太君は、笑いながら私の服をひっぱるだけだ。健太君、どうしたんだろう。
「どうしたの」
「あのね」
健太君がアイスキャンディーが入ったビニール袋を持ち上げて見せてきた。
「お姉ちゃんが座ってた石の所に置きっぱなしになってたよ」
いけない。川原に置き忘れた。それで、健太君、ずっとにやにやしてたんだ。私、今日はどうかしてる。やっぱり、体調が悪いんだ。
健太君は私にビニール袋を渡すと、笑いながら家の中に走っていった。
(つづく/文・竹内みちまろ/イラスト・ezu.&夜野青)









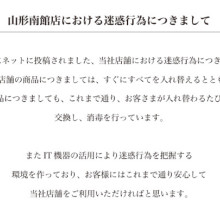




















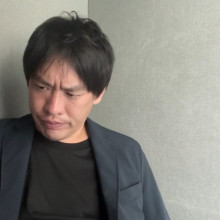
 社会
社会








