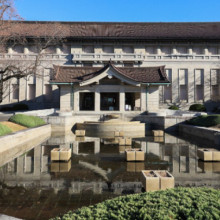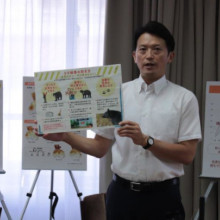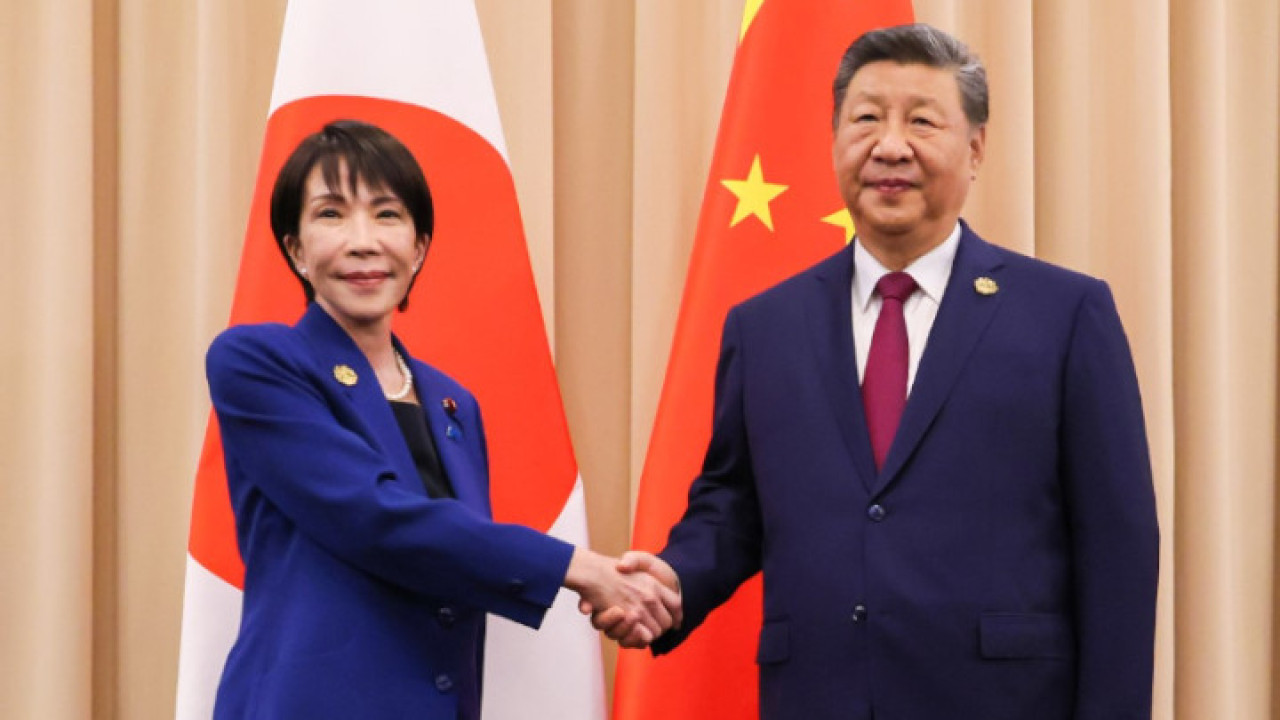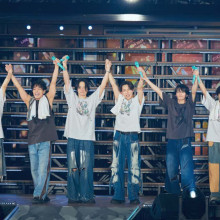立花容疑者は知事選関連の動画を100本以上投稿し、YouTube動画は合計約1500万回と、圧倒的な数で再生された(選挙期間中/ネットコミュニケーション研究所調べ)。しかし、動画を作成していたのは、立花容疑者や斎藤元彦知事の支持者だけではなかった。
政治系YouTuberとして“切り抜き動画”を配信する関東在住の男性は、再生回数がもっとも多かったのが兵庫県知事選で、YouTubeから月87万円超の広告収入を受け取った。「(YouTuber同士で)競争が起きるのでサムネやキーワードがどんどん過激になっていくが、うそじゃないかというレベルになると自分は身を引いた」と振り返る。
政治系チャンネルの“切り抜き動画”コンテンツは仲介業者を通じて、一般に制作依頼募集が出されている。斎藤知事を支持する動画作成を受注していた大学生は「僕自身はそう思っていたわけではないが、仕事としてやっていた」とバイト代目的だったと明かす。
メディアとSNSの問題に詳しい法政大学の藤代裕之教授は、「ヘイトや誹謗中傷など発言側の責任が指摘されがちだが、(発言が)注目されるとお金がもうかる仕組みが問題。規制は表現の自由を毀損するおそれもある。発信することによるもうけを抑制する。これだとリスクが少ない」と提案する。
「斎藤おろしの黒幕の1人」との誹謗中傷を受けた丸尾牧兵庫県議はXなどプラットフォーム事業者らに100件以上の開示請求や削除を求める裁判を起こしてきた。しかし、裁判所が開示決定を出すまで7カ月もかかった。今後、さらに選挙とSNSは切り離せなくなるので、開示請求に迅速に対応できるシステムが不可欠になってくる。
一方、デマや誹謗中傷を後悔する人も出始めている。動画で「知事の疑惑のネタをでっちあげた」と拡散させ、丸尾県議から開示請求を受けた人物が、県議に謝罪の手紙を送った。
「YouTubeの収入で家族を支えてきましたが、現在は生活面でも困難が続いており、別の収入手段を模索しております。誤った情報や表現によりご迷惑をおかけしたことを真摯(しんし)に反省しており、穏便にご対応いただきますよう心よりお願い申し上げます」という内容だった。
丸尾県議は「率直に謝罪をしていただいたことは、ホッとする半面、素直に100%『はい、もうこれでいいです』ということにはならない」と語った。
立花容疑者が逮捕されても、SNSや法律が変わらなければ、根底の問題は解決しない。