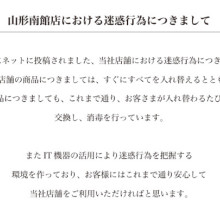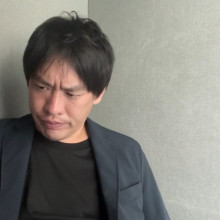小説『関ケ原』(司馬遼太郎)は、著者が少年のころに琵琶湖畔を歩いた思い出から始まる。ある寺の縁側に著者が涼を求めて座ると、老人から、豊臣秀吉もこの場所に腰掛けたという伝承を聞く。また、石田三成の居城があった佐和山に登った著者は、佐和山城がわずか19万4千石の石田三成には不相応の巨城だったと感じたことが紹介される。
『関ケ原』は、石田三成に焦点をあてた創作だ。秀吉の死後、天下が乱れると確信していた三成は「野望のもちぬし」として描かれている。三成のライバルは、関ケ原の戦いで三成と日本を二分した徳川家康。秀吉の死後に本格化した三成と家康の戦いが『関ケ原』の主な内容となっている。
『関ケ原』では、「ものが見えすぎる」三成が次々と敵を作っていく様子も描かれている。他人を型にはめて自分の中で思い詰めていく性格、義に殉じるのは当然と他人にも自分の思想を当てはめて考える発想、愛想笑いなどせずに正論ばかりを並べていく不器用さは、三成の部下である島左近の目には「人の反感を買うような小道具が、これだけそろっている男もめずらしいであろう」と映る。
『関ケ原』には、初芽という少女が登場する。反三成派の大名・藤堂高虎から送り込まれた間者で、秀吉の妻であり豊臣秀頼の母である淀殿の心を三成から切り離すことを命じられている。しかし、初芽は、実利への欲望がむき出しになる戦国時代にあっては短所や弱点と目された三成の実直さにひかれていく。
『関ケ原』では、人情家を演じながら大名たちを取り込んでいく家康が、利益や感情では動かない上杉景勝や、直江兼続、島左近、大谷吉継などが三成のもとへ集結していくことを、内心では恐れていた様子も描かれていた。
決戦の場所、関ケ原に集結した軍勢は、豊臣の旗をかかげた三成の西軍10万、対抗する家康の東軍7万5千。布陣図だけを見れば、戦いに慣れた宇喜多秀家を中心とする野戦部隊をはじめ、長宗我部盛親、吉川広家、毛利秀元、長束正家、安国寺恵瓊(えけい)、小早川秀秋の大軍が東軍を取り囲み、秀忠遅参のため徳川本隊を欠き福島正則をはじめとする豊臣恩顧の大名を主力とせねばならない東軍よりも、西軍のほうが圧倒的に有利だ。いざ、戦いが始まってみても、宇喜多隊が次々と攻め手を跳ね返し、誰の目にも西軍優勢で進んでいった。
このところ、石田三成がゲームや舞台で取り上げられることが多く、『江〜姫たちの戦国〜』でも存在感を増している。『関ケ原』は、歴史ファンのみならず、石田三成を考えてみたい人にも参考になるだろう。(竹内みちまろ)