筆者、山口敏太郎が京都のイベントでご一緒させていただいたとき、結城さんは口元の髭を揺らし、にこやかに語ってくれた。
京都から車で二時間、S地区という緑豊かなエリアがある。山に覆われたその里を縫うように流れる八丁川は、ツキノワグマが棲息するような秘境を水源にしている。この川の豊かな恵みからは、天然のヤマメなど川魚も豊富に育ち、それを狙った腕利きの釣り師たちが、奥深く分け入ったりしていた。
結城さんも釣りには目がなく、ヤマメを求めてよくこの川に通っており、中流域から上流へ、そして沢の水も細くなる源流まで足をの伸ばしたことがたびたびあった。無論、その川が晴れた日とどんより曇った日では、まったく違う表情を見せることも知っていたし、川を知り尽くしていたつもりであった。
あの日、あれに出逢うまでは…。
数年前には、結城さん自身がこの川沿いの八丁林道で事故を起こしたことがあり、レッカー車でけん引されたこともあった。この時、彼は地元の修理業者から、ヘアピンカーブを曲がりきれず、谷底に落下した事故車について詳しく話を聞いたという。
人里離れた山奥で、冬場は豪雪で知られた同所は、冬場の自殺者・遭難者の遺体が毎年のように回収されている。
「そこですわ、いつも死体を置いておく所は。この前も家族連れがテントを張ってたけど、何も知らんからできるんやろねぇ」
その業者はキャンプにうってつけの河原を指さしながらつぶやいた。そんな結城さんに怪異の影が忍び寄る。
ある年の事、シーズン何回目かの釣行は、八月のお盆の真っ最中であった。お盆には殺生をしないと決めていたのだが、今回はフライフィッシングを始めたばかりのT君の日程上、その日に行かざるを得なかった。
(まあいいか、T君にフライフィッシングの楽しさを教えてやろう)
結城さんはそんなことを考えていた。
その日は、絶好の釣り日和だった。はやる気持ちを抑えて、二人はクルマを林道の入り口で止めると川に分け入る。二人で交互に毛針を流しながら、ゆっくりと上流へ向かっていく。車ならわずか三十分ぐらいの距離をたっぷり一日かけて釣りを楽しんだ。釣り仲間の間で「八丁の出合い」と呼ばれる、川が二つに分岐している場所までたどり着いた頃には、とっぷりと日も落ち、毛針がほとんど見えなくなっていた。
「お、やばいなぁ、日が暮れてしまう……」
結城さんとT君は急いで竿を収めると、車を置いた場所に戻るため、林道に向かった。釣りに夢中になっていたせいか、いつのまにかだいぶ遠くまで来ており、林道を急いで歩いても車までは一時間ほどかかってしまう。
「あのポイントでライズしたヤマメは、いい形だったなぁ」
などと、今日の釣りの話に花を咲かせながら、川に沿ってくねくねと蛇行する林道を並んで歩いた。だが歩く速さよりも闇が忍び寄るほうが早く、ものの三十分もしないうちに、あたりは夜の世界に変わってしまった。会話が途絶えると、周囲には不気味さが漂う。二人は、知らず知らずのうちに早足になっていた。
と、そのとき音が聞こえた。
「ピーッ、ピリピリ……!」
ほの暗い川から、唐突に笛を吹く音が聞こえる。
(…なんやろ)
しばらく間を置いて、少しためらうかのようにまた聞こえた。
「ピー、ピリピリピリ!」
「ああ、まだ川に誰かがいる。こんなに暗いのに釣り好きなやつだなぁ」
結城さんは、川釣りの仲間が合図に使う笛の音に仲間意識を感じた。すると、三回目に聴こえてきた音は、さらに弱々しくなっている。
「ピー、ピリピリピリ」
結城さんは自分のフィッシングベストから自分の笛を取り出し、その人の仲間でもないのだが、俺たちも釣り人だよ、もう帰る途中だよ、という気持ちを込めて、ピリピリピリッ!と川の釣り人の笛に応えてやった。
闇に吸い込まれていく笛の音。その刹那、彼は何か、してはいけないことをしてしまったような気がした。うまく言えないが、その場の空気が突如変わったような気配を感じたのだ。
(あっ、なんか、まずい事をしたかなぁ……その人の仲間と勘違いされると困るな)
結城さんがそう思っていると、突如、二人の背後、つまり歩いてきた林道の奥から、とてつもなく激しい笛の音が聞こえた。
「ピーッ、ピリピリピリッ!」
(えっ、どうして、今まで下の河原から聴こえていた笛が移動したんだ。瞬時にそれも、全く音をたてずに移動するなんてことは不可能では…)
混乱しながらも彼は心を落ち着かせた。ぞくぞくする悪寒を抑えながらも必死に歩く結城さん。相棒のT君もこの異常事態を理解したらしい。ワーッと叫んで、走り出したくなりそうな気持ちを抑えてひたすら二人は歩いた。
(どういうことだろう、昼間には釣り人も、車も見かけなかった、あの笛の音の主はいったい…)
そう思った瞬間、結城さんはとうとう後ろを振り返ってしまった。だが、そこには、夜の林道があるのみであった。なんとなく胸をなでおろし、歩をさらに速めようとした時…。
「ザッ、ザッザッザッ……ザッザッザッザッ」
何か、闇の奥から足早に近づいてくる。まるで、われわれ二人に追いつこうとするかのように急いでいる。
(やばい……これは、全くしゃれにならない)
畏怖した結城さんは、T君にも伝えた。
「ぜったい、後ろを見るなよ!」
顔面蒼白でうなずくT君。恐ろしさを少しでも紛らわせるために、わざと砂利道で派手な音を立てた。小石を蹴飛ばし、大声で歌を歌い、拾った枝で木や草をバシバシと叩き、後ろの足音が聴こえないように必死になった。
すると、ようやく前方に車が見えてきた。背後の音も聞こえなくなっている。
「怖かったですね」
T君は震える声で、そう言った。
あの日、この耳で聞いた笛の音、着いてきた足音の正体は何者であったのであろうか。今もお盆になると、夜の川に笛の音が響き渡っているのではないか。闇の川べりで永遠にさまよう笛の音。そう思うとふと結城さんは悲しくなった。
「あの日、僕らは釣り人ではなくて獲物だったのかもしれませんな、笛の音で釣られたのは僕らの方だったんですよ。姿の見えぬ釣り人にね」
結城さんは、にやりと笑った。
監修:山口敏太郎









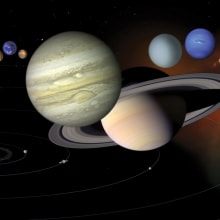





















 芸能
芸能








