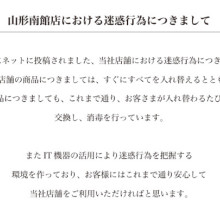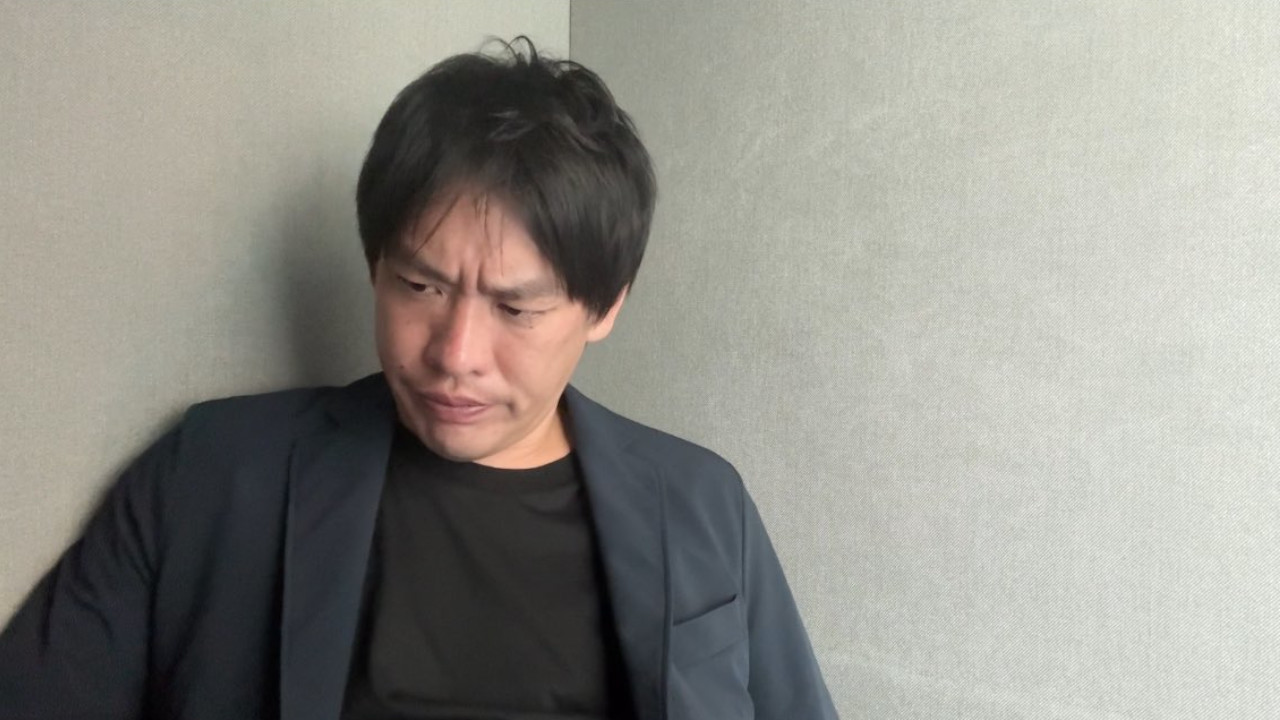「一汁一菜 凛(いちじゅういっさい りん)」を名乗る。一汁一菜とは簡素な食事のこと。はじめに温かいスープと炊いた野菜を供する「凛」の、そうして、さしあげるものは粗餐(そさん)でございますという、謙遜(けんそん)をかねたごあいさつか。板場を仕切るのは、看板どおりに目元の涼しい、凛とした女子。女子というものが、台所に立つ自分を、いつから受け入れるのか周辺に聞いてみたことがあるが、みな言葉を濁すので、いまだ判然としない。ある女子は「石器時代に男子が狩りに出ていた名残かな」と答え、逆にわたしに問うた。「じゃあ男子は、獲物を持って帰らねばならない自分を、いつから受け入れるのよ」。
カウンターには、わたしともうひとりの男客が、その端と端に陣取っている。花板はどちらにお愛想するでもなく、仕事に集中。板場の女子2名も煮炊きにいそがしい。ひまなのは客だけ。湾曲したカウンターの両端にひとりづつ座れば、いやおうなく目と目が合う。人となりは隠しようもないが、はしの上げ下げや、さかずきの運びは見られたくないものである。
さて、見知らぬ客同士は、気まずい思いをさせられたのでしょうか。これが、絶妙な位置に生ビールのサーバーがあって、目隠しの役を果たしてくれたのでセーフだったのだ。女子たちは、そこまでたくらんだにちがいないと、一人客同士は納得したのでありました。女子が、その花も実もある仕事ぶりで逸品料理をものする過程を、さかずきをかたむけながら口腹を満たすのは、石器時代から今に続く男子のしあわせでありましょう。ああ、かえりみるに、私は家族の待つ洞穴に十分な獲物を背負って帰宅したのであろうか? 吹きすぎる風よ、教えておくれ…。鯛腸(たいわた)と、松茸の土瓶蒸しをそういう。酒は燗(かん)で、黒龍の二合徳利にした。鯛腸の朱の彩りが、土瓶蒸の香り立つ秋が、男子を酔わせた。しかしがんばって、凛とした客で通した。
居酒屋で“ドストエフスキーにまさる「つまみ」はない”とロシア文学者・亀山郁夫氏がおっしゃっている。なぜなら“親しい友人との酒の語らいに適度な重さが欠かせない”からである、と。「罪と罰」などの新訳でドストエフスキーを復活させ、世間をあっといわせた氏は、この店で翻訳原稿を手渡し、校正刷りを受け取り、編集者ともども常連になった。氏の、ドストエフスキーに次ぐつまみはアジフライ。「凛」が“西荻のガード下”にあると申し上げれば、いかにもロシア文学が似合いそうな立地と思われるだろうが、あとは見てのお楽しみということにしておきましょう。予算5000円。
東京都杉並区西荻窪3-17-6