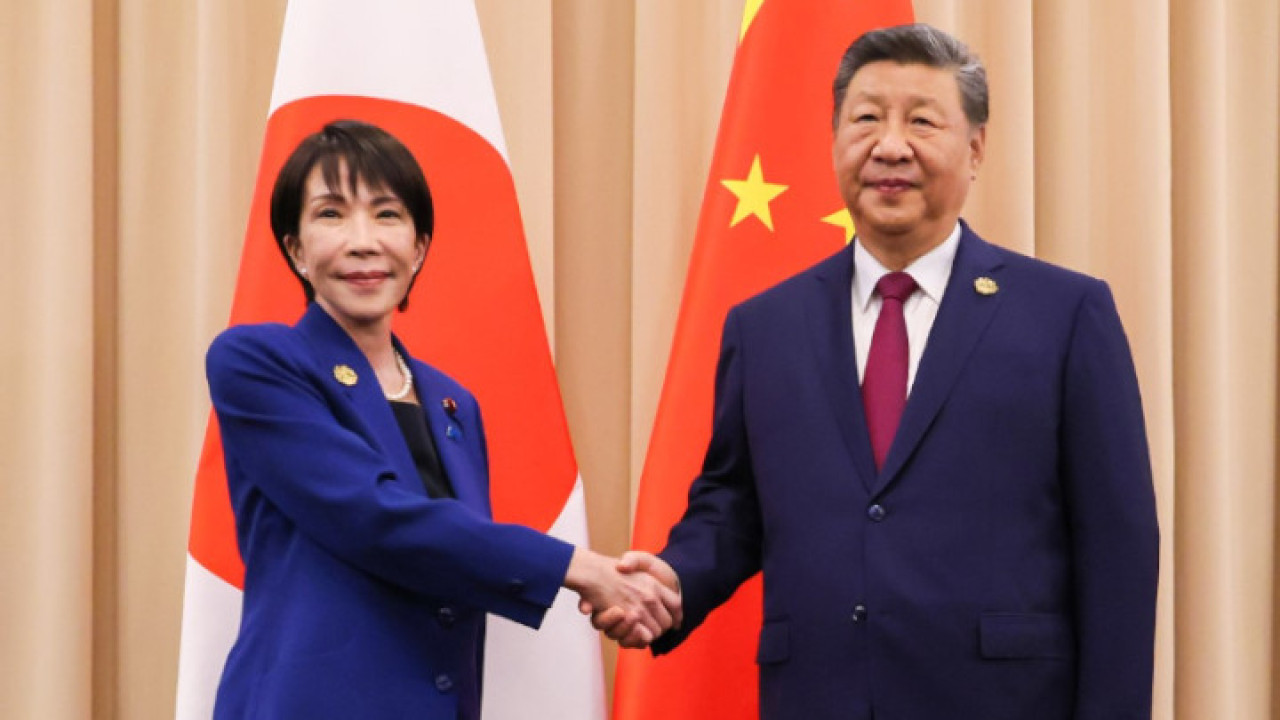タネ明かしまでに数か月の時間を費やしたり、海外まで追っかけたり。さらには、一軒家まで建ててしまったり、複数名のタレントをいっせいに引っかけたり。青木さやか、狩野英孝にいたっては、ネタばらしで巨大アリーナを貸しきって、数千人のエキストラを雇う、超大規模なドッキリを成功させている。
これらを具現化した演出家のテレビ朝日・加地倫三さんは、あの『アメトーーク』(同局)を手がけていることでも有名。そんな彼と、“イジりのプロ”田村淳が手を組むことによって、同番組のドッキリはどんどん過激に、巧妙に、ずる賢さを増していった。その原点というべき番組が、およそ19年前に存在した。『あなあきロンドンブーツ』(同局)、ロンブー初の冠番組だ。
デビューして2年がたったこのころ、淳は22歳で、田村亮は24歳。出演していた東京・銀座7丁目劇場では、人気投票トップをキープ。ニッポン放送『オールナイトニッポン』(2部)のメインパーソナリティを務め、まさに飛ぶ鳥落とす勢いのままゲットしたのが、同番組だ。若手芸人は、体を張ってナンボという時代。ロンブーも、スタッフに言われるがまま、命を削るチャレンジ企画に挑戦させられた。
まずは、炎で燃えさかるブーメランをキャッチする企画。もちろん、防火手袋は装着しているが、顔面を保護するプロテクターやマスクなどは、いっさいなし。服も普段着だ。31投目にして、ようやく亮がキャッチしたが、企画はその後、エスカレートしていった。
1か月後には、燃えたぎる野球ボールを、頭に乗せた鉄製のカゴでキャッチする内容にリニューアル。バッターは、亮。キャッチャーは、淳。野球のユニフォームにも、バット、グローブにも、防火加工はされていない。火の粉をもろにかぶる危険と背中合わせのなか、淳は見事にキャッチした。だが、その瞬間、ボールは淳の頭の上で打ち上げ花火のごとく、火花をあげた。淳はこのことを、事前に聞かされていなかった。
さらにその翌月には、「試合」という最終形態に行き着いた。四面が火で覆われるなか、火がついた竹刀でマジ剣道対決する運びになったのだ。ただならぬ緊張感が支配するなか、試合が開始。まもなくして、淳の小手に引火するというアクシデントに見舞われた。「熱っ、熱っ」と消火しようと手を振っていると、周囲を囲んでいたおよそ2,000発の爆竹が、次々と爆発した。ラストは、何も知らない亮の防着の背面に、淳が着火。すると、亮の身体から爆竹がパチパチと音をたて、まさに、身を粉にしたオチが待ち受けていた。
現在のテレ朝の十八番といえる“究極のバラエティ作り”は、このころ、ロンブーとともに形成されていったのかもしれない。淳は同番組で、何度もその犠牲になっている。
あるときは、企画内容を聞かされないままタイに連れていかされ、あのレオナルド・ディカプリオも飛んだ岩から飛び降り「ヘオナロック」に挑戦しろと、その場で言われた。高所恐怖症の淳は断ったが、スタッフも諦めない。結局、昼が夜になり、18mが3mになり、まったくおもしろくない映像で終わった。
むずかしすぎるバラエティのノウハウ、油断をすると大事故になりかねない危険性、視聴率という恐ろしすぎるリアリティなどを、身を持って知ったロンブー。この奮闘は見事に評価され、翌97年には『ぷらちなロンドンブーツ』となって生まれ変わり。深夜枠ながらも、30分、45分、55分と徐々に放映時間は長くなり、出演者の幅もグンと広がった。
彼女の浮気を疑っている男性からの依頼を受けたロンブーが、「ロンドンブーツだ!!」の発声と同時に、女性宅に侵入する名物企画『ガサ入れ』は、いつしか看板コーナーに。ここで淳の手腕は発揮され、研磨され、“ロンハー”でおおいに役立っている。テレ朝によって育まれた、ロンブーのバラエティ脳。今後も、テレビ業界にどんどん新たなケンカを仕掛けていくに違いない。
(伊藤雅奈子=毎週木曜日に掲載)