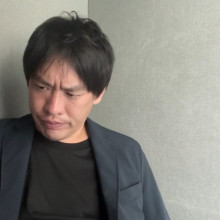農林水産省が公表している5年ごとの統計「農業就業人口」によれば、1985年に540万人いた農業人口は、’15年には約209万人と30年間で6割も減っている。また、主に農業をメインにする「基幹的農業従事者」は175万人と、初めて200万人を割り込んだ。65歳以上の高齢農業従事者の割合は63%で’85年の3倍となり、日本の農業は就労人口激減と高齢化で崖っぷちに立たされている現状が明らかだ。
その日本の農業で“革命”が起きている。ICT(情報通信技術)化、ロボット技術化、AI(人工知能)化が進み、これらを活用して、効率的な農作業を実現する新たな農業、いわゆる“スマート農業”が急ピッチで進んでいるのだ。
特に国がここ数年、最も力を入れてきたのは日本版GPS(衛星利用測位システム)の確立だ。農水省関係者が語る。
「いままで日本での位置情報はアメリカのGPS頼りでした。しかし、アメリカは全世界をカバーリングすることに力を入れているため、日本のGPS位置情報には数メートルから数十メートルの誤差がありました。国はより高度なIT社会と農業の産業育成のためにも、どうしても誤差数センチにする日本版GPS衛星を打ち上げたかったのです」
2006年からJAXA(宇宙航空研究開発機構)を中心に、省庁の垣根を超えてチャレンジしてきたのが日本版GPS衛星の打ち上げだった。’10年に初号機の打ち上げに成功し、そして、昨年までに4機目の衛星の打ち上げに成功する。
「従来、普通のトラクターの運行では超ベテランオペレーターでも10センチからの誤差が生じる。しかし、4機の衛星を有効活用すれば無人で2〜3センチ程度の誤差で種まき、耕作、田植え、刈り取りまで可能になり、人手もほぼ半分の省力化も図れます」(同)
これは世界一の精度で、新衛星打ち上げ成功で日本農業は一気に世界のスマート農業の最先端を獲得できるポジションに立った。そのため日本の大手農機メーカーもビジネスチャンスと捉え、最先端の技術を駆使したロボットトラクターの熾烈な開発競争に突入する。
日本トップの大型農機具メーカー「クボタ」は、2017年に日本版GPS衛星の成功を確信し、ロボットトラクターをいち早く開発した。
「作業員が別の有人トラクターに乗って監視しながら無人ロボットトラクターを同時に動かす。これで作業効率は1.5倍で、生産性がアップしました」(農機具販売店関係者)
クボタは、このトラクター以外にロボット式の田植え機、稲刈り機も開発中で、まもなく販売する方針だという。
クボタを追う大手農機メーカーである「ヤンマー」と「井関農機」も、ロボットトラクターを相次いで発売し、大手3社の競争は激化している。
「ロボットトラクターは、運転席に人はいるがすべて自動運転するレベル1。運転席にも誰も人はいないが近くに人がいて監視するレベル2。そして、監視がなくて完全自立走行のレベル3。今の日本のロボットトラクターはレベル2の段階。早ければ来年にはレベル3のトラクターが出現する可能性は大です」(大手農機メーカーの開発担当)
農業ロボットはトラクターだけではない。種まき、栽培作物の収穫、搬送などを行う収穫・搬送ロボットも進化している。
「キャベツやニンジン、大根などの収穫機を開発してきた北海道のオサダ農機が、大手機械メーカーや大学などと協力し、完全自動化でキャベツ収穫する機械を開発、実用化段階までこぎつけた。他にも果実収穫で、ロボット農機の導入を試みる動きもあります」(同)
農作業機のロボット化が進めば、人手不足が解消され生産性もアップするとなれば、活用しない手はない。
「ただ、ネックは初期投資額の高さです。ロボットトラクターだけでも1台1000万円を超えるので、仮に投入しても資金回収には時間がかかります。IT知識をどう身につけるかも問題であり、国としてどう根付かせていくかが問われます」(農業業界アナリスト)
不安要素はこれだけではない。
「日本の農業総産出額は1984年の11兆7000億円をピークに下がり続け、今は9兆円前後まで下がっているが、今後は、日米貿易交渉が本格化する中で米農産物の大量輸入もささやかれています」(同)
ただ、多くの専門家たちは口を揃えて「日本の農産物の世界的評価は高い」と分析している。
ロボットトラクターなど、スマート農業を積極的に取り入れることで、日本の農産物の付加価値がさらに高まることに期待したい。