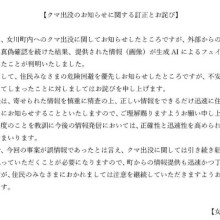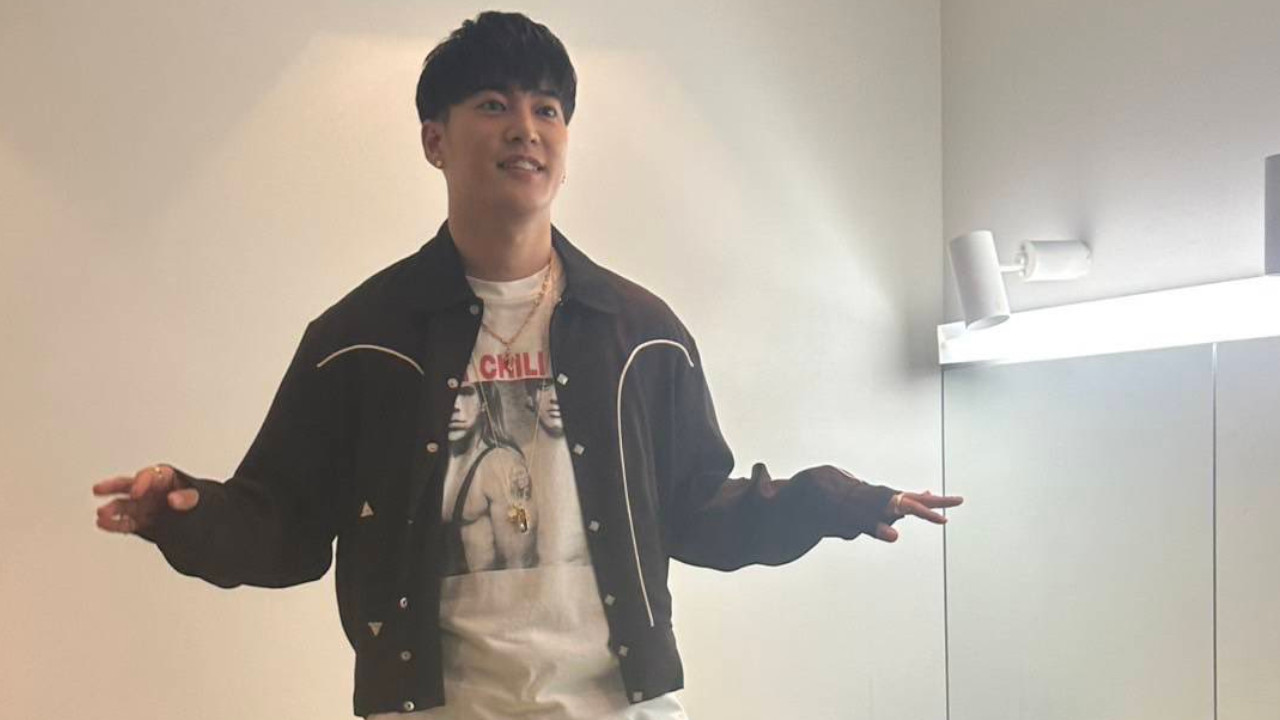明治42(1908)年4月15日、7年7カ月の年季奉公が明けた。その朝、徳次の食膳には尾頭付きの魚がつけられてあり、盃も添えられた。芳松が改まった口調で年季が明けたことを告げ、長い間の奉公を労(ねぎら)う挨拶をした。そして、きちんと仕立てた縞物の木綿羽織を徳次の前に置いてくれた。
当時は、羽織を着て初めて一人前の職人と認められた。徳次は16歳(数えで17歳)の若さで晴れて一人前の職人になった。これは当時としても極めて早いほうだった。
店の景気は相変わらずあまりよくなく、兄弟子2人もすでに店からいなくなっていた。徳次と芳松夫妻はますます親しくなり、お互いの信頼はさらに深まっていた。
これから1年間のお礼奉公には、毎月5円の月給が支払われることになっていた。2人は懸命に働いた。徳次は時には夜店も出し、夜学にも通った。少しでも収入を増やしたいと思ったが給金の額は決まっている。そこで別に方法はないかと考え、店の休みを利用していろいろな工夫を凝らした。
職人になってから最初に考案したのは印籠(いんろう)だ。印籠とは薬などを入れて腰に下げるもので、水戸黄門を思い出すかもしれない。明治の終わり頃はまだ時代劇の中の話ではなく、日常で使われていた。徳次は使い屑の地金を利用して印籠に工夫を施してみた。従来の印籠は内部に仕切りがなかったので、いくつかの仕切りを作り、何通りかの使用を可能にしたのだ。
そして知人に1個2銭で売った。評判がよくて8銭の収入になった。僅(わず)かな収入増だったが、自分の考案が商品になって売れた喜びは大きかった。同時に、頭を使い、技術を用いて工夫すれば必ず物は売れるという自信にもつながった。