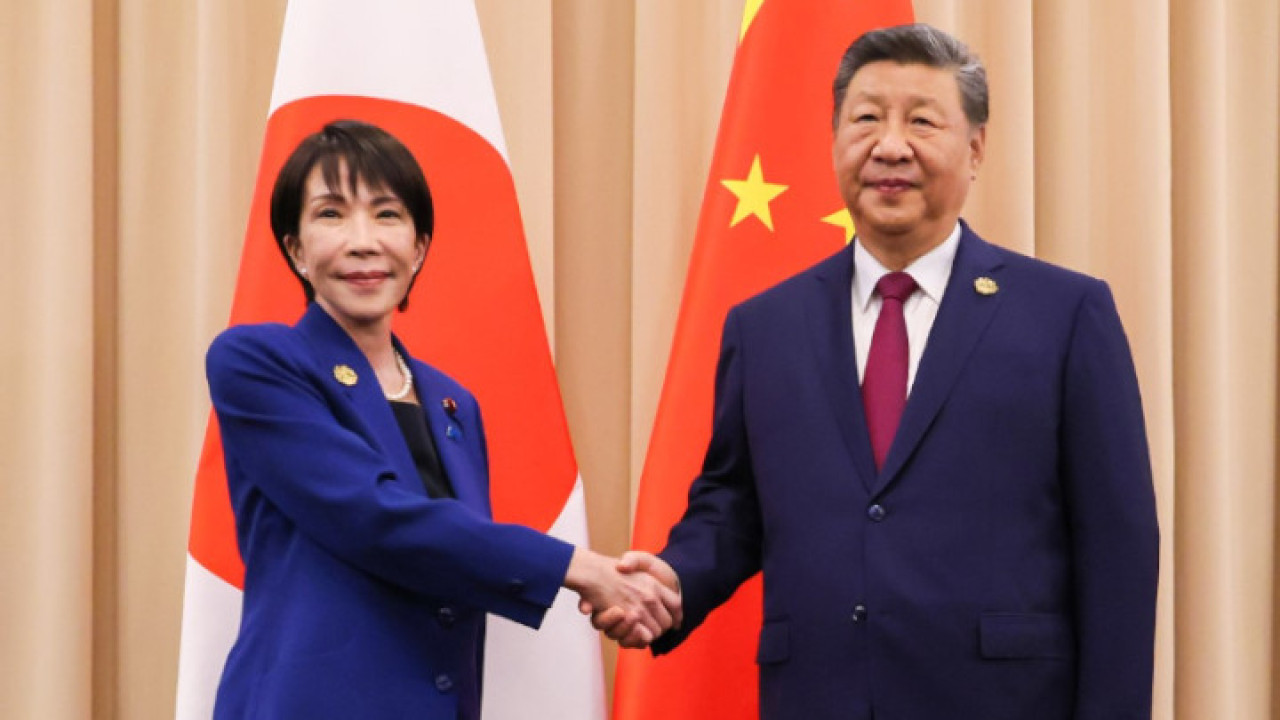『安土往還記』はまず、宣教師と共に日本に来た船乗りの男の記録という形式が特徴的だ。イタリア人の男は元将校だが、ジャングルでの戦いで苦い経験をし船乗りに身を落としていた。
男が九州に到着したのは1970年。信長は、北の浅井・朝倉連合軍、南の三好軍に挟まれていた。石山本願寺や甲斐武田の動向も予断を許さず、堺は傭兵を雇って信長に敵対姿勢を示していた。つまり、信長は苦境に陥っていたのだ。
男は宣教師と共に、キリスト教の保護を訴えるため、岐阜の信長に会いに行く。しかし、混乱する情勢のもと、堺で足止めをされていた。そこで、比叡山があるという北方に異様な炎と煙を見た。男は焼き討ちを知った人々の恐慌ぶりを目の当たりにしても事態を冷静に見つめ、むしろ、「窮地に立つ大殿のとった作戦の大胆さと決断の早さ」に称賛の念を抱いた。男は、危険を乗り越えて、なんとしても信長に会おうと決意した。
やがて、鉄砲やピストルの扱いに慣れていた男は信長の軍事顧問の立場になった。信長軍の装弾訓練や、三段構えの鉄砲隊の編成、のちに毛利水軍を壊滅させた鉄板装甲船の設計に関わる。しかし、男が戦場に出ることはなく、『安土往還記』には戦の描写はほとんどない。武田信玄の西征に際しても、徳川軍の興廃をかけた正面衝突には触れず、あとになって、なぜか突然に武田が軍を返したことを聞き知っていた。
しかし、いっぽうでは、男は信長から求められ、地球儀を回しながらヨーロッパや、インドや、アメリカ大陸の話をしていた。先入観や価値判断を加えることなく耳を傾ける信長は、日蝕の仕組みを聞いて「理にかなっている」と満足する。
男は、信長が自分たち外国人を庇護する理由を、「大殿に対して、なんらの偏見も先入主もなしに、一個の人間として対処し、話しあうことができたからではなかったか」と回想している。信長は「無神論者」だが、「大殿がフロイスやオルガンティノに好意を持ったのは、彼らが、自ら信じるもののために、身命を賭して、水煙万里の異邦にまで来て、その信念を伝えようとした熱意であり、誠実さであった」と感じ取っていた。
男は、信長の周りにいる部将たちとも交流を深めていく。羽柴秀吉や明智光秀など一部の臣下をのぞいて、「和を乞い、帰順を示す相手を斬殺しなければならぬ理由を見いだせなかった」部将たちに囲まれた信長の孤独を感じていた。秀吉と光秀が毛利との戦いに出征してからは、いっそう、信長の表情が暗く、そして、厳しくなったと記録している。
『安土往還記』は本能寺の変でクライマックスを迎える。光秀の思い詰めた顔を回想する男の興奮も最高潮に達していた。(竹内みちまろ)









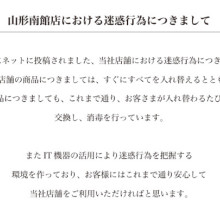





















 芸能
芸能