ところが、興味深いことに英米では亡霊軍人の帰郷譚に対して関心が日本よりもはるかに薄いようで、軍人にまつわる幽霊譚集などでも帰郷に関するものは非常に少ない。英米における軍人幽霊は、大半が基地の霊安室に出没する戦死者か、あるいは古戦場や退役軍艦などで過去の戦いを再現する将兵のどちらかである。つまり、英米における軍人幽霊の主流は地縛霊で、遺族への思いよりも軍人としての忠誠を選んだ存在として受け止められているのだろう。
また、日本において亡霊軍人の帰郷譚が関心を集めた背景には、間違いなく仏教の「盂蘭盆会」が存在しており、キリスト教圏とは文化的な土壌が全く異なっているとも言えるだろう。とはいえ、敗戦から70年もの時を隔てた今日では日本でも戦争遺族の多くが老齢化し、英米と同様の地縛霊型亡霊軍人の怪奇譚が増えてきたように思う。それも、祖国への忠誠や軍人としての義務を感じさせるものが多く、その点でも欧米化が進んでいるといえよう。
さておき、戦場や霊安室に出没する地縛霊が多い英米の亡霊軍人にも、留守宅への帰還を果たした者がいないわけではない。それは英地中海艦隊司令長官トライオン中将の亡霊で、レバノン沖の衝突事故によって殉職した際、ちょうど同じ時刻にロンドンの自宅で行われていたパーティーに姿を見せ、多くの人々を驚かせたという。
軍人幽霊譚として最もよく知られたエピソードのひとつで、かつ「王族ではない高位の軍人」が亡者となったという点でも興味深い。さらに、事故はトライオン提督が発した軍艦の性能を超える機動命令によるもので、すべての責任は彼自身にあったという点においても特異な事例で、彼が最後に発した言葉は「すべて私の誤りだ(It is all my fault)」ともされる。
トライオン提督の事故死は融通の効かない海軍という組織や、有能だが気難しくて部下とは打ち解けなかったと死後に噂されたことから、彼自身の実像とは無関係に頑迷さの象徴とされ、死の直後から舞台や映画などでパロディの対象となった。彼の幽霊譚は事故を舞台化した演劇が上演された後に広まったとの説もあり、都市伝説の成立過程を探る意味でも興味深いエピソードといえよう。
(続く)







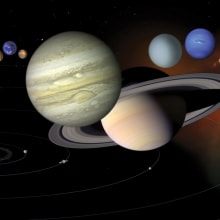



















 芸能
芸能








