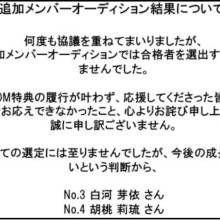浅黒い顔でどこか精悍なX君は代々続く漁師の生まれだった。
「君は大網元に生まれながら、家を継ぐことは考えてないのだね」
そう聞くと、決まってこう言い返すのだという。
「よしてくれよ、僕は元来臆病者であって、『板一枚の下は地獄』なんてものを、家業にする勇気などとてもないよ」
かくいうX君はある資格を取得して個人事務所を開いている。日頃は面倒な雑務の間にミステリー小説を読むのが好きな普通の青年であった。当然、霊など信じないたちだったのだが、ある興味深いある話をしてくれた。
X君のおじいさんの弟、つまり友人にとっての大叔父さんから聞いた話だという。
その大叔父さんは、生涯独身で子供もいなかったので、X君を本当の孫のようにかわいがってくれたそうだ。
「僕にとってもう一人のおじいさんかな」
X君が大叔父を回想する瞳は、どこか優しい。
その大叔父さんは若い頃、腕の良い漁師だったという。だが一方で、喧嘩っ早く、飲み屋で大立ち回りをやったり、朝まで飲み続けそのまま漁に行ったこともあった。まあ典型的な昔気質の職人漁師である。そんな豪傑だった大叔父さんも一度だけ心底震え上がったことがあった。
それは大叔父さんさんがまだ20代だった、昭和の初期のことだ。
その夜は、思ったほど漁で成果が上がらず大叔父さんはむなしく帰路についた。
(いかんいかん、こんな夜はとっとと帰るに限る)
すると、真っ暗な海上で人の声が聞こえてくる。
「おーい おーい」
何やら人を呼んでいるようだ。
ひょっとしたら仲間の船がトラブルに巻き込まれているのか。
「おーい、どうした、今行くぞ」
大叔父さんは声のする方に船を向けた。海は一面が暗く、どこに声の主がいるのか分からない。すると真っ暗な海に一隻の船が漂っているのが見えた。
「あの船か!!おーい、こっちだぞー」
その船からは、ただならぬ雰囲気が漂っていた。これは妖気というのがふさわしい。
(何かあったのか、妙な雰囲気だぞ)
大叔父さんがその船に近づいた。
すると
「ぷ〜ん」
と焦げた臭いが鼻をつく。
(なんだ、火災か、船舶火災か)
大叔父さんの背筋に冷たい汗が滝のように流れた。
よく見ると、船全体が焼き焦げているのが分かる。
そして、全身にやけどを負った船員が数人うごめいているのも見えた。死者なのか、生者なのかも分からない。その黒く焦げた人の形をしたものが叫んでいた。
「お〜い お〜い」
目玉だけが妙に白かったのが印象的だったそうである。
あまりの怖さに大叔父さんは港まで、わけも分からず逃げ帰った。
恐怖のあまり、大叔父さんはしばらく漁を休んだという。
その幽霊船は、それからもしばしば近海で目撃されたと伝えられている。
(山口敏太郎事務所)









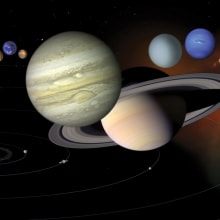




















 トレンド
トレンド