自民党の2回生議員、つまり'12年11月の総選挙で初当選した衆院議員は、とにかく「数」が多い。何しろ、人数が100人を超えている。新聞報道によると、2回生議員の内、30人弱の衆院議員が提言に賛同したとのことである。
『日本の未来を考える勉強会』の提言は、財政出動を絞ると経済が低迷し、税収も減少。財政がかえって悪化してしまうという「当たり前の話」を指摘し、PB黒字化目標の撤回と積極的な国債活用も提言。
「こども保険」(これは単なる増税だ)ではなく、教育国債の発行も明記。さらに、消費税については凍結のみならず、「5%への減税」も視野に入れるべきと提案している。
実は、筆者は『日本の未来を考える勉強会』の講師の一人を務めさせてもらった。筆者がこの会で講義をしていたまさにそのとき、議員会館の隣の会場では『財政・金融・社会保障制度に関する勉強会』が開かれていた。
『財政・金融・社会保障制度に関する勉強会』は野田毅前党税制調査会長を発起人とし、緊縮財政を推進するために財務省後見で創られた自民党の勉強会である。
発起人の野田毅議員は、
「財政破綻の足音が聞こえてきており、このまま放置するわけにはいかない。財源の裏付けがないまま、惰性に流されるのはあまりにも無責任だ」('17年5月16日 日本経済新聞「自民・野田毅氏ら、財政再建へ勉強会発足」より)
と、語った。
財政破綻の足音…。「幻聴」としか言いようがない。
無論、過去に財政破綻した国は少なくない。'12年にはギリシャ、'01年にはアルゼンチン、1998年にはロシアが財政破綻した。
財政破綻するためには、二つ、必ず満たさなければならない条件がある。奇妙な言い方に聞こえるかも知れないが、この二つの条件のいずれかが満たされなければ、その国は財政破綻をしたくてもできない。
(1)国債金利が急騰する
(2)政府の負債が自国通貨建て「ではない」こと
'12年にギリシャが財政破綻したとき、ギリシャ政府の10年物国債金利(いわゆる「長期金利」)は、一時的に40%を超えた。もちろん、年利である。
年利40%の金利など、支払えるのか? と、思われたかも知れないが、もちろん誰も支払えるなどとは思っていない。それどころか、ギリシャ政府に貸し付けたおカネが返済されない(=財政破綻)と金融市場が考えた結果、誰もギリシャ国債を購入しなくなり、国債価格が暴落した=国債金利が急騰したのである。
'98年のロシアの財政破綻の際には、長期金利が80%、短期金利は何と170%に達した。もはや、自分でも何を言っているのか分からなくなってきているが、事実である以上、仕方がない。
また、ギリシャ政府が財政破綻、つまりは返済できなかった借金は「ユーロ建て」だった。ユーロとは共通通貨であり、ギリシャの自国通貨ではない。ユーロを発行できるのは欧州中央銀行(ECB)のみだ。ギリシャ政府は、勝手に自国の中央銀行(ギリシャ中央銀行)に命じ、ユーロを発行し、ギリシャ国債を買い取らせることはできない。
アルゼンチンやロシアの政府が返済できなかったのはドル建て負債であり、ペソ建てでもルーブル建てでもなかった。
わが国の場合、政府の負債の100%が自国通貨建て、日本円建てだ。日本銀行に日本円を発行させ、国債を買い取らせることが可能な日本政府が「日本円建て負債」の返済不能に陥ることはあり得ない。
また、日本の国債金利は、急騰するどころかむしろ下がってきている。バブル期に6%を超えていた日本の長期金利は、バブル崩壊と橋本緊縮財政による経済のデフレ化を経て急落。人類の歴史上、初めて1%を下回り、'16年には0%まで割り込んでしまった。
下図の通り、日本政府が「国の借金」とやらを増やせば増やすほど、国債金利は下がっていった。理由は、バブル崩壊と橋本緊縮財政で経済がデフレ化し、民間がおカネを借りなくなってしまったためだ。
経済がデフレ化し、民間がカネを借りなくなったとはいえ、銀行は「誰か」におカネを貸し付け、金利を稼がなければならない。
だからこそ、政府に貸し付ける、つまりは国債を購入することで、銀行はおカネを運用していったのだ。デフレが長期化し、日本は政府がどれだけ「国の借金」とやらを増やしたところで、国債金利が急騰するどころか、むしろひたすら下落していった。民間の資金需要が高まらない以上、当たり前なのだ。
政府の負債が100%自国通貨建てで、さらに国債金利が世界最低水準(ちなみに、世界最低はスイス)の日本が財政破綻する可能性は、繰り返しになるが「ゼロ」なのだ。
それにもかかわらず、重鎮のはずの国会議員が、
「財政破綻の足音が聞こえてきている」
などと、自らの幻聴を堂々とメディアに語る。
日本の闇は深い。
ところで、本来は『日本の未来を考える勉強会』の提言を、政府に提出するべき役割を担うのは「野党」なのだろう。大変不幸なことに、わが国の野党には、まともな政策提言をする能力はない。
国会では、PB黒字化目標の是非について議論すら行われず、わが国の緊縮路線は継続だ。PB黒字化目標という日本経済の喉元に刺さった毒針を抜かない限り、わが国の経済成長はあり得ない。
みつはし たかあき(経済評論家・作家)
1969年、熊本県生まれ。外資系企業を経て、中小企業診断士として独立。現在、気鋭の経済評論家として、分かりやすい経済評論が人気を集めている。












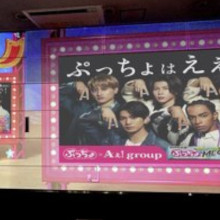










 トレンド
トレンド





