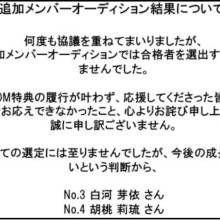『源平盛衰記』にも描かれているこのシーンは、倶利伽羅峠で源義仲が、5万の軍勢で約10万と、数で勝る平家討伐軍を打ち破った。その勝利の背景には「牛の角に松明(たいまつ)をつけて敵中に向けて放つ」という「火牛の計」という策が存在したというものだ。
『源平盛衰記』には以下のように書かれている。
「牛四五百疋取り集て、角に続松結付て、夜の深るをぞ相待ける。……時を合せよとて、四五百頭の牛の角に松明を燃して平家の陣に追入つゝ」
400〜500頭もの牛が、夜の闇を切り裂いて敵陣に突っ込む。しかも、どの牛の角にも松明が燃え盛っている…なんともダイナミックな戦闘シーンだ。
しかし残念ながらと言うべきか、当然と言うべきか、この「火牛の計」は創作である可能性が高いと言われている。
牛は臆病な動物であり、非常に目も悪い。頭に火を近づけられると動けなくなるか、混乱して暴れてしまうというのだ。400〜500頭もの牛に松明をつけるだけでも相当時間がかかるのに、牛がおびえて暴れてしまっては自陣が混乱に陥るだけ。作戦どころではなくなってしまう。
また当時、牛馬は物資運搬に用いることができる貴重な軍事資源の一つでもあった。そんな牛を大量に無駄遣いするような策を、当時の戦況でやすやすと実行できるわけがない。
現在、この「火牛の計」は、中国戦国時代に斉国の武将・田単(でんたん)が用いた「火牛の計」のエピソードを下敷きにし、後世になって追加・脚色されたものであろうと考えられている。田単の「火牛の計」は、角に剣、尾に松明をくくりつけた牛を敵陣に放つというもので、突進する牛の角の剣が敵兵を次々に刺し、尾の炎が敵陣に燃え移って大火災を起こすという、火計にアレンジを加えたものである。
この場合、牛は火を目にしてもおびえることはないし、尾の炎も策を仕掛ける直前につければ自軍に影響が出ることもない。また、文字通り尻に火がついた牛が敵陣に向けて真っすぐ走っていくというのも、考えられなくはない。もっともこの策も、牛を使いすぎると失敗する場合もある。自軍への被害の方が大きくなる可能性があるので、実際は小規模なものだったとみられている。
そもそも敵の虚をつき、攻め込むきっかけを作り、自軍に有利に戦局を動かすことができれば策としては十分に成功と言えるだろう。実際の策や計略においては、ドラマチックさやダイナミックさは二の次と考えた方がいいのかもしれない。
(山口敏太郎)









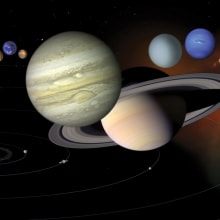





















 芸能
芸能