日本人における茶は、平安時代の初期に空海や最澄、栄西が中国から日本に伝えたとされており、茶葉が持つ薬効を期待されたものであった。その後、茶の味を飲み分けて勝敗を競う賭博的な闘茶を経て、茶の湯が生まれる。さらに、村田珠光や武野紹鴎によって侘びの世界観が構築されていき、堺の豪商の息子に生まれた千利休によって、芸術の域まで昇華された。
利休は茶聖とも呼ばれ、数多くの革新的なことを行っている。まず、水質に徹底的にこだわり、天王山の麓、山崎の地から湧き出る水を好んで用いた。また、茶道の作法を確立する上で、キリスト教の所作を参考にしたとも言われている。通常、茶道の作法では、参加者はお茶を回し飲みし、茶菓子を分けあって食する。これはキリスト教の聖餐式において、ワイン(血)を回し飲みし、パンを分けて食べる行為と似ていると言われているのだ。これは単なる偶然ではない。武者小路千家の家元の千宗守氏が日本経済新聞2010年12月16日夕刊にて述べている有力な仮説だ。
また、侘茶の概念の中に”市中の山居”という言葉がある。これは町中において孤独な空間を構築し、その空間の中で茶をたてるという茶人の真理を意味するものだが、この考え方は、キリストが荒野で修行した故事に由来するのではないか。このようなキリスト教と利休の関連に関しては、山本秀煌の『西教史談』、長富雅二の『ザベリヨと山口』などの書籍において唱えられたのが始まりである。
よくよく考えてみれば、利休の弟子や友人には蒲生氏郷や古田織部、高山右近らキリシタンが多い。極端な話、千利休の洗礼名が聖ルカ(St.Luke)であり、その音読みから千利休という名前を創ったという”とんでも仮説”さえ出てくる始末だ。作家の山田無庵は、神戸市立博物館に保管されている南蛮屏風にこそ、千利休の謎が隠されていると主張する。この屏風は利休の切腹から数か月後に描かれたものだが、構図の中に謎のキリシタン茶人が確認できる。この人物こそ、キリシタン利休だというのだ。
彼がキリシタンであったかどうかは不明だが、彼は南蛮人も多く訪れた大阪・堺の豪商の家に生まれている。南蛮人との交流のうち、キリスト教の所作や文化を知って作法に取り入れたとしても不思議はない。
天正十九(1591)年2月13日、利休は謹慎処分を受け、半月後の28日に切腹を命じられる。理由は不敬罪とも言われているがはっきりしない。もしかすると、政治の裏側を知りすぎた存在となってしまったため、処分が下ったのかも知れない。利休はこの命に逆らうことなく、切腹を受け入れている。自らの身に起きた事態を理解していたのか、運命に抗うことなく全てを受け入れるのも「侘」としたのか。彼の真意は解らない。
(山口敏太郎)









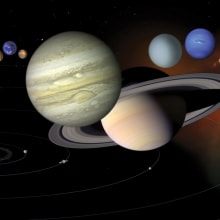





















 社会
社会








