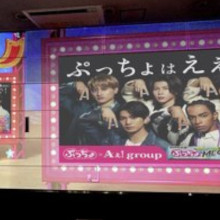実際、下地幹郎郵政民営化担当相は、閣議後の記者会見で、「新規業務を議論できるスタートラインに立った」と述べて、政府としても新規事業参入を認める意向を明らかにした。新規事業は、住宅ローンや医療保険などになりそうだ。
しかし、日本郵政の新規事業参入に関しては、民間金融機関が強く反発している。金融業界を監督する財務省は、なぜ日本郵政の新規事業参入を認めることにしたのか。
それは、明らかに株式売却収入との引き換えだろう。日本郵政株の連結純資産は11兆円ほどあるから、株式の3分の2を売却すると、国庫に7兆円程度が入ってくる勘定になる。国家財政が厳しくなる中で、財務省がついに郵便局のたたき売りに出たのだ。
日本郵政が保有する子会社のゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式売却は、日本郵政自身が判断することになっているから、当面はこれらの株式が売却されることはない。したがって、郵便事業の赤字をゆうちょとかんぽの黒字で穴埋めするという経営構造は維持できる。だから、日本郵政株を放出したとしても、すぐに問題が起きるわけではない。
しかし、長い目で見れば、新たに株主となる投資家にとっては、郵便事業がいつまでも赤字を出してよいわけがないので、郵便事業の合理化への圧力が高まることは間違いない。
ただ、一番大きな問題は、株の放出で「民間企業」となったゆうちょやかんぽが、資金運用を国債中心から、他の金融資産に移す可能性だ。
現在、ゆうちょ銀行やかんぽ生命が保有している国債は、約220兆円で、国債発行の3分の1近くにのぼる。これまで日本が膨大な国債を発行しても、順調に消化することができたのは、官営のゆうちょ銀行やかんぽ生命が、黙って国債を買い続けてきたからだ。
それだけではない。ゆうちょ銀行の貯金者やかんぽ生命の契約者は、自分が預けたお金の大部分が国債で運用されていることを知らない。だから、国際投機資本、すなわちハゲタカたちが、どんなに日本国債を暴落させようと画策しても、実現することはなかった。いくら格付け会社が日本国債の格付けを下げたところで、ゆうちょ銀行やかんぽ生命の利用者が、動揺して解約に走ることがないからだ。
今回の日本郵政株の上場は、こうした日本財政の安全装置をゆるがす第一歩になりかねない。財務省は7兆円の株式売却収入欲しさに、自ら発行する国債の最大の買い手を失ってしまうことになるのかもしれないのだ。
それだけではない。ゆうちょ銀行が住宅ローン市場に参入して、それがうまくいく保証はどこにもない。民間銀行でさえ住宅ローンで多くのこげ付きを出しているのだから、融資経験のないゆうちょ銀行に事故が起こらないはずがないのだ。
日本郵政株を売るくらいだったら、中央官庁が保有しているグラウンドとか研修所とか、先に売るべきものがたくさんあるのだ。