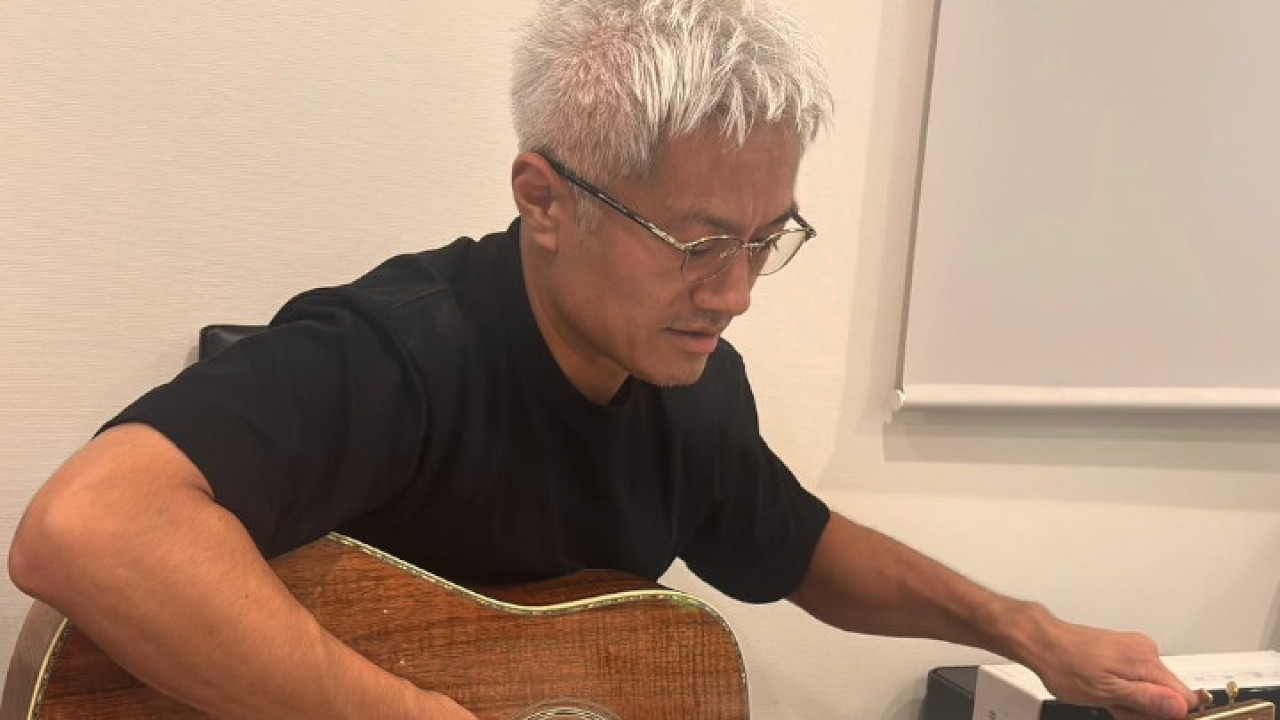東京・新橋のガード下でホッピー片手に焼き鳥を頬張っていたサラリーマン(サービス業・45歳)が語ってくれた。
「宮崎県の自治体に2万円を寄付したそうなんですが、200グラムの宮崎牛のロースステーキ肉が3枚、ドカンと送られてきて、家族3人でたらふく食べたそうです。2000円を超える寄付金の分が所得税と住民税から控除されるとかで、とても得した気分だと言ってました。それを聞いて、自分もやってみようかなと思ったんです。でも、確定申告をしないといけないとわかってね。面倒くさいなと思ってやめてしまいました」
ふるさと納税−−数年前からテレビや新聞でも、話題になっていた。でも、よくわからないし、関心もなかった。そんな人も多かったのではないだろうか。
そこで、まずはその仕組みから説明しよう。
ふるさと納税は2008年に交付された「地方税法等の一部を改正する法律」によって、全国どこの地方自治体にでも2000円以上を寄付すると、その2000円を超える金額について、一定限度額まで原則として所得税と合わせて全額が控除されるというもの。
「えっ、故郷に税金を納めるんじゃないの」と思う人がいるかもしれない。また、納税という言葉に気後れするという人もいるだろう。
実は、ふるさと納税とはいっても、故郷に税金を納めるわけではない。実際には、ある自治体に金を寄付するということ。その寄付金額が、自分の所得税や住民税から控除されるのだ。当初はふるさと寄付金ともいわれた。
寄付行為だから、寄付をする先は自分の出身地でなくてもよい。応援しているサッカーチームがある街、好きな農水産物がある市町村や温泉町、災害に遭った自治体、どこでも可能だ。
つまり、寄付に対する税制上の控除という制度を、地方自治体への寄付という仕組みにまとめたのが『ふるさと納税』ということ。従って、確定申告をすることで税金が安くなるのだ。
欧米では普通に行われている寄付だが、日本ではあまりなじみがなかった。2011年に起きた東日本大震災を機に被災地への寄付が爆発的に増えたが、それでも習慣化しているとは言い難い。困っている人たちを助けたいと思って寄付をした人が大多数で、税の控除を受けようとまでする人は少なかったのではないだろうか。
当初、ふるさと納税の寄付金総額は、総務省発表の統計によれば73億円弱。交付翌年の'09年から'10年には60億円台半ばと、あまり活用されているとも思われなかったが、大震災が起きた'11年には10倍ほどの650億円弱に増加した。'12年はおよそ130億円にとどまったものの、当初に比べれば増加傾向で推移しているといえるだろう。