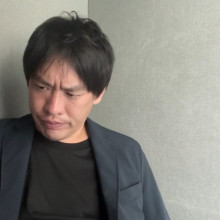その人物の名は曳田照治。田中角栄が昭和22(1947)年4月の総選挙において、2回目のチャレンジで当選を果たした直後から、正式に「衆議院議員・田中角栄秘書」となり、田中が郵政大臣となって以降は秘書官を務め、約10年間にわたり田中を支え続けた。性格は陽気、度胸もあり、秘書になって間もなくは「政治的感覚は田中より上。なかなかの人物」というのが、永田町および霞ケ関官庁街での評判だった。
冒頭のエピソードは、田中の地元〈新潟3区〉の小学校の改修予算計上への陳情だったが、書類が下のほうに積まれていたのでは時間がかかるため、素知らぬ顔で順番を入れ替えたのである。この手のことは朝メシ前、田中はこの曳田の一挙手一投足を見習ったかたちで、政治というものの表裏を学んでいった。その意味では、陣笠の頃の田中という政治家を語るうえで、曳田の存在は欠かせないものになっている。
曳田は田中より1歳上、終戦から間もなく生きるあてのない中で、戦友の紹介により東京・飯田橋に本社を構える「田中土建工業」に就職した。田中との出会いである。ところが、間を置かず社長の田中が総選挙への出馬を決めたことにより、社員の曳田も新潟での選挙運動に駆り出されたということだった。
かつて、筆者は名にし負う田中の新潟での後援組織「越山会」の古老幹部から、次のような話を聞いたことがある。
「田中は1回目落選、2回目の出馬で当選したが、その頃に曳田秘書の知恵がなかったら、今の田中があったかどうか。地元にとって田中は無名の新人と言ってよく、やがては新潟で田中の絶対的基盤となった魚沼地方の票を掘り起こしたのも曳田だった。当時の選挙は“重立ち”、すなわち地元のボスが票を押さえていたが、曳田は度胸のよさと口の達者さで、これを突破していった。
また、1回目の選挙では、田中の演説はドモるうえに中身もなかったが、2回目ではこれに絶望した曳田が、『東京へも日帰りができる、冬でも車が走れる。そんな鉄道と道路を整備し、展望のある新潟をつくらねばならない』などと、演説の中身を一新させた。のちに有名になった『三国峠を切り崩せば、越後新潟に豪雪は降らなくなる。切り崩した土は日本海へ持って行き、佐渡と陸の間に埋めて陸続きにしたらいい』との“大演説”も、じつは曳田のアドバイス、差しガネだったんだ。まさに、曳田あっての田中だった」
★精鋭結集の求心力は田中にあり
筆者は50年超の永田町取材を経験してきたが、多くの実力者を見る中で、田中くらい人の集まった人物を見たことがなかった。とくに、秘書団である。この秘書団も、いくつかのグループとなっていた。
一つは、「二人三脚」で代議士になって以来、長く政治行動を共にしてきた佐藤昭子や、のちに政治評論家に転じた早坂茂三ら、田中の個人事務所の秘書団。
二つは、東京・目白の田中邸に詰めていた、山田泰司ら「江戸家老」と呼ばれた秘書、書生団。
三つが、国会議員の中でも最強の後援組織とされた「越山会」に、にらみを利かせ続けた、本間幸一ら「国家老」と呼ばれた新潟の秘書団となる。
そして四つが、141人を誇った田中派木曜クラブのピーク時には、所属各議員の公設、私設秘書合わせてじつに400人超が、“鉄の結束”を見せつけた「木曜クラブ秘書会」ということになる。この秘書会は、誰言うこともなく、一糸乱れぬ戦いぶりから「秘書軍団」の異名があった。
これらの四つのグループが、一朝事あった場合は互いに連動し、選挙ならとてつもない票を田中にもたらせた。まさに「最強」の名にふさわしい秘書たちの集まりだったのである。
それにしても、田中のもとには、先の曳田照治をはじめ、仕事にたけた才覚の持ち主が多く集まった。優秀な部下は、優秀な上司のもとにしか集まらない。ビジネス社会の組織でも、ダメな上司には一度は集まった優秀な部下も、やがては去っていくのと同様である。部下の敬意を集めることができる上司だけが、優秀な部下に支えられるのは、どの社会、組織でも同じということである。
例えば、次のような精鋭が集まった要因は、田中自身の求心力そのものにあったということだった。
佐藤昭子。手紙を書かせたら天下一品の達筆で、頭の回転も男まさりだった。田中が、「金庫」のカギを預けていたのもうなずける。
早坂茂三と麓邦明。前者は東京タイムズ、後者は共同通信社の記者から、田中の秘書となった。早坂は弁と筆が立つ熱情家、麓は冷静、沈着な政策通として知られていた。
山田泰司。目白の田中邸に常駐し、田中の陳情処理を補佐しつつ、毎年夏、2週間をかけて〈新潟3区〉各地の約300に細分化された「越山会」を回り、選挙区内での陳情、要望を聞いて回るのが常だった。そして、越山会それぞれが前回の選挙で田中の票をどれだけ出したかで、この陳情、要望を厳しく差配した。これは「越山会査定」と呼ばれ、各地越山会の幹部たちは陳情の実現のために、選挙でいかに田中票を出すか、この“信賞必罰主義”に頭を抱えたものであった。
そのうえで、選挙となると水も漏らさぬ態勢で全力投球したのが、「国家老」の本間幸一だった。「選挙戦に入ったら、本間はフトンで寝たことがない」との伝説を残している。
(本文中敬称略/この項つづく)
***********************************************
【著者】=早大卒。永田町取材49年のベテラン政治評論家。抜群の政局・選挙分析で定評がある。著書に『愛蔵版 角栄一代』(セブン&アイ出版)、『高度経済成長に挑んだ男たち』(ビジネス社)、『21世紀リーダー候補の真贋』(読売新聞社)など多数。