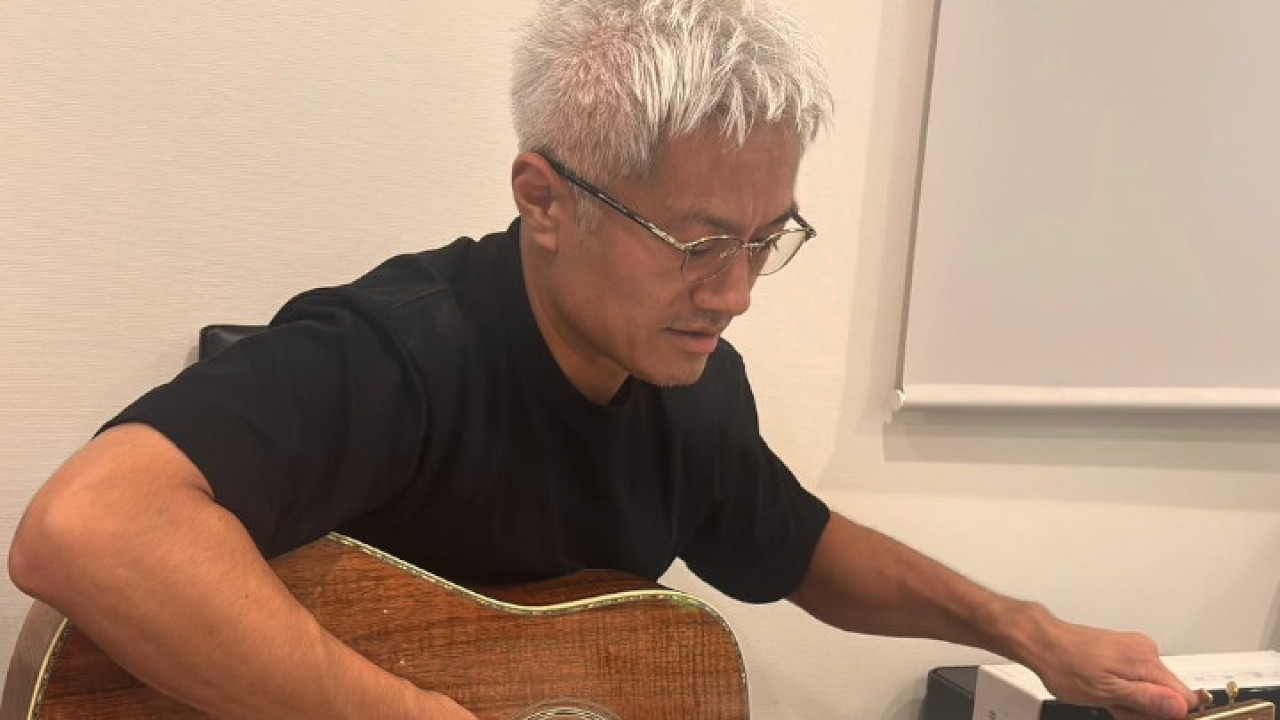その選挙に吉田は実父・竹内綱の選挙区である〈高知1区〉から出馬、当選を果たした。だが、所属した自由党は議席が伸びず、社会党の片山哲が新憲法下で初の総理のイスに就くことになる。
しかし、その片山内閣は短命で終わり、本来ならば「憲政の常道」として、第2党だった吉田の自由党へ政権が譲られるべきだったが、民主党の芦田均に政権が回った。その芦田内閣は、閣僚も含めて政財官の各界から、じつに64名もの逮捕者を出した贈収賄事件「昭電疑獄」に見舞われて退陣。政権はまた自由党と民主党が合同した、民主自由党の総裁だった吉田に回ってきたのだった。まさに、「政権たらい回し」の戦後のドサクサ政治と言えたのである。
ところが、この芦田から吉田への政権バトンタッチにGHQ(連合国軍総司令部)が「待った」をかけた。GHQは「吉田は保守反動であり、戦後日本の民主化にはふさわしくない」として、吉田と同じ民自党の幹事長だった山崎猛に肩入れをしてきたのである。
これには、民自党内の反吉田グループがGHQと組んだ“謀略説”もあったが、党の総務会でこの「山崎首班」に待ったをかけたのが田中角栄だったのである。当時からダミ声だった田中は、このとき顔を真っ赤にしてテーブルを叩き、こうブチ上げたのだった。
「いかにGHQと言えども、その国の総理大臣を誰にする、彼にするというのは、内政干渉そのものと言わねばならない! 過去、こんな例があっただろうかッ。だいたいですナ、本当にGHQがそんなことを言ってくるのかどうかだ。GHQが吉田首班でいかんと言うなら、わが民自党は堂々と下野すべしでありますッ。私は、断固として闘う!」
この田中のブチ上げに、総務の間からは「黙れッ、チョビひげ野郎!」「若僧に何が分かるのかッ」とヤジ、罵声が相次いだ。一方で、「そうだッ、田中の言う通り。断固、GHQと闘うべし!」との声も出た。こうした議論の中で、やがて「山崎首班」を支持する声は少数派となり、当の吉田はこの流れにしごくご満悦だったのだ。
結果、昭和23年10月19日、第2次吉田内閣が発足した。組閣が終わると、吉田は政務次官(現在の副大臣、政務官にあたる)人事を任せてある側近の副総理・林譲治に、次のように厳命したのだった。
「あのチョビひげの若いのを、どこかの政務次官にはめ込むように」
この「ワンマン」吉田の“鶴の一声”で、時に30歳の田中は1年生代議士にして、法務政務次官として抜擢された。この“ご褒美”こそ、田中が「吉田学校」入校を許された瞬間でもあった。一方で、田中土建工業の経営で大儲けしていた田中の終生の“得意ワザ”が出たのも、早やこの頃だったようだ。次のような証言が残っている。
「政務次官への着任と前後して、田中は『お中元』と称するカネを周囲の議員に配っている。これも、新人議員としては異例のことで、田中はその後も『指導料』など、いろいろな名目でカネを配るが、これは1年生議員のときからの習慣だった」(『田中角栄の青春』栗原直樹・青志社)
こうした“手法”は、田中にとっては将来の天下取りをにらんだ布石にほかならなかった。すなわち、そうしたカネを受け取る、受け取らないといった中で、自分の仲間であるか否かの選別をしていたということである。30歳にして見上げた男は、すでに将来図を描いていたと言える。
★「大磯」に出入り自由の田中
しかし、人生まさに好事魔多し。田中は法務政務次官に就任して1カ月もたたぬうち、「炭管法案」に絡む贈収賄事件で逮捕、身柄を小菅の東京拘置所に収監されるという憂き目にあった。昭和23年12月15日の東京高検による逮捕であった。
「炭管法案」とは元をただせば、社会党の片山首相が社会主義政策の具現として、英国の労働党に学んで石炭産業の国有化を目指し、国会に提出した臨時石炭鉱業管理法案を指す。これに田中は猛烈に反対し、委員会審議では「石炭を国家管理にすることは、黒い石炭を赤くすることだッ」と、激しく追及したものであった。
しかし、一方で田中に、「炭管法案」に反対する炭鉱業者から100万円の小切手が渡され、田中はそのカネを法案反対の政党関係者に配ったという疑惑が表面化した。結局、これが災いして逮捕、起訴ということになった。裁判結果は、のちに一審有罪だったが、二審無罪となる。
その田中の収監のさなか、現職代議士の逮捕により、吉田首相は衆院の解散・総選挙を迫られた。裁判でも一貫してシロを主張していた田中は、ここで敢然と総選挙への「獄中立候補」の声を挙げ、保釈を待って時すでに10日しか残されていない選挙戦に駆け回ったのだった。
翌24年1月23日の開票日、田中は〈新潟3区〉で辛くも2位、2回目の当選を果たした。吉田首相にとっても、目をかけた「チョビひげ野郎」ではあったが、田中の逮捕により野党から内閣不信任案を提出され、総選挙を余儀なくされるなど、えらい飛ばっちりも受けたということでもあった。
その後、田中は「吉田学校」優等生の池田勇人、佐藤栄作(ともに、のちに総理大臣)と親交を結び、やがてこれをバネにした格好で自民党の「保守本流」を自負、天下取りを目指すに至るのである。
吉田は政界引退後、神奈川県大磯の邸宅に引きこもり、人の出入りを選別していたが、田中は自由に出入りさせていた。弟子でもある池田勇人と佐藤栄作が自民党総裁のイスを争ったときなどは、田中を通じて情勢を掌握していた。
こうした吉田の田中に対する深い“信用”が、のちに「保守本流」として、田中のもとに自民党の精鋭たちが多く集まった原因にもなっている。
吉田との出会いあってこその、田中の政治家人生だったと言うことである。
(本文中敬称略/次号は「最強の秘書軍団」)
***********************************************
【著者】=早大卒。永田町取材49年のベテラン政治評論家。抜群の政局・選挙分析で定評がある。著書に『愛蔵版 角栄一代』(セブン&アイ出版)、『高度経済成長に挑んだ男たち』(ビジネス社)、『21世紀リーダー候補の真贋』(読売新聞社)など多数。