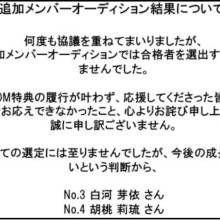筋肉隆々のたくましい腕、日焼けした顔は、まさしくベテランドライバーの風貌だ。
「まあ、そうさな〜。車の運転なら、誰にも負けねえよ」
とうそぶくSさんは、若い運転手に交じり、東京〜大阪間を3日に1回往復する生活を続ける。運転席はゴージャスな飾りや、各地で買った土産物で埋め尽くされている。
「まあ、俺はまだまだ現役だし、プロだもんな〜。最近車、転がし始めた若いもんにはまだ負けるわけにはいかねえな〜」
自分の腕だけで生きてきた職人の自信は、Sさんを現実主義者にしていた。当然、幽霊は一切信じない。怪談話を口にする人間のことは馬鹿にしていた。同時に、自動車という「科学の結晶」に勝るものなどこの世の中にはないと思っていたのだ。
「ばかばかしいと思ってさ。そりゃそうさ、俺は幽霊なんかいないと思ってたんだし…あんなものを見るまではさ」
Sさんは、はにかむように鼻の頭を掻くと、奇妙な話を語り始めた。
まだ、世の中が「昭和」と言われていた頃の出来事である。
その日、Sさんは東京の某倉庫を、真夜中に出発した。
「ちくしょー、俺だけ何でこんなに積み込みに時間がかかるんだい。これじゃ間に合わねえよ。どうしてくれるんだ」
バックミラーで、シャッターを卸すフォークマンを見ながら、Sさんは荒々しくハンドルをさばいた。その日は運の悪いことに、Sさんが積み込む荷物の出荷に時間がかかり、いつもと比べて1時間遅い出発となっていたのだ。
(このままじゃ、明日の朝に間に合わない。不眠不休で走るか)
Sさんはかなり焦っていた。大阪に着くべき時間は朝5時である。このままでは間に合わない。Sさんの車が到着しないと建築現場の工事が進まないのだ。まして職人たちは、遅れがちな工事の進行を取り戻すために、早出して現場に詰める予定だと聞いた。
(何とか間に合わせないと)
職人気質のSさんは、缶コーヒーをがぶ飲みしながら、車を走らせた。真夜中の高速道路を、車を斜めにしながらハイスピードで駆け抜けていく
当然、車のスピードはぐんぐん上がり、大型トラックとは思えない素早さで走り抜けた。先行車をどんどん追い抜いていくうちに、Sさんの心に慢心が芽生えた。
(ふふっ、やっぱりな。おれはまだまだ誰にも負けない)
負けず嫌いのSさんは、いつしか得意になってハンドルをさばき始めていた。
そのとき、Sさんはある車に気付いた。
(あの車は、さっきから何度抜いても抜き返してくるようだ。全く生意気な奴だ。ちょっといたぶってやろうか!)
Sさんがよく観察すると、自分と同じ車種であった。しかも、塗装に社名、そしてボデイにいたずらで貼ったステッカーも一緒という始末。
(誰なんだ、誰が運転してるんだ。おっ、おかしいぞ。あんな車、見たことないぞ。うちの会社にもう一台あったのか)
不思議に思いながらSさんは、その車を追い越した。しかし、また5分もたたないうちに追い越されてしまう。そんな応酬を何度か繰り返した。
(この野郎、あくまで俺と競争するつもりだな)
再び熱くなったSさんは、追い抜きざまに相手のナンバーを確認した。
(なんだって。ありゃ、俺のナンバーと一緒じゃねえか、そっ、、そんな、ばっ、ばかな。偽造ナンバーか?)
Sさんは、混乱し、いつしかハンドルを持つ手は汗ばんでいた。
(運転手の顔を見てやれ。ええっ、誰なんだ)
相手の車がSさんの隣に並んだすきに、Sさんは相手のドライバーの顔を確認した。
(……俺だ、俺がもうひとりいる)
何とその顔はSさんの顔だったのである。
しかも、頭部がざっくりと割れ、血と脳みそがあふれ出している。
唖然とするSさんを後目に、そのもう一台のトラックとSさんの「分身」はゆっくりと半透明になり、夜の闇に消えていった。
(あれは、事故で死ぬ自分への警告だったのだろうか)
Sさんはそう反省した。その日以来Sさんは、安全運転を第一に心がけるドライバーに変わった。
(監修:山口敏太郎事務所)









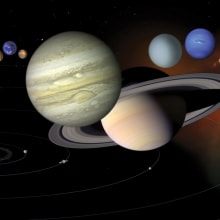





















 トレンド
トレンド