「どないした ばあちゃん? 」
「毎回毎回、時計がなる度に小人がいっぱい降りてきて輪になって踊るんよ。たまらんわ」
祖母はヒステリックになりながら、筆者に訴えたことがあった。だが、筆者には小人の姿は見えない。
「ええ? 小人なんかおらんよ、ばあちゃん」
「そこにおるやん、そこに、ほら、そこに」
祖母は誰もいない居間を指差した。
「どこにおるの?」
「ほら、気味の悪い小人の輪っかが、見えるやろ」
彼女の目には、小人たちが輪になって踊っていたのであろうか。祖母のこの奇妙な行動を見たとき、筆者は複雑な気持ちになった。かつて、まったく妖怪や魔物を恐れなかった祖母。
その祖母が、小さな小人たちの”見えないダンス”におびえているのである。
「小人の踊りが怖い! 小人の踊りが怖い!」
祖母は絶叫した。
「ばあちゃん、大丈夫か」
筆者は衝撃の展開に色をなくした。異界から生まれ出た人間は、いつか魔物に擦り寄られ、異界に帰っていくのだろうか。祖母の脳裏では、間違いなく小人が輪になって踊っているのであろう。永遠に続く“見えないダンス”とは、いったい何なのだろうか。
ここで筆者は、ある質問をした。
「どこが怖いの? 小人が踊ってるだけやろ?」
祖母は、虚ろな瞳を輝かせている。
「小人が呼びかけるんよ」
「呼びかけるって、どういうふうに」
この質問に、祖母は語尾を震わせて答えた。
「この輪の中に入れ、輪の中に入れって、小人が話しかけるんよ」
私は驚きのあまり、しばし言葉を失った…。
気を取り直してこう聞いた。
「輪の中に入れとは、どういうことなの? ばあちゃん」
すると祖母は、ひと呼吸おいてこう言った。
「あの輪を抜けると、抜けると…」
「抜けるどうなるの?」
すると祖母は恐ろしく低い声でつぶやいた。
「あの世の世界なんよ」
この言葉を聞いて、筆者は固まった。
働きづめの祖母の心の隙間に、小人や魔物が棲みついたのだろうか。筆者は、丸くなって小人のダンスに震える祖母の姿を見て、悲しい気分になった。
祖母が死去したのは、それからちょうど一年後のことであった。やはり、祖母は小人の輪をくぐってしまったのだろうか。









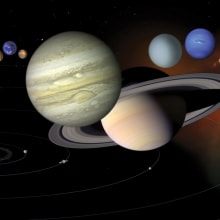





















 芸能
芸能








