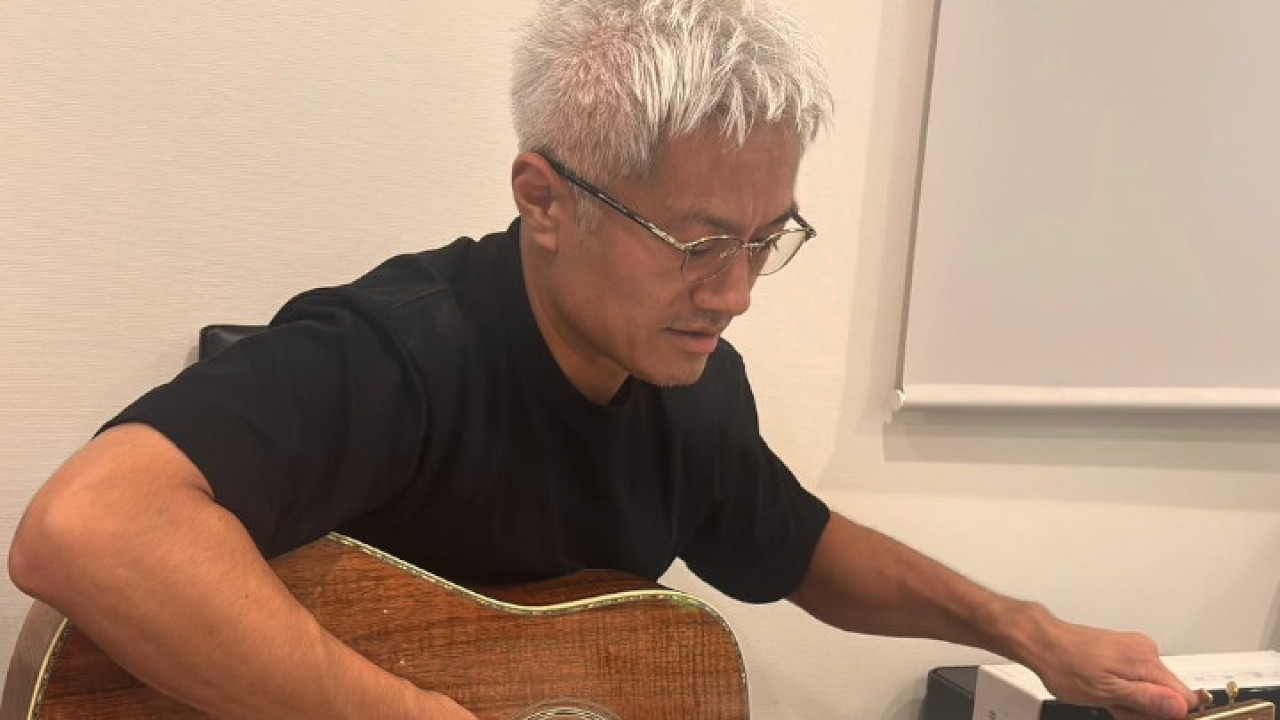思い込みの強いタイプ、時に世論の反発を買っての強気一辺倒の政権運営を続ける安倍晋三首相を支える屋台骨であり、“軍師”なのが内閣のスポークスマンこと菅義偉官房長官である。手法は硬軟自在ながら、子細に見ると表題の言葉にあるように「硬七分・軟三分」がうかがえる。
事に当たっては強気で勝負するタイプといってよい。「国民から数をもらっているからには」とは「大衆、あるいは多数の支持がある以上は」と置き替えられるため、企業など一般社会組織での「強気のリーダーシップ」の在り方を示唆しているともいえる。
「強気」の好例は、いくつかある。最たるものが、平成24年9月の自民党総裁選だった。すでにその5年前に病気を理由に政権を投げ出し、すっかり自信を失っていた安倍の復活劇に乗り出したのである。安倍は出馬には後ろ向きだったが、菅は「100%勝たせる自信はないが、もう一度、国民に政治家安倍晋三を見てもらいましょう」と粘り強く説得、出馬に踏み切らせた。
結果は、第1回投票では地方票で対抗馬の石破茂(現・地方創生担当相)に大差を付けられて2位。国会議員票だけでの2人の決選投票ではこれをひっくり返し、見事、石破を下して勝利し、安倍に第2次内閣の復活を実現させたのであった。「菅は投票前、石破には派閥の後押しが弱いことを見抜き、決選投票に持ち込めば勝てると読み切っていた。石破とは勝負勘の差があった」と、当時の総裁選取材の政治部記者の証言がある。
その第2次安倍内閣で官房長官就任以降、今日まで菅の「強気」は一貫して続いている。アルジェリア人質事件では反対論もある中、情報を官邸に集約して邦人輸送のための政府専用機派遣を果敢に主導したのを手始めに、TPP(環太平洋経済連携協定)交渉への参加、消費税率8%据え置き、特定秘密保護法成立、中央省庁の幹部人事を官邸主導でやる内閣人事局創設、集団的自衛権行使容認への決断等々、時に世論、党内外からの逆風を押さえ込んで安倍の政権運営をレールに乗せ続けた。
こうした菅の勝負勘、読みの的確さはどこから来たのか。これには、二つある。一つは、秋田の農家の長男で高校卒業後上京、町工場に住み込み、苦学して大学を卒業したあと代議士秘書、横浜市議という“下積み”経験があったこと。もう一つは、「政治の師」を自民党幹事長や官房長官を務めた実力者の梶山静六(注・この連載でも登場済み)に仰いだことであった。菅に気脈のあるベテラン政治部記者が、次のように言っている。
「命令されたことは倒れてもやる。ウソをつかない。陰、日向がない。一方で、おかしいと思ったら上司、先輩にもハッキリ物を言う。『意志あるところ道あり』が秘書、市議時代からの一貫した人生訓なんです。さらに、ガラス細工をいじるような精密さと豪胆な決断力、官僚の動きを重視した党内外への目配りで腕力を示した梶山の薫陶が大きかった。その上で、“下積み”経験の長さから、人と社会の本質を見抜く目を自然に養ってきている。世情を見る目の確かさは、スムーズな人生を送ってきた者ではどこか物足りない。多くの要素が合わさって“菅流”の勝負勘、読みの的確さにつながっている」
一方で、こうした「叩き上げ人生」の菅は、これまで政治家となってからは落選、失政など大きな窮地に立ったことがない。官房長官として最も要求される絶対的な危機管理能力を問われたこともない。戦争突入へ危機一髪だった大韓航空機撃墜事件を仕切った中曽根内閣の後藤田正晴元官房長官のような真価が問われる場面にもまだ直面していない。
また、強気が目立つ一方で「本質はリベラル、穏健派」(前出・ベテラン政治部記者)だけに、「主君」安倍との“間合い”をどう取り続けられるのかが注目される。
菅の強気を後押しするかのような男がいた。同様に「叩き上げ」だった田中角栄元首相だ。彼のこんな言葉がダブるのである。
「内閣はできたときが一番、力、勢いがある。モタモタしているとあちこちから必ず異論が出て、結局、何もできなかったということになりかねない。そこがトップリーダーの大事なところだ」
=敬称略=
■菅義偉
現内閣官房長官。沖縄基地負担軽減担当大臣を兼務。自民党幹事長代行、総務大臣(第7代)、内閣府特命担当大臣(地方分権改革)、郵政民営化担当大臣、横浜市会議員(2期)等を歴任。
小林吉弥(こばやしきちや)
永田町取材歴46年のベテラン政治評論家。この間、佐藤栄作内閣以降の大物議員に多数接触する一方、抜群の政局・選挙分析で定評がある。著書多数。