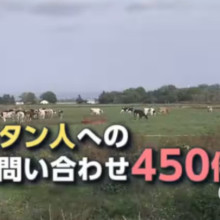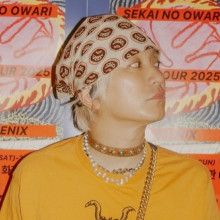'00年にホイス・グレイシーを激闘の末に破ると、ヘンゾ、ハイアンにも勝利。前年末のホイラーも合わせて、格闘技界の黒船と畏怖されたグレイシー一族を4タテ完勝してみせた。桜庭は、これを機に日本格闘界のエースの座に上り詰める。
著書はベストセラーとなり、39Tシャツなどグッズもバカ売れ。その人気は格闘技界にとどまらず、テレビCMにも多数出演するまでに至った。
「桜庭の凄さはただ勝ちにこだわるのではなく、プロとしてエンターテインメントを意識したところ。リング上で対峙する相手選手の動きと同時に、観客席の反応までも視線に入れていた」(格闘技ライター)
ガード状態の相手に上から振り下ろす“モンゴリアンチョップ”や、両脚をつかんでグラウンド上を引きずり回す“炎のコマ”などは、格闘技の理論からすれば明らかに余計な動きだ。
プロボクサーも相手を挑発する動きを見せることはあるが、そのほとんどが相手と距離を置いた、いわば安全地帯でのこと。接近戦の多い総合格闘技において、余計な動きのリスクは格段に高くなる。
「モンゴリアンチョップなどは片手で放つ通常のパンチと異なり、相手との距離が詰まる上にガードもできない。そのせいでバッティングを食らい、優勢な試合を落とした('03年のPRIDE25におけるニーノ・“エルビス”・シェンブリ戦)ことも実際にありました」(同)
それでもあえてやるのはなぜか。余裕を見せて相手を心理的に揺さぶるため、相手の予測しない攻めで混乱させるためなど、もっともらしい理屈もいわれるが、やはり観客を意識してのことが大きかっただろう。
相手の腕を抱え込んで、観客席を見渡してからニヤリ笑みを浮かべる。これぞ桜庭の真骨頂であり、多くのファンが記憶するその雄姿だ。
「グレイシー兄弟を次々に撃破して、残るは打倒ヒクソン・グレイシーのみ、というのがファンの期待であり、PRIDEも実現に向けて動いていました」(業界関係者)
'01年3月25日、PRIDE13のメーンイベントで行われた桜庭和志vsヴァンダレイ・シウバは、ヒクソン戦という来たるべき大一番までの谷間の試合…そのような見方がほとんどであり、戦前の予想でも桜庭有利の声が圧倒的だった。
「シウバはこの前の試合で、リングスKOKトーナメント覇者のダン・ヘンダーソンを破るなど、戦績からも決して侮れる相手ではなかった。しかし、当時はそれを上回るだけの桜庭への信頼感があったのです」(前出・格闘技ライター)
また、この大会からはグラウンド状態での相手の頭部への蹴りが解禁されたことも、桜庭にとって不利に働いた。
フジテレビでの中継放送が本格化するに合わせ、一般ファンにとっては退屈なグラウンドでの膠着を減らすためのルール改定であったが、これがエース桜庭の敗因となるとは、関係者も予想していなかっただろう。
試合開始から積極的に打ち合いに出た桜庭だったが、打撃ではムエタイをベースとしたシウバに一日の長がある。右フックを顔面に食らって崩れた桜庭の頭部に、シウバは容赦なくヒザを落としていく。
それでも体を丸めて、グラウンドを這うように脚を取りに行く桜庭だったが、シウバは距離をとって、やはり頭部を狙ってサッカーボールキックを連打する。
さらに頭部へのヒザの追撃で、これに耐えかねた桜庭が顔を上げたところに、フルスイングのシウバの右足甲が直撃し、レフェリーストップが告げられた。試合時間わずか1分38秒の惨劇に、満員の観客も息を飲むしかなかった。
それまで総合では、柔術やレスリングベースの選手が活躍していたことから、寝技有利が定説とされてきた。桜庭がシウバに敗れた後も、たまたまのことと見る向きは強かったが、同年11月の再戦でも桜庭は敗退してしまう。
同年にはK-1出身のミルコ・クロコップの台頭もあり、以後、総合格闘技は“打撃もグラウンドもできるトータルファイターしか通用しない”時代へと、急速に移行していくことになる。




















 社会
社会