さらに、互いの国境を超えたカネ(資本)の移動に制限はない。加えて、シュンゲン協定により加盟国間の「ヒト」移動についても国境検査が行われない状況になっている。
経済の三要素とは、モノ(&サービス)、カネ、ヒトである。EUやTPPに代表されるグローバリズム的政策とは、モノ、カネ、ヒトという経済の三要素の「国境を超えた自由」を実現するものなのだ。
各要素のモノ、カネ、ヒトの動きを自由化するとは聞こえがいいが、これは各国の国民や企業について「国家という共同体による保護をなくす」という意味でもある。
関税とは、自国企業、自国市場を外国企業から守るための「盾」だ。サービスの分野における各種の規制、ルールとは、その国が歴史的に育んできた文化、伝統、慣習に基づいている「法律」のことである。
資本移動の制限や外資規制とは、各国の企業や投資家に「自国の国民経済」のために投資(工場建設など)を行うインセンティブ(意欲への刺激)を与える。同時に、自国の重要資産(インフラ、放送局など)への外国人の投資を制限するのは、これは国民国家として当たり前の「主権」だ。
観光客はともかく、労働者の国境を超えた移動の自由を制限することは、国民所得の水準(=人件費の水準)が異なる国々の労働者の流入により、自国の雇用が奪われる事態を防止する意義を持つ。
ゆえに、国家という共同体が持っている関税や各種の規制、制度、ルールは、その国の国民や企業を保護し、国民経済が内需中心で健全に成長するための武器・盾なのだ。
内需、すなわち国内の需要が拡大することは、国民の所得増大とイコールになる。とはいえ、政府による各種の規制が強すぎると、民間企業や投資家が自由にビジネスや投資を行えず、国民経済における潜在GDP(供給能力)が成長しない
故に、各種の規制は可能な限り緩和もしくは撤廃し、自由な競争が行われる市場を「国家」の上に位置させるべし。以上が、1980年代以降に世界で広まった新古典派経済学、新自由主義、あるいは構造改革主義の本質だ。この種の規制緩和を「国境を超えて、実施するべき」という考え方が、まさにグローバリズムなのである。
EUは欧州におけるグローバリズムの結実であるが、それをより究極的な形に押し進めたのが「共通通貨ユーロ」である。共通通貨ユーロに加盟している国々は、関税に加えて、為替レートという「自国企業」を保護する手段を喪失している。
結果的に何が生じたかといえば、もちろん「市場ルール」という国家の枠を超えたルールに基づく「弱肉強食」の市場競争である。
日本のマスコミは、ユーロを単純思想で「グローバリズムが実現したユートピア的世界」として報じるのみだ。現実のユーロは、決してユートピアではない。むしろ、「サバンナ」的な状況が、共通通貨ユーロにより発生しているのである。
ユーロ加盟国は、それぞれが関税自主権や対ユーロ諸国の為替レートの変動という「盾」を喪失している。結果的に、ユーロ加盟国は、外国から輸出攻勢を受けた際に、「関税で自国企業を保護する」ことも「為替レートの引き下げで、自国企業を保護する」こともできない。
結果的に何が生じるかといえば、生産性が高いユーロ加盟国が、ひたすら生産性が低いユーロ加盟国への輸出を拡大していく「サバンナ」の出現である。
例えば、ドイツとギリシャの生産性の違いは、これはもう「圧倒的」だ。生産性が異なる国同士が関税や為替レートといった「盾」なしで戦うと、ストロー級のボクサーとヘビー級のボクサーが、同じルールで殴り合うような有様になる。生産性が低いストロー級のボクサーの側には、全く勝ち目がない。
読者のほとんどがご存じないだろうが、ギリシャには自動車企業がない。だからといって、ギリシャが車社会ではないかといえば、そんなことはない。ギリシャの鉄道や公共交通網は、日本に比べると悲しくなるほど貧弱だ。国民は基本的には、自動車を運転して移動するしかない。
それにもかかわらず、ギリシャには「国民車」が存在しない。公共交通網が貧弱で、かつ国民資本の自動車企業が存在しないギリシャは、現在はドイツ車を始めとする外国車で溢れている(主にドイツ車、イタリア車、日本車、韓国車など)。
それほどまでに自動車に対する需要が大きいのであれば、ギリシャ国民車が誕生しても良さそうなものだが、現実には不可能だ。何しろ、ドイツ車やイタリア車など「ユーロ加盟国」の自動車に対しては、ギリシャは関税をかけることも、為替レート引き下げで輸入を防止することもできない。
ギリシャ企業が自動車生産に乗り出したとしても、生産性の違いを埋めることは不可能で、結局、ギリシャ国はドイツなどから自動車を輸入し続けるしかないのだ。
ギリシャなどの低生産性国が、ドイツなど生産性が高い国々から自動車等の製品の輸入を続けた結果、ユーロ圏では「経常収支のインバランス」が拡大していった。経常収支のインバランスが何を引き起こすかは、次回以降、解説していく。
ところで、ギリシャがドイツから自動車を輸入し続けるということは、自国で「自動車関連の雇用が創出されない」という意味だ。「関税なし、為替レート変動なし」という「ガチンコのリング」でストロー級ボクサー(低生産性国)とヘビー級ボクサー(高生産性国)が統一ルールで殴り合った結果、ユーロ圏は綺麗に「勝ち組」と「負け組」に分かれていった。
勝ち組、負け組の判定が最も明確に出るのは失業率だ。'13年1月時点の失業率の数値を見れば、勝ち組と負け組の差は「圧倒的」である。
この状況で、負け組に対し勝ち組が「負け組の失業率が上昇しているのは、自己責任」と切り捨てるのがグローバリズムなのだが、読者はいかなる感想を抱いただろうか。
三橋貴明(経済評論家・作家)
1969年、熊本県生まれ。外資系企業を経て、中小企業診断士として独立。現在、気鋭の経済評論家として、わかりやすい経済評論が人気を集めている。












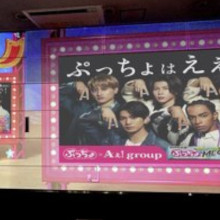










 芸能
芸能





