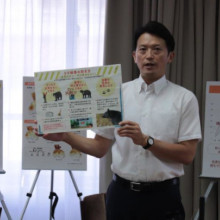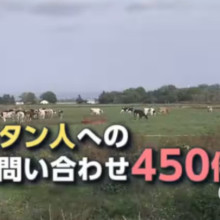平成10年7月、橋本龍太郎首相退陣を受けて首相に就任した小渕恵三に対する世間の反応は、何とも冷ややかなものであった。当時イケイケの議員だった田中真紀子(後に外相)からは小泉純一郎への「変人」、梶山静六への「軍人」と共に「凡人」とキメ付けられ、米国のマスコミからは取り立てて強いリーダーシップも窺えない“味気のなさ”から「冷めたピザ」との酷評も頂戴した。政権発足時の内閣支持率もわずか20%程度と、異例の低さだった。
しかし、政権の座にすわった小渕は内政・外交とも一変したかのように次々と大胆な決断力を発揮、世論の懸念は徐々に氷解し、ジリジリと右肩上がりの支持率を見せていった。内政では折からの不況下、前任の橋本首相が掲げた「財政構造改革」を思い切ってタナ上げし、政権運営の照準を景気回復一本に定める一方、中央省庁改革法、国旗・国歌法など、それまでの政権の懸案法案を次々に成立させていった。また、外交も韓国との間で日韓共同宣言、中国とも同様に共同宣言を発表、両国に譲るところは譲りながら、その歴史認識の国益を頑固に守り抜いて見せた。こうしたことを背景に米国メディアなどはやがて手のヒラを返し、冷めたピザに「風味が出てきた」などと報じたのであった。
その小渕は、当選、落選を繰り返す代議士だった父・光平の跡を継いで政界入りを果たした。早稲田大学文学部で学ぶ一方、雄弁会のサークルに所属していた。筆者も一時その雄弁会にいたのだが、当時の先輩から、次のようなエピソードを聞いたことがある。
「小渕先輩は、雄弁会一、二を争う生マジメさだった。同じ先輩たちがよく怪しい“新宿2丁目”の青線に出入りしていたのに、誘っても絶対に行くことはなかったと聞いた。その上で、オレがオレがタイプの多い雄弁会の中でも口数が少なく、人と争うことをしなかった。しかし、一方で物事がモメたとき、小渕さんが一枚加わると不思議に合意が生まれたそうだ。雄弁会史上、人柄ではダントツの小渕さんだったとされている」
政界入り後もそうした小渕の姿勢は変わることなく、常に一歩引いた発言が目立った。表題の言葉もそうで、後に首相となったあとも「オレは“真空総理”だから、自分から考え方を押し付けないから対立することがない。無、空ということなんだナ」とも言っていた。表題にある「(周りに対する)『お疲れさま』の一言で、ここまで来ることができた」はむろん謙遜の弁にほかならないが、政界入り後も万事が一歩引きながら、ひたすら合意形成に努めたということだった。
こうした手法は学生時代の雄弁会当時からの延長線上にあるが、一方で、これは竹下登元首相のもとでさらに磨かれた合意形成手法と言えた。竹下についてはこの連載でも以前に触れているが、徹底的に一歩引いたリーダーシップで合意形成を固めていったそれまでに稀有な首相であった。なるほど、小渕は政界入り後、この竹下を「政治の師」とし、長く側目にいたのである。竹下も小渕をかわいがり、竹下内閣では官房長官を任かせた。昭和天皇崩御の際の新元号「平成」を記者会見で発表した姿が記憶に残る。竹下が亡くなる前年、その竹下に、筆者は弟子としての小渕の人となりを質した思い出がある。
「小渕は若い議員によく言ってたわナ。『謙虚であれ、誠実であれ、勇敢であれ』と。これを小渕に言わせると、“三あれ主義”ということだった。しかし、キレ味は見せないが合意形成づくり、したたかさはひょっとするとオレより上かも知れん。譲るべきは譲るが、貫くところは貫く決断力がある。昨年(平成11年)秋の自民党総裁選再選時、挑戦を受けた加藤紘一と山崎拓を、その後の改革人事でピシャッと斬り捨てた。あれがいい例だ。オレにはあそこまではできない。実は、神経は相当に太い男だ」
小渕自身は度々会っていた筆者に、穏やかな表情でよく言っていたものだ。「平凡に勝るものはないね」と。小渕流の常に一歩引きながら、しかし、したたかなリーダーシップ、合意形成法は一考に値する。
一時は「日本初の女性首相候補」との名が高まったが、“政治とカネ”で謹慎を余儀なくされている小渕優子前経産大臣は、その娘である。
=敬称略=
■小渕恵三=第84代内閣総理大臣。総理府総務長官(第29代)、沖縄開発庁長官(第10代)、内閣官房長官(第49代)、外務大臣(第125代)などを歴任。総理在任中の平成12年5月、脳梗塞が原因で死去。享年62歳。
小林吉弥(こばやしきちや)
永田町取材歴46年のベテラン政治評論家。この間、佐藤栄作内閣以降の大物議員に多数接触する一方、抜群の政局・選挙分析で定評がある。著書多数。