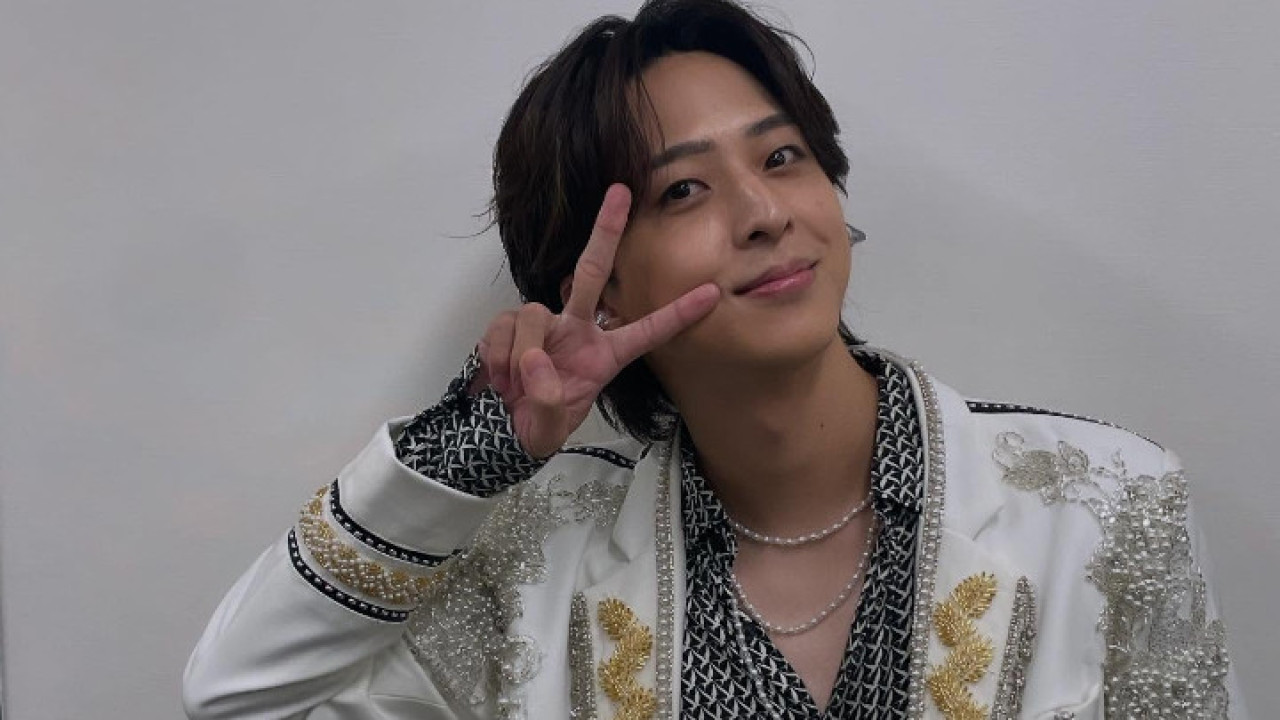決して、寡黙というわけでもないが、マイペースな田上は、試合後、まともな話をしてくれない。いつも、「くたびれた」といったような調子。それが、たとえ大一番の前であっても、「絶対に勝ちます!」なんて、大きなこともなかなかいってくれないものだから、記者としてはお手上げだったのだ。
そんな田上が、三沢光晴が亡くなった後、プロレスリング・ノアの社長に就任するなど、その数年前に誰が予想したか? 田上は192センチという日本人としては類まれな長身を生かし、大相撲の押尾川部屋に入門し、1980年初場所で初土俵を踏む。後に、師匠の押尾川親方の現役時代のしこ名(大麒麟)から“麒麟”をもらって、玉麒麟と改名し、将来を大いに嘱望された。86年夏場所で新十両に昇進。新入幕が期待されたが、87年名古屋場所の直前に廃業した。その理由は師匠との確執といわれている。当時まだ26歳で、その素質からして、相撲を続けていれば、幕内昇進はかなり高い確率で果たしていたはずだ。
浪人となった田上は、その体格を生かすべく、プロレス転向を決意。天龍源一郎ら多くの大相撲出身者のいる全日本プロレス入りを決め、同年8月にプロレス界の門を叩く。しかし、当初は長州力率いるジャパン・プロレスに入門する。これは、あくまでも“表向き”の措置。前年に全日本は相撲界とトラブルを起こした元横綱・輪島大士を入団させたばかりとあって、相撲界とのあつれきを避けるためだった。
88年1月、予定通り、全日本に移籍すると、同月2日、前座をすっ飛ばして、ジャイアント馬場とのタッグで、外国人選手相手に破格のデビューを果たす。しかし、田上は伸び悩み、ふがいないファイトが続いていた。転機となったのは、新団体SWS設立に伴う、天龍らの大量離脱騒動だった。ジャンボ鶴田のタッグパートナーに抜てきされた田上は、三沢、川田利明、小橋健太(現・建太)らの超世代軍や、スタン・ハンセンら大物外国人選手とのビッグマッチで力をつけていき、92年3月、鶴田とのタッグで世界タッグ王座に初戴冠。その後、鶴田が肝炎のため、第一線を退くと、川田らと聖鬼軍を結成。川田とのタッグでは、「世界最強タッグ決定リーグ戦」を2度制し、世界タッグ王座には実に6度就くなど、後にプロレス史に残る名コンビとなった。
シングルプレーヤーとしても、メキメキ実力を上げ、96年春には「チャンピオン・カーニバル」を初制覇。同年5月には、三沢を破って、3冠ヘビー級王座を初めて奪取。三沢、川田、小橋と並ぶ“四天王”として活躍した。生来、マイペースで、欲があまりなく、自己アピールなど、とんと縁がなかったが、ここ一番の大勝負となると、大爆発することから、その様は“田上火山”と称された。
2000年にノアに移籍してからは、力皇猛、森嶋猛ら、若手選手の台頭もあり、タッグパートナーに恵まれなかったこともあって、なかなかチャンスがなかった。だが、05年11月、ファンの後押しを受けて、力皇の持つGHCヘビー級王座に挑戦。見事にチャンスをモノにして、同王座を奪取した。これが、シングル、タッグを通じ、唯一のGHC王座戴冠となった。
三沢の不慮の死後、09年7月に2代目ノア社長に就任すると、その性格もあって、あっさりトップ戦線から退き、後にスポット参戦となる。そして、13年12月7日、東京・有明コロシアムで引退試合を行い、現役生活に別れを告げた。
現役を退いてからは社長業に専念している。社長になってからも、マスコミやファンの前で、しゃべるのは好まず。必要最低限のことしか話さないため、今でも記者泣かせであるのは変わらない。
“田上火山”が爆発しない時は、ファンをやきもきさせることも多かったが、田上もまた、日本プロレス史に残るレジェンドだ。
(ミカエル・コバタ=毎週水曜日に掲載)


































 社会
社会