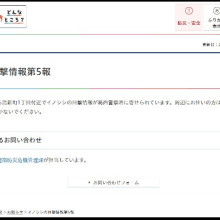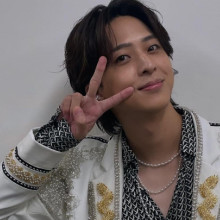区役所のある場所はよい立地どころか、あまり利便性がよくないと思われる場所であることが多い。たとえば千代田区は東京駅ではなく東京メトロ九段下駅、中央区も同新富町駅、港区は都営地下鉄御成門駅で、これらはターミナル駅でもないし、決して駅として資産性の高そうな駅とは言いにくい。
品川区は東急大井町線の下神明駅、世田谷区はチンチン電車風の世田谷線の松陰神社前、杉並区は丸の内線の南阿佐ヶ谷駅、足立区は東武スカイツリー線(旧伊勢崎線)の梅島駅か五反野駅、葛飾区は京成立石駅、江戸川区に至っては都営新宿線の船堀駅からバスを使わなければならず、歩ける距離ではない。
実際、これらの駅はその行政区の中でも割安な立地である。そうした立地でも区役所の周辺で総じて資産性が保たれるのは、どこに理由があるのだろうか。
しかも日常生活の中で、特別な用事がある場合以外に役所に行く機会はそれほど多くない。役所へのアクセスがいいという利便性だけでは、マンションの資産性が高いことの説明にはならない。
しかしよく考えると、区役所立地の中には、区の中心をイメージさせる駅が多い。例えば新宿区役所は、巨大ターミナル新宿駅に近い、台東区役所も歌にも多い上野駅、墨田区役所は東京メトロか東武スカイツリー線の浅草駅、大田区役所の蒲田駅、渋谷区役所の渋谷駅、中野区役所の中野駅、練馬区役所の練馬駅などだ。
このように区の名前と駅の名前が同じところも多い。ということは、役所以外に商業施設も含めてオフィスや商業ビルが多く、色々な機能が集積している場所だといえる。つまりこうした事例から「区役所のあるところは区の中心地」というイメージが刷り込まれていると考えてよさそうだ。
都庁のように大江戸線が引かれたりする例を見ると、時間をかけて「中心地」を形成していく可能性も高い。目黒区役所に近い中目黒駅は、目黒区の中心になりつつあるし、千代田区の九段下駅は、高級住宅地の番町の近くで、不動産価値を高めている。また、板橋区の板橋区役所前は、都営三田線の駅名になって知名度を上げている。こうしてみると再開発計画が浮上しやすい区役所周辺は、値上がりしやすいといえるのだ。