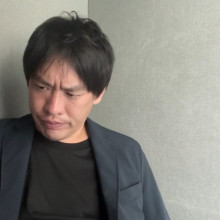智弁学園は強豪、伝統校としても知られるが、全国制覇は初めて。奈良勢のセンバツ優勝は97年以来19年ぶりとなる。
同校を指揮する小坂将商監督は、大会前、「投打の柱に頼りすぎない野球を」と、各メディアの取材で答えていた。近畿地区の野球関係者によれば、センバツ初戦で途中からレフトを守った藤田和樹や、他控え選手のなかにも秋季大会のマウンドを務めた投手がいたという。「中心選手に頼りすぎない野球」と聞くと、投手の数人体制による継投策がイメージされるがそうではない。同校の勝因は近畿準々決勝(秋季大会)での敗戦から学んだチーム作りにあるようだ。
昨年10月25日、滋賀県大津市・皇子山球場。同校は大阪桐蔭に敗れた。スコアは4-9。スタンドから見た感想は「力の差」。関係者によれば、両校は同3月に練習試合を行っていたという。大阪桐蔭がセンバツ大会に臨む直前であり、同校にすれば、実力のある智弁学園と試合をすることで実戦感覚を磨いておきたかったのだろう。
「練習試合で、大阪桐蔭は村上頌樹が屈指の好投手だと認めました。そのときのイメージから対策を練り、近畿大会の勝利につながりました」(関係者)
その村上が打たれ、3イニング目に6点を失った。その後は防戦一方だった。打の中心である太田英毅(新二年)もヒット1本を打つのがやっと…。だが、智弁学園が一矢を報いたのは“選手層の厚さ”。人数は新三年生と新二年生を合わせ、33人(センバツ公式プログラムより)。マンモス野球部ではない。途中出場の選手たちがヒットを連続し、コールド負けを防いだのである。
どの学校もそうだが、日曜日の練習試合では第一試合と第二試合で何人かのスタメン選手が変わる。レギュラーの控え選手の力量差で「第二試合が凡戦になる」ことも多いが、智弁学園にはそれがない。
このセンバツを戦った打線にしても、そうだ。第一試合では岡澤智基捕手が1番を務めたが、その後は納大地二塁手が1番で岡澤捕手は2番にまわった。秋季大会では3番の太田遊撃手が1番を任された試合もあった。
選手層の厚さとは、人数の多さだけではない。レギュラーと控え選手の力量差を小さくすることであり、投打の中核選手がマークされたときに、チーム全体で1点をもぎ取っていかなければならない。誰かがマークされても、チームはガタガタにならない。
昨秋、大阪桐蔭に敗れた後、智弁学園は投打の中核が徹底マークされたときにどうすべきかに取り組んできた。チーム全体を底上げする。これが、トーナメントを勝ち上がっていく高校野球の戦い方である。(スポーツライター・美山和也)


























 芸能
芸能