私とTは高校時代の同級生で、大学進学後も親交のあった男である。高校でもトップクラスの成績を収めるインテリタイプの男であったが、オカルト趣味の私と何故か気が合った。
「何かにこだわる姿勢は大事やからな」
Tは私のオカルト研究に理解を示した数少ない友人の一人であったのだ。後にTと私は共に関東の大学に進学し、関東周辺の魔界探索に明け暮れる事になるのだが、同時期、Tは不思議な体験に、二回遭遇する事になる。
2004年の7月、私は都内でTと軽く酒を呑んだ。東京を離れ、徳島にUターン就職した奴と会うのは4年振りであった。いまだに独身貴族を気取るTだが、お互い既に30代後半になっていた。
「お互い歳とったな〜」
「何言よんぞ、わいはまだ若いぞ〜」
Tは屈託なく笑った。ノリの軽さは学生時代のままである。
「ほんなんやったら、早く年貢を納めて結婚せいだ〜」
「う〜ん、見合いの話はあるんやけどな〜」
Tはうまく話をはぐらかした。どうやら結婚という束縛は嫌いのようだ。
最も私も今になって結婚に伴う責任の重荷はよくわかる。
だから友人にはおいそれとは勧められない。
そんなこんなで酒を呑み、馬鹿な話をしながらも、私はTが学生時代に経験した怪異談が気になって仕方なかった。
「おい、あの話をもう一度聞かせてくれへんか」
私は単刀直入に切り出した。
「なんな〜酒の席でも怪談の取材かいな」
Tは、私が持参した最新の拙著を眺めながら、にやりと笑った。
「あの、トンネルの事件から頼むわ〜」
「あれか、気色悪い経験だったな〜」
Tの箸が止まった。思い出すように遠くを見ている。
当時、大学2年だったTは、楽しみにしていたサークルの合宿を、独り早めに切り上げて東京にある自分のアパートに車で向かっていた。
本当は最終日までいたかったのだが、どうしてもはずせない用事ができたのだ。
「くそ〜あせるな、ほんまに」
Tはややご機嫌斜めであった。そして、運転もいつもより若干乱暴であった。
スピードがいつもより余計に出ていたかもしれない。
Tご自慢の愛車のタイヤが、微かに悲鳴をあげている。
「ああっ〜ねむ〜」
気が緩むと瞼が閉じてしまう。
睡魔と戦いながらTは運転を続けた。
「あの娘、どうしてるかな〜」
当時Tには気になる女の子がいたのだ。合宿はまたとないチャンスである。
それが、自分だけ戦線離脱とは…
ある部分、納得いかない部分もあったのかもしれない。
「次は絶対最終日までおるからな〜」
Tは、怒るようにつぶやいた。
兎に角、いつもは仲間と一緒に移動する車である。
深夜の単独ドライブ程つまらないものはない。
たった独りで無機質な夜のアスファルトを睨むだけだから、
心の中に退屈な気分が持ち上がって来ることを、押さえきれない。
「ああ〜誰でもいいから、隣りにおればな〜」
Tは、眠い目をこすりながら、ハンドルを握り続けた。どのくらい走ったであろうか。
Tの車は神奈川県の某道路に入っていた。この道路はトンネルが多いので有名である。
「…なんや、随分トンネル多いな」ブツブツ言いながら、Tは慎重に運転を続けた。(いかんいかん、慎重に運転しないと…)
Tのハンドルさばきが軌道修正された。
とかく夜間のトンネルは事故を起こしやすい。
「…んっ あれは」
Tは自分が視覚で捕らえたものが何か、最初は理解できなかった。
「まさか…でもそうだろうな …たぶん」
Tはその物体を注視し続けた。
ちょうど車の進行方向にあるトンネルの前に浮いている。
そう浮いているのだ。
「………」
Tの見たものは、横たわった人間であった。しかも透明で向こう側が透けて見える。透明で空中に浮いているのだから、間違いなく幽霊だろう。(でもなぜ横たわっているのだ?)Tはそれが疑問であった。幽霊なら普通立った姿で出てくる。それがなぜ横たわっているのだ。
「ひょっとしたら」Tの脳裏に結論めいたものが浮かんだ。
あれは遺体なのだ。土葬された遺体なのだ。だから、幽霊は土葬されたままの状態で出て来るんだ。
Tはハンドルを持つ手に、じんわりと汗を感じた。
文:山口敏太郎 監修:山口敏太郎事務所









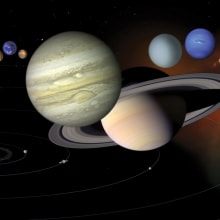





















 芸能
芸能








