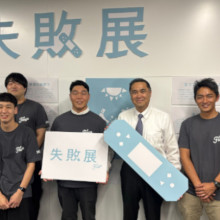江戸期から続く名門で、その屋敷は築百年を越えていた。庭も大きく、その屋敷は付近でも豪邸と呼ばれていた。
しかし、昭和五十年代の石油ショックに巻き込まれ、Gさんの父は破産。どうにか、屋敷は残ったものの、両親が共働きで莫大な借金を返さねばならなくなった。
坊ちゃん生活から困窮生活への暗転。だが、Gさんはめげることはなかったという。それからのGさんはいつも学校から帰ると、夜まで1人で過ごした。
広大な屋敷を1人で留守番するのは、少年にとって恐怖以外の何物でもなかった。だが、父や母の働く姿を見て、自分も負けてはならぬと心に決めたのである。
ある夜の事、Gさんがテレビを見ていると、突然テレビが映らなくなった。
「なんだ、こんないい場面で、まったく酷いな」
Gさんは、違法電波の影響だと思った。少年時代からハム無線にはまっていた彼は、当時北陸で度々確認されていた奇妙な電波の影響だと思ったのだ。事実、付近には違法電波の発信源と思われる箇所があった。
だが、それは大きな勘違いだとわかる。
「ふおーい。ふおーい」
地底から響くような低い声が、聞こえた。魔物が泣いている、そんな感じの声だ。鳥肌が立つぐらい不気味である。なんともいえない程の寒気が襲ってくるが、この声の主を確認せねば気が治まらない。
ひょっとして、父が呑んで帰ってきたのか。
「父さん、また、お酒を呑んで帰ってきて、困ったもんだな」
Gさんは無理に自分に言い聞かせると、玄関に向かった。しかし、誰もいる様子はない。薄暗く、静まりかえっている。ガランとして、無人の玄関。
突如、静寂が破られた。
「ふおーい。ふおーい」
再び、不気味なうめき声が聞こえたのだ。よく聞くと、声は縁側の方から聞こえてくるようだ。おかしい、いつのまに庭の方に廻ったのか。Gさんは、ぶつぶつ言いながら庭に廻った。
「うわっ」
そこに、奇妙な物体があった。黒くてぶよぶよと動いている。庭と縁側の間を仕切る為に設けられたサッシで異物を目撃したのだ。
「なっ、なんだあの物体は」
絶句し、立ちつくすGさん。確かに自分の視界に信じられない物体が写り込んでいる。全身真っ黒で、どろどろと溶けた塊がサッシにへばりついている。どう見ても、この世のものではない。
そして、サッシの隙間から僅かに匂う異臭。まるで、生魚が腐ったような臭いだ。
「なんだ、この動物の死体が腐ったような臭いは」
そして、その物体は、こう叫ぶのだ。
「ふおーい。ふおーい」
背中に冷や水を浴びせられたような悪寒と恐怖を感じた。見てはいけないものを見てしまった。口はがくがくと震え、上と下の歯が噛み合わない。
「あああわわっ」
口を開けたまま、腰を抜かした状態でそこから逃げ出す。どうしても、腰が立たない。虫のように這いずりながら、逃げ出した。
「たっ、助けて」
2階の自室に閉じこもり、ドアにカギをかけると、布団をかぶって震えていた。
「あの異物は、いったい、なんなんだ」
何度もあの異様な姿を考えてみる。しかし、今まで見たどんな生物にも当てはまらない。震えながら、自分の体に付着しているあの物体の匂い。自分は確かにあの異物と遭遇したのだ。
「この臭い、とても生きている物体ではないぞ」
脳の中で更に恐怖がリピートされた。彼の心に、あの黒い異物が何度も襲いかかる。恐怖と混乱でいつしか彼は失神してしまった。何時間か過ぎた頃。彼は深夜に帰宅した父に起こされた。
「どうしたんだその顔。まるで幽霊でも見たみたいだぞ」
父は背広を脱ぎながら、軽口を聞いた。
「化け物だよ、黒くて臭い化け物を見たんだ」
「おいおい、冗談だろ」
父は笑っている。Gさんは父に詳細に目撃談を説明したが、いっこうに信じてもらえず、笑われてしまった。
「そんな馬鹿な。夢でも見たんだろう」
父はそう言うと、笑いながら風呂に入ってしまった。すると、翌日、不気味な出来事が起こった。
ちょうど庭を接している隣家のおじさんが、脳溢血で亡くなったのだ。あの物体は死の前兆なのか。彼の恐怖は再び強く強く心を締め付けた。
以来、黒い物体は、知人や肉親など、身近な死に付随して現れた。まるで、死に便乗して姿を現す死神のように。
黒い物体と人間の死はセットのように、何度も彼の前で展開された。
「あいつは、死神だ」
Gさんは自分が見た黒い物体をそう思ったという。
監修:山口敏太郎事務所









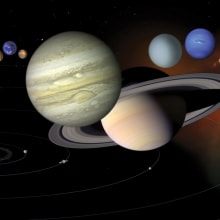




















 芸能
芸能