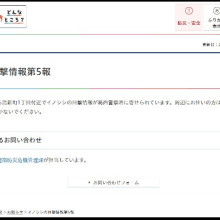「中には千葉の私の家に寄ってくださる方もおり、そういう場合には、魚がおいしい勝浦や成田山を案内したりしました。勝浦の海中公園なんかは喜んでくれましたね。私は運転しないので、そういう時は家内が運転してくれました。家内は最初の5年は留守番役で、後半の5年は私と一緒に、家族ぐるみでご遺族のお世話をさせていただいたという感じです。細々とですが、ご遺族とのそうした関係は今も続いています。去年も、私が最初に担当した和歌山のご遺族が『千葉の落花生が欲しい』というので送ったら、すぐに御礼にミカンを送ってくれました。今では本当の親戚のような関係になっています」
現在、天野氏は体調を崩し、酸素ボンベが手放せないが、本誌の取材に丁寧に答えてくれた。とくに、天野氏が最後に語った言葉が印象的だった。
「ご遺族と親戚付き合いができたということは、私にとって生きるための勉強ができたことだと、今では思っています」
もう一人、前出の伊藤氏が忘れられない人物がいるという。
毎月、わずか6万円の給料で「御巣鷹山の管理人」をしていた仲澤勝美氏だ。雨の日も風の日も山に登り、遺族に頼まれれば代理で墓に線香を手向け、花を添えることもあった。
伊藤氏が言う。
「私が観音様を建立する際、旧道の見返り峠からも観音様が拝めるようにと大木を何本も伐採してくれたり、『安全の鐘』の設置にも協力してもらったり、亡くなった方々の墓標を作ったりと、もう本当に筆舌に尽くしがたい働きをしてもらいました。彼がいなければ、遺族が安全に集える今の御巣鷹山はなかったといってもいいでしょう」
御巣鷹の麓、群馬県上野村で生まれ育った仲澤氏は、若い頃は村で一番の暴れん坊として有名だったというが、一時は村議も務め、晩年は山守として18年間も遺族に寄り添った。
ある日、仲澤氏から「助けてくんろっ!」という電話が伊藤氏のもとに入った。山の尾根にある木のイスが朽ちて、慰霊登山に訪れた人が怪我をしたというのだ。
「村にはイスを新しくする予算はないし、ほとほと彼は困った様子でした。それで、私がスチール製のベンチ20個を寄付したんです。一つ20キロもするベンチを、私の会社の社員たちが文句一つ言わず山の上まで担ぎ上げてくれましてね。勝っちゃん(仲澤氏)にたいそう感謝されましたが、長年、たった一人で山を守ってくれた彼に、私のほうが感謝の気持ちでいっぱいでしたよ」(伊藤氏)
そんな仲澤氏も、'06年に86歳で旅立った。
「御巣鷹山を守ってきた男・仲澤勝美のやってきた事を山に残したいという思いから、彼の名前を彫った供養塔を観音様の横に建てました。それと、退職後も遺族のケアを続けた天野さんのこと。2人の男の生き様を、どうか皆さんに覚えておいてほしいのです」(同)
事故後30年という一応の区切りはついたが、すべての関係者の脳裏から、あの日の記憶が消え去ることはないのだろう−−。