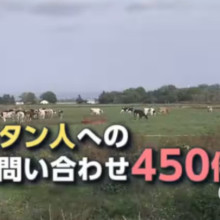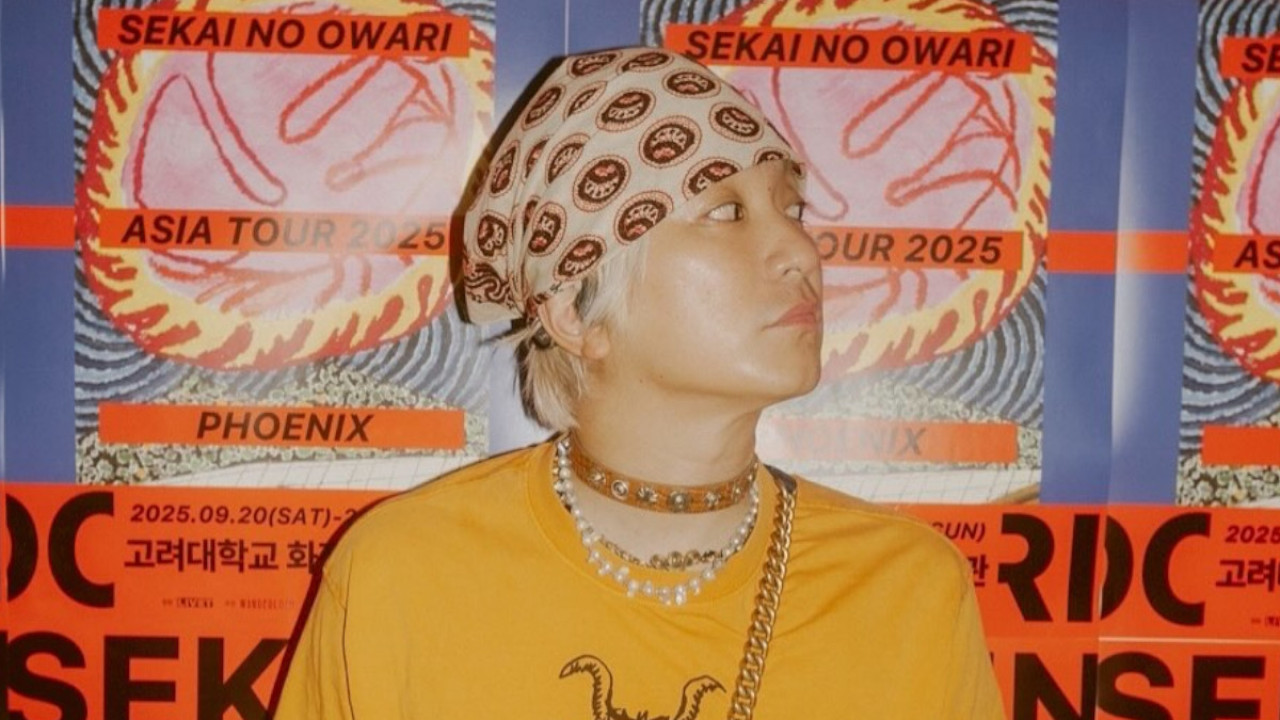東京電力を国有化すること自体への批判は、たくさんある。たとえば、日本経団連は、「政府が経営して、うまく行った企業がどれだけあるのか」と批判している。それに対して枝野経産相は、「民間で経営しますと手を挙げるところがどこにあるのだ」と選択肢のなさを強調している。
国有化の是非は別として、私は、今頃になって国有化を言い出すのなら、原発事故直後に東電を経営破たんさせて国有化した方が、国民負担はずっと少なかったと思うのだ。
原発事故直後、東電の経営は明らかに債務超過の状態にあった。莫大な賠償金の支払いが降りかかってくるのが確実だったからだ。ところが、政府は東電を経営破たんさせなかった。その効果は、破たんをさせていたときと比べるとわかりやすい。
もし東電を債務超過だとして、即座に経営破たんさせたら、その時点で東電の株式は紙くずになった。株主の持ち分はゼロである。ところが政府が東電を守ったため、東電株には3月末で208円の株価が付いて、時価総額は3343億円となっている。法律上は、いまのところ東電はこの株主のものだ。だから、政府は完全な国有化を実施しようと思ったら、この時価総額分を買い取らないといけない。つまり経営破たんをさせた場合と比べてその分、余分にコストを抱え込んだことになる。
もっと大きなコストは、東電が抱えている借金だ。東電は、有利子負債を8兆円も抱えていた。東電を債務超過で経営破たんさせていれば、この借金も棒引きになった。8兆円分の焦げつきは、東電に融資をしている銀行や社債を持っている投資家が負担することになった。政府は、それでも賠償額に足りない分だけを税金で補填すればよかったのだ。
そして必要最低限の資本注入をしたうえで、東電の株式を売却する。買い手はいくらでもいるだろう。原発賠償から解放された東電は、確実に儲かる最強のビジネスモデルを持っているからだ。事故前の時価総額である3兆円程度で売れるかもしれない。そうなれば、売却益で、投入した税金のほとんどを回収できるかもしれない。
では、なぜこのシナリオが採られなかったのか。公益企業だから経営を混乱させるわけにはいかなかったなどというきれい事ではないだろう。経済産業省が東電の利権を手放したくなかったというのが、一番大きな理由ではないか。
規制緩和の流れのなかで、経済産業省の利権はどんどん縮小している。東電は、経済産業省にとって絶対に手放したくない利権の宝庫なのだ。もし、いきなり経営破たんさせてしまったら、この利権が吹き飛んでしまう。東電を民間が買いにくいようにしてから国有化する本当の理由は、東電を経済産業省のものにしたいという官僚による火事場泥棒なのかもしれない。