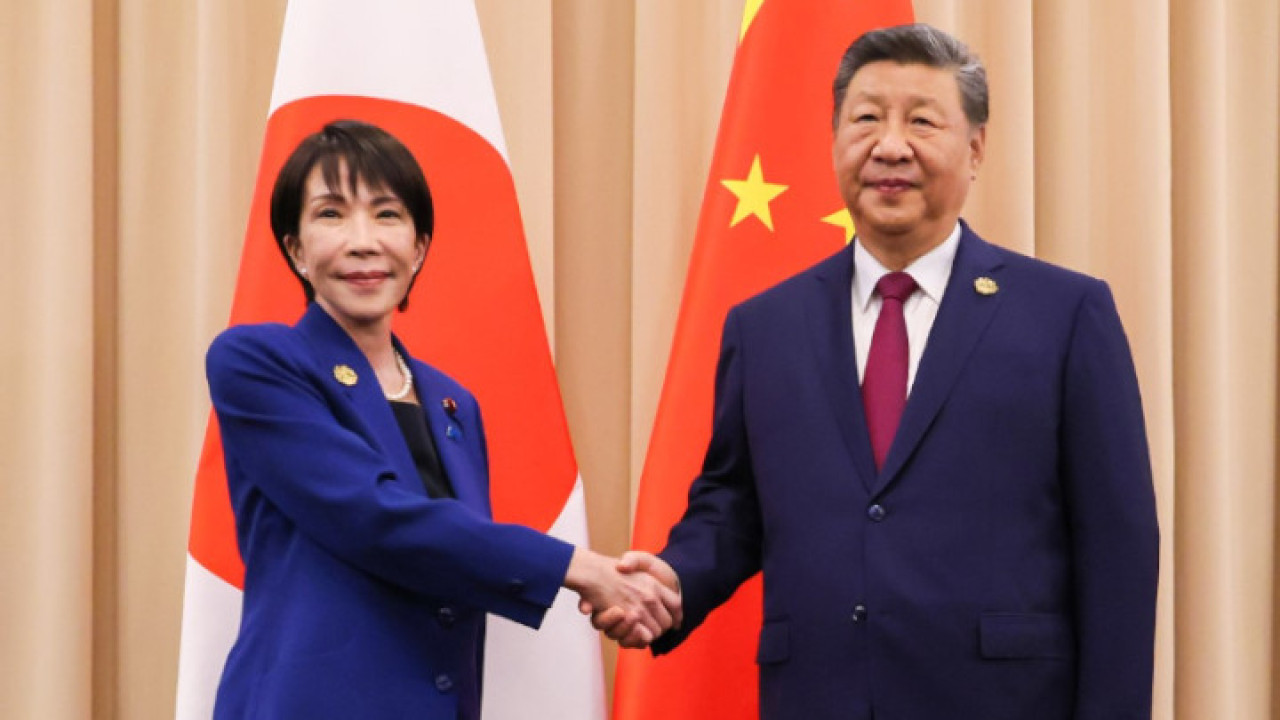こんな面白いことを言っていたのが、塩谷又三郎、池上岩男の2人。先行一本で戦っていたが、一発屋の魅力十分な選手だった。
マーク屋の林栄和はいっとき「近畿のしきり屋」として、番手を決めていた時期があった。特別競輪ではそんな彼の言っていたとおりのレース展開になっていた。ゴールの順位はともかく、展開がピタリと決まるのには驚いた。小柄だが競りもうまく勝負にかけては厳しかった。
安福洋一(41期)は東京で選手登録、西武園をホームバンクにしていた。もともと大阪の出身で、地元に戻って結婚してから奈良に転籍した。適性組で高校時代は400ハードル障害の選手だった。デビュー時には「必ず一流になって中野浩一を追い込む選手になる」といって猛トレに励んでいたが、頂点のS1に上がるのに9年もかかった。昭和62年の高松宮杯で(3)(3)(4)(5)で優参。平成7年の高松宮杯準決では三宅伸-小橋正義-本田晴美の岡山ライン4番手から追い込んで小橋の2着に入った。
「追い込み選手は1周で7秒だけ集中すればいい。その7秒間のために、一日7時間の練習をしてきた。同じ適性でも松本整(京都)は中野浩一と練習仲間だったが、わしは一本どっこや」という話を本人から聞いたことがある。
鈴木勝(45期)も適性組で、競輪学校では僅かに1勝しか出来なかったが、日体大陸上競技部ではヤリ投げ選手。基礎体力は、実戦ですぐに証明された。
追い込みを中心に時にはまくりも打ち、昭和60年の立川・日本選手権では(8)(5)失失と位置取りに厳しい選手だった。同年の一宮・オールスターでは(3)(1)(2)(9)と優参を果たした。いまはA級に落ちているが、若手の良きアドバイザーとして存在感を示している。





























 芸能
芸能